 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
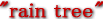 vol.10
vol.10 <詩>執筆者紹介(小池昌代)へ
<詩>執筆者紹介(小池昌代)へ
小池 昌代の詩 2 |
 反射光
反射光
 岸と橋をめぐって
岸と橋をめぐって 夕立
夕立 馬喰という名の土地で
馬喰という名の土地で
反射光
小池 昌代
(詩集『水の町から歩きだして』1988年思潮社刊より)
五月の光線が きりん缶ビールの つめたいアルミにくだかれている 細魚に似たかんじの 切れ長の目の男の子を産んだ妹 「魚じ満」にも五月 店頭に並んださかなの目が まちのみどりをうつし始める たとえば、こんな日 静かに席順が決められている 山奥の小さな小学校 ひんやりとした土のなかから 新品のコクヨのノートが掘り出される お昼をまわる頃 生徒たちの筆圧も弱まって とうさんが かあさんが ねえさんが おとうとが と、さかんに話し始めるこどももいる 山雨のあと 栞という字に 初めて惹きつけられている少女 かかとのうつくしい
 岸と橋をめぐって(小池昌代)へ
岸と橋をめぐって(小池昌代)へ 逃亡者(小池昌代)へ
逃亡者(小池昌代)へ岸と橋をめぐって
小池 昌代
(詩集『青果祭』1991年思潮社刊より)
倣岸というように 岸がその意味をつくっているとき わたしは岸という、孤独をおもってみる 川を中に流して えいえんに和することのない ふたつの岸のつよさをおもう かためて きりり くいいる けつだん こわごわ、ころして きびしい くぎょう…… なぜ、か行は多くくるしんでいるんだろう きし、も? 右岸と左岸に けれど、橋がかかるとき 橋はふたつの岸をとかし 人たちは、両岸の土を柔らかく同質化するだろう 橋の中央でてばなされ、交換される右と左 方角、あるいは日と影 橋がつくられるところを見たことがない ――月番の労働者が弁当を食べるのは、ここから見て、日のあたる右岸。 日陰の多い左岸には、古い自転車が一台、乗り捨てられてある。車体 を半分川につっ込んだまま、いつ行っても片づけられずにそこにある。 行くごとに少しずつ、さびついてくさっていくのがわかる。左岸とい う、ひびきを、わたしはあいしているようだ。
 夕立(小池昌代)へ
夕立(小池昌代)へ 反射光(小池昌代)へ
反射光(小池昌代)へ夕立
小池 昌代
(詩集『永遠に来ないバス』1997年思潮社刊より)
暗い雲がみるみるうちに あなたの顔をおおう 何もない皿の上 蛍光灯の貧弱な光があふれ わたしたちは じぶんのうちがわに 爪をたてて 声をころし 約束をさけた会話をしている この昼のくらさ わたしはふかいところによろこびをかくした 古代の植物のようにみしみしとほほえむ やがて 夕立 あなたの肩越しのぶあつい窓ガラス、そのずっとむこうに 夏のもっともあぶらじみてさびしい部分が めくれあがりあらわになってひるがえっているよ (緑の武士が古い馬具にまたがり 虹に重たい音をこすりつけて歩く) 室内の影たちはぼろぼろになって疲れ ものたちの配置はいよいよ確かだ わたしは部屋を出る どしゃぶりの雨のなかへ わたしはその姿をテーブルからみている ドアが閉まる固い音 その前後の空白に 室内の影たちが ぐったりとたおれかかる なまあたたかい、いきものの息を交わして 素足から透きとおり 大きな歓びの声だけをあげたい
 馬喰という名の土地で(小池昌代)へ
馬喰という名の土地で(小池昌代)へ 岸と橋をめぐって(小池昌代)へ
岸と橋をめぐって(小池昌代)へ(詩誌「Mignon bis 01」1998.5.25発行)馬喰という名の土地で
小池 昌代
馬喰という名の土地を歩くと 馬喰のなげきが聞こえてくる 寛政5年、弥生の月 じゃらじゃらとたずなを引きながら 一人の小柄な馬喰がいく 「おーい馬」 すると、いつしか雨が降ってくる 馬喰は鞍から蓑をとりはずす いぐさの匂いが雨をたたきおこし 馬喰は一瞬 ほんの一瞬 ふわっと、死にたいような気持ちになる 荷車ががたん、と通り過ぎる 賢そうな子供が駆け出していく 向こうからは盲の女乞食もやってくるだろう 折から橋の上にさしかかったところである と 馬は岩のように立ち止まって動かない とたんに股間からほとばしる 太い棒のごとき馬の小水 円柱の温かな洪水である 浅い春 そこにあたたかな湯気が立ち上る くらい空である やぐらがみえる 馬をひき 馬にひかれて 馬喰がいく 江戸の中期を 平成10年 東京日本橋 馬喰町の朝は早い 道いっぱいに通りすぎるトラック ダンボールの箱をいくつも運んでいるのは 倒産しそうなふとん屋の主人だ 従業員にはイラン人もいる 「まいど」と言っている 「おはよ」と言っている 馬も馬喰もでかけたままである 長い不在の時空のうえを ばらばらと 人々の靴音がかけぬけていく 「午後からたぶん、雨になるよ」 はるかとおくから鈴の音が聞こえ 疲れた一人の馬喰のなげきが 土地の下から湯気のようにたちのぼる 銭のこぼれる壮絶な道 そのなかを わたし、わたしという女乞食も 馬のようなものをひき 歩いていく
 <詩を読む>小池昌代の生まれたての詩(関富士子)へ
<詩を読む>小池昌代の生まれたての詩(関富士子)へ 夕立(小池昌代)へ
夕立(小池昌代)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |