
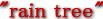 vol.24
vol.24 橋の下の家族
橋の下の家族 わたしの3人の妹は
わたしの3人の妹は 「植物地誌」レンゲソウ
「植物地誌」レンゲソウ
橋の下の家族
|
| | 橋の天蓋がつくる真ひるまの大きな影が
| | 宮殿の厚ぼったい絨毯のように
| | 川の流れに続く幅広な石段を
| | ふかぶかと覆う時刻
| |
| | 禿げた額をうやうやしく段にのせ
| | 腕を広げ両足を投げ出し
| | 橋の王が
| | ぐっすり眠っておられる
| | 酒に焼けた顔をさらに赤らめ
| | 頬をふるわせて鼾をかく
| | 古ぼけたシャツとズボンのあいだから
| | ふとい腹がはみ出す
| | 片方脱げたゴムぞうり
| | 頭のそばからラジオの大音響が
| | 宮殿の天蓋にこだまする
| | そのかたわらには
| |
| | 川っぷちの砂利の上に
| | ちりちりの白髪頭を広げて
| | 橋の王妃が
| | ごろりと横たわっておられる
| | 眉根を寄せて瞼を閉じ
| | 唇を断固としてひん曲げて
| | 激しい諍いの夢にうなされる
| | 固い床でしびれた耳のほとりを
| | たえまなく川が流れている
| | からのコップ酒や包装パック
| | たばこの吸殻やスーパーの袋
| | 饗宴の跡がひどく散らばって
| | 午睡する王と王妃をとり囲むように
| |
| | 五羽のハト
| | 三羽のカラスが
| | しずしずとやってきて
| | においたてる残飯から
| | 紐のようにこぼれた焼きそばをつつく
| | 臣下の数はしだいに増える
| | 川を横切ってくる二羽のカルガモ
| | ハエとカとそのほかの虫たち
| | イヌとネコとスズメたち
| | 尿の臭気に惹かれたアオスジアゲハ
| | クロアリの行列
| |
| | そのとき橋の影の先端は
| | 大階段を静かに横切り
| | ちょうど王のつむじのあたりを
| | 東へあとじさる気配だ
| | 翳っていた流れがきらめきだし
| | 王の頭に太陽が直射して
| | あぶらじみた頭蓋を
| | 冠のように輝かせる
| | 王はまぶしげに身じろぎして
| | 目の上に腕をのせる
| | その賑やかな大広間の最上段
| | 橋げたのもっとも奥まったところに
| |
| | 王子の寝台がある
| | まんが雑誌を何冊も積み重ね
| | 砦のように厳重に周りを囲んで
| | 王子が
| | 石段に腰掛けておられる
| | よじれて固まった髪を肩まで垂らして
| | そろえた膝に分厚い本を一冊ずつ載せ
| | 折れないようにそっと表紙を開く
| | おおぜいの兄弟たちとの絶え間ない戦争
| | よく似た姉妹たちと繰り返される恋
| | 尻をしびれさせながら読みふける
| | 王妃と王の午睡のあいだも
| | 彼はけっして目を上げない
| | 刻々に移ろう橋の影もここからは去らない
| | 午後に傾きさらに深まる |
紙版"rain tree"no.24(2002.8.15)掲載
|
 <詩>わたしの3人の妹は(関富士子)へ
<詩>わたしの3人の妹は(関富士子)へ
わたしの3人の妹は
| | |
| | わたしの3人の妹は
| | 笑い上戸で能天気で強情であばずれで
| | 意地が悪くて夢想家できまぐれで
| | 今ごろどこでどうしていようと
| | わたしの知ったことじゃない
| |
| | わたしの3人の妹のために
| | 破滅した男は数知れない
| | 強靭な二の腕とまっすぐな向こう脛
| | 冷酷な瞳と非情な唇
| |
| | わたしの3人の妹が
| | 世界じゅうをほっつき歩いて
| | 5大陸で5人の娘を生み
| | 3万5千の島で3万5千人の息子を生んでも
| | わたしの知ったことじゃない
| |
| | 伸びほうだいの髪で地球を翳らせ
| | 扁平なあしうらをひらひら
| | はりぼての都市を踏んづけて
| | 歴史が古代に戻っても
| |
| | 21世紀の魔女と称えられ
| | 人類の疫病神と罵られ
| | 千年生きて老いさらばえても
| |
| | わたしの知ったことじゃない
| |
| | 妹たちがちっちゃなころ
| | こわがりでのろまで泣き虫で
| | じれったくてずいぶんいじめた
| | わたしたちはいつも歌っていた
| | 今でも歌っているのなら
| |
| | どんなにひどい世の中でも
| | 生きることは歌うこと
| | わたしの3人の妹を
| | 太陽は照らし雨は濡らすさ
| |
| | わたしの3人の妹が
| | 今ごろどこでどうしていようと
| | わたしの知ったことじゃない
|
「蘭の会」の女たちのために
 Web女流詩人の集い「蘭の会」2002.8.15掲載より転載 Web女流詩人の集い「蘭の会」2002.8.15掲載より転載
|
 <詩>「植物地誌」レンゲソウ(関富士子)へ
<詩>「植物地誌」レンゲソウ(関富士子)へ
 <詩>橋の下の家族(関富士子)
<詩>橋の下の家族(関富士子)
「植物地誌」連作
レンゲソウ
| | | 田んぼの畔のでこぼこを、一列に並んで歩
| | いていく。乾いた盛り土が崩れるまぎわ、ひ
| | ょいひょいと跳ぶ。田んぼの四つの隅のうち
| | いちばん遠い角まで来て立ち止まる。
| |
| | いちめんに生い茂って波のように揺れてい
| | る。先頭の者が、そろそろと波の中に足を踏
| | み入れる。茎が柔らかくしなって、膝まで沈
| | む。一列に並んで沈む。腰まで沈む者もいる。
| | ひんやりと向うずねを擦るのを、かまわず進
| | む。向かいの角をめがけていくと、ほぼ真ん
| | 中に着く。
| |
| | 四人は互いの背中を合わせて、それぞれが
| | 四つの方角を向く。つなごうとする手をふり
| | ほどいて、両足を思いきり広げ、腕を左右に
| | 伸ばす。いちにの、さん。四人は体を前のめ
| | りに傾け、いっせいに身を投げる。
| |
| | 目の横に見えていた畔の水平線がゆっくり
| | 傾いて、地面に体がちかかると、もう恐ろし
| | さに目を閉じてしまう。いつまでも落下し続
| | けるかのような数秒後、震える体ぜんたいを、
| | 柔らかく湿った厚いものが受け留める。
| |
| | 深みの底では波の音も聞こえない。蒸れた
| | 草のにおいのなかで、静まりかえって、ああ、
| | 死んだ、と思う。うつぶせの頬にくすぐった
| | く触れる葉。耐えきれずに目を開けると、細
| | い柔らかい茎が鼻先に密生して直立し、丸い
| | 三つ葉にからだが覆われている。
| |
| | これはほんとうの身投げではない。練習だ。
| | いつか身を投げるときのためのレッスン。で
| | ももしほんとうに死んでしまったら…。
| |
| | ピンクのぼんぼりがいくつも揺れて、その
| | 先にわずかに青空が見える。死後の世界。息
| | を殺して死体になる。羽状複葉で小葉は9〜
| | 11枚。中国産の越年草。茎は紫褐色がかり、
| | 放射状に生えて地に伏し、先の方が立つ。頭
| | 状に散出した直径3cmの花序。アリが首筋
| | を通っていく。草グモが顔にはい上がるが、
| | 体温を感じて去っていく。ミツバチがやって
| | きて、ぼんぼりに次々と明かりをともしてい
| | く。
| |
| | そのとき、青空をさえぎって、だれかのぞ
| | きこむ者がいる。くすくす笑っている。大急
| | ぎで起き上がると、辺りは明るく広々として、
| | 鳥の声や車の音が聞こえる。笑いたくなる。
| | 笑いながら自分がはまっていた穴を見下ろす。
| | たくさんの草が人の形に倒れている。足先
| | を中心にして、放射状に四つの方角に倒れた
| | 四つの人の形。死体は今片付けられたばかり
| | だ。
| |
| | 四人はまた一列に並ぶ。来たときと反対側
| | の角に向かっていく。草を漕いで畔に上がる。
| | 今日のレッスンはおしまい。明日の朝、レン
| | ゲソウはすべて起きあがっていて、死体の形
| | はあとかたもない。四人は何度でも、身投げ
| | の練習を繰り返すのだ。
|
*語彙、文体の一部は、日本百科大辞典別冊原色植物図鑑から引用がある。
|
 <詩>原始の呼吸(宗清友宏)へ
<詩>原始の呼吸(宗清友宏)へ
 <詩>わたしの3人の妹は(関富士子)
<詩>わたしの3人の妹は(関富士子)
 Web女流詩人の集い「蘭の会」2002.8.15掲載より転載
Web女流詩人の集い「蘭の会」2002.8.15掲載より転載