
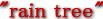 vol.22
vol.22 フユイチゴ
フユイチゴ ユズ
ユズ ダイズ
ダイズ
植物地誌 続
フユイチゴ
|
|
|
|
| 沢沿いの道の途中が昨夜の雨で崩れていて、
|
| 小さな流れになっているのを飛び越えると、
|
| すぐに急な登り坂になる。沢の水があふれる
|
| と道も川になるから、表土は流されて岩肌が
|
| 現れ、岩を覆うように松や杉の太い木の根が
|
| 巡っている。下草はすっかり枯れていてフユ
|
| イチゴの緑の葉は見当たらない。
|
|
|
| 暖地の樹下
|
| に生える。常緑のバラ科。夏から秋に葉腋ま
|
| たは茎頂に開花し、5〜10個の花が集まって
|
| つく。根元から地をはう長い茎を出して末端
|
| に苗をつくる。名は実が冬熟すのでいう。森
|
| の冬枯れの地面に濃い緑の葉を茂らせる。茎
|
| には短毛を密生し、ときにまばらに短刺が出
|
| る。
|
|
|
| 円い4〜10cmの葉の下に、小さな粒々の
|
| 集まった、10mmどの集合果が隠れているは
|
| ずだ。真っ赤に熟し、つまむと指のあいだで
|
| 崩れるのを急いで口に入れるのだ。甘味があ
|
| る。根に足をとられないように、はいつくば
|
| って登っていくと、不意に背後からにぎやか
|
| な声が聞こえてくる。
|
|
|
| 山道を登っているの
|
| に、息も切らさずさざめいている。ぺちゃく
|
| ちゃと人のおしゃべりのようだが、意味は聞
|
| き取れない。鳥の声のようでもある。立ち止
|
| まってようやく下を見ると、三人連れの娘た
|
| ちがすぐ後ろに迫っている。人ひとり立つの
|
| がやっとの道をどうやって譲ろうかと思案す
|
| る間もなく、娘たちはたちまち追いつき、い
|
| かにも身軽に、背後をふわりと通り過ぎてい
|
| く。
|
|
|
| 二人めが通るあいだもすぐそばでおしゃ
|
| べりは続いているが、何を話しているのか言
|
| 葉がわからない。木々がさざめくような気配
|
| がするばかりだ。木の根にすがって娘たちの
|
| 軽そうな赤い布靴を見ている。三人めが通り
|
| 過ぎてからようやく仰向いて、「どこへ?」
|
| と声をかけると、
|
|
|
| 「フユイチゴを採りに」
|
| と一人が答える。その声に響くように、二人
|
| めが、
|
| 「フユイチゴを採りに」
|
| 「フユイチゴを採りに」
|
| と三人めが振り向きもせず答えると、きつい
|
| 勾配を、ふわり、ふわりと浮きあがるように
|
| 登っていって、姿は見えなくなる。
|
gui no.65より(2002.4掲載) <詩>「植物地誌」ユズ(関富士子)
<詩>「植物地誌」ユズ(関富士子)
 <詩>音の梯子(関富士子)
<詩>音の梯子(関富士子)
ユ ズ
|
|
|
|
| 革を粗く縫った灰色の手袋を渡される。は
|
| めるとごわついてぶかぶかである。「こうで
|
| すよ」と言いながら、2メートルほどの棒を
|
| 掲げ、先端のオレンジ色の鳥の嘴のような部
|
| 分を、パチパチと動かして見せている。金属
|
| の鋏が付いているのだ。棒の下の先には同じ
|
| 色の取っ手が付いていて、握ったり緩めたり
|
| すると、鳥の嘴が上下に動く仕組みだ。だれ
|
| かが感心すると男は嬉しそうに幾度もやって
|
| 見せる。
|
|
|
| 男の大きな丸い顔が午後の光に照ら
|
| されている。つやのいい顔いちめんに古い吹
|
| き出物の痕があって、笑うと顔じゅうがでこ
|
| ぼこにふくれあがる。そばにいる妻の顔は、
|
| 作業用の帽子に隠れて見えない。ユズの皮を
|
| 煮詰めたマーマレードやゼリー、ジャム、大
|
| 根に刻みこんだ漬物などを人に薦めながら、
|
| 「十個だけね」と念を押す。
|
|
|
| 高枝鋏を受け取
|
| り、ロープを巡らせた通路に沿って家の裏に
|
| 回ると、南向きの斜面はユズの林で、明るい
|
| 黄色の実が輝いている。葉は長さ3〜7cmで、
|
| 葉柄に広翼がある。腺点が散在して香気があ
|
| る。常緑で実は熟しても裂果しない。叢にい
|
| くつも転がっている。採ったもののまだ小さ
|
| いので捨てていったらしい。木は高さ3メー
|
| トル。日当たりの良い実は大きく、内側のも
|
| のは小ぶりである。
|
|
|
| 目指す実を決めて、高枝
|
| 鋏を操り枝の中に挿し入れると、太い緑の棘
|
| が革手袋を刺す。長さ3cm。かまわずぐいと
|
| 刃を押しこみ、取っ手を握るとどしんと落ち
|
| て斜面をごろごろと転がっていく。落ちた実
|
| は思ったより小さい。拾わずにさらに大きそ
|
| うな実を探す。地面に当たってまた転がる。
|
| どうもなんだか小さくて物足りない。仰向い
|
| たまま次々に落としていくうち、何個だった
|
| か分からなくなる。
|
gui no.65 2002.Spring 掲載 <詩>「植物地誌」ダイズ(関富士子)
<詩>「植物地誌」ダイズ(関富士子)
 <詩>フユイチゴ
<詩>フユイチゴ
ダイズ
|
|
|
|
| 畑に通じる土間の上がりかまちに、無造作
|
| に置かれた3本の枝。剥き出しの根が付いた
|
| まま緩く束ねてある。長さ50cm。引き抜い
|
| てすぐ水場で洗ったらしく、土をつかんでい
|
| た短いひげ根が、固くねじくれて乾き始めて
|
| いる。
|
|
|
| 朝寝坊をして屋敷の中は静かだ。北向
|
| きの窓の明かりが、台所の隅々まで柔らかく
|
| 広がっている。パジャマのままたたきに降り
|
| て、枝の束を持ち上げるとずっしり重い。先
|
| 端に丸い葉が茂ってやや蔓状に揺れる。小葉
|
| は3枚。下のほうの葉は手でむしったらしい。
|
| 実は莢状。葉柄の付け根ごとに5cmほどの莢
|
| が3〜5個ずつ下がり、ほどよく膨らんでい
|
| る。
|
|
|
| パジャマの袖をまくって束をほぐしてか
|
| ら、根っこを逆さに持つ。バケツに漬けてざ
|
| ぶざぶと濯ぐ。全体に褐色の長毛が密生する
|
| が、洗うと取れて水の表面に浮かんでくる。
|
| 手の甲に触れるとちくちくする。腕までむず
|
| がゆいのを我慢して、冷たい水で洗い流す。
|
|
|
| テーブルに新聞紙を広げ、莢をつまんで鋏
|
| でパチンパチンと切り落とす。全部摘んで笊
|
| に山盛りになったら、粗塩を揉み込むように
|
| まぶしておく。莢に豆は2個か3個入ってい
|
| る。稀に4個。
|
|
|
| 時間を見計らってたっぷりの
|
| 塩水で茹で上げたころ、裏口の扉を開けて入
|
| ってくる者がいる。腕いっぱいに新しい枝束
|
| を抱えている。受け取ろうと両手を差し出す
|
| と、パジャマから出た腕が植物の毛に刺され
|
| て赤らんでいる。
|
|
|
| 戸口に立つ者は、抱えてい
|
| た枝をばらばら床に落とす。両腕を広げてそ
|
| のままきつく腰を抱いてくる。蒸れた泥の甘
|
| い匂いをかぶる。毛にまみれた手で胸や腿を
|
| こするので、からだじゅうがちくちくと痛が
|
| ゆい。
|
|
|
| 床に散らばった枝のうち、充分実った
|
| ものは茹でずに、枝ごと日陰で乾燥させてか
|
| ら叩いて莢を剥く。莢を摘んだ枝や莢殻は、
|
| 屋敷の裏の乾いた軒下に集めておく。根こそ
|
| ぎ抜き取り、夏じゅう、豆を食べたり干した
|
| りするごとに新しい枝が積み上げられる。冬
|
| には枝も根も莢もすっかり乾いて軽い。火に
|
| くべると勢いよく燃えて、開けそこねた莢が
|
| 竈のなかでぱちぱち爆ぜている。
|
gui 64 2001.11
*語彙、文体の一部は、日本百科大辞典別冊原色植物図鑑から引用がある。
 <詩>田村奈津子詩集『人体望遠鏡』へ
<詩>田村奈津子詩集『人体望遠鏡』へ
 <詩>「植物地誌」ユズ(関富士子)
<詩>「植物地誌」ユズ(関富士子)
 <詩>音の梯子(関富士子)
<詩>音の梯子(関富士子)