HOME>独想録>
2005年1月の独想録
1月16日 生きる支えになるもの
本を書く者として、私がとても気をつけていることは、
「本はすばらしいけれど、本人はすばらしくない」
と非難されないようにすることだ。
このような批判は、現実にはよくあることである。
愛を説き、低級な欲望に浸るのではなく高潔な生活を説き、寛容さを説き、誠実さを説いたすばらしい本なので、こんなにすばらしい本を書くのだから、その著者もすばらしい人に違いないと思う。それで会いに行くと、意外にも冷たかったり、傲慢だったり、口が悪かったり、無愛想だったりしてがっかりしてしまう。こういった話をときおり耳にするし、私自身にも経験がある。
そういう経験をすると、本当にがっかりするもので、その著者と会って以後、あれほど感動したその本の内容が、妙に空しいものに感じ、ときには腹立たしいものにさえ覚えてきたりする。あげくには、人間という存在そのものに対する不信感さえ芽生えてくる。すべての人間が「偽善者」ではないかとさえ、思えてしまうこともある。
人を、このような気持ちにさせるということは、あきらかな罪であるに違いない。それゆえに、私は本に書いてある内容と自分自身とを一致させなければならないと気をつけている。そして、自分にできないような偉そうなことは書かないようにするか、あるいは、「自戒を込めて(自分に言い聞かせるつもりで)」という表現を添えるようにしている。
しかしながら、本と著者との間のギャップという問題には、単純ではない要素が絡んでいたりもする。ときには、著者に対する過剰な幻想や誤解といったこともある。
たとえば、これはもうむかしのことだが、「自分の書いた原稿を本にしたいので協力して欲しい」という人物がやってきたことがあった。その原稿の内容とその人自身を見て問題があるように思えたので協力を断ると、「あなたは本の中で愛を説いているくせに、ぜんぜん実践していないじゃないか」といって責められたことがある。
これは、自分の望むことを無条件に十分に満足させてくれることが「愛」であると思い込んでおり、相手がそれを満たしてくれないという理由で、責めているのであろう。
また、私が主催するセミナーにおいて、私が来場者にお茶を入れてさし上げたことがあり、それを見た参加者のひとりが「あなたは、お茶汲みのようなマネをする人間なのか」といって怒り、去っていってしまったこともあった。私はいまだにその理由がよくわからないのだが、おそらく、「お茶汲み」というのは卑しい人間のすることだと、その人は思っていたのだろう。その人にとっては、私が壇上で偉そうに構えていればそれで満足したのかもしれないが、あのイエスでさえ弟子の足を洗ったのだから、この私が壇上で偉そうにしていなければならない理由はない。お茶汲みを卑しいことだと思っていない私からすれば、こうした批判は、その人の偏見によるものとしか考えられない。
かと思うと、病気で苦しんでいる人をサポートする小さな集まりを呼びかけたところ、「そのような慈善的な活動をするのは、あなたのエゴがそうさせるのだ」と、辛辣な言葉に満ちた批判の手紙をもらったこともある。
こうしたことをたびたび経験してわかったことは、
「結局、何をやっても批判されるのだ」
ということであった。頼み事を断れば批判され、お茶汲みをすれば批判され、人助けをすれば批判される。何をやっても批判されるのだとわかれば、批判などは逆に気にならなくなってくる。悪意なきアドバイスには謙虚に耳を傾けなければならないが、基本的には自分が信じることをするまでのことだと、今では開き直っている。
結局、批判というのは、自分の考えとマッチしているか否かということで為されるのであろう。それが本当に正しいか否か、善いか否かというよりも、自分の考え(むしろ感情といった方が近いかもしれないが)に反することが間違いであり悪であるという自分本位の基準によって為されるように思われる。このようなことにいちいち関わっていたら、人生は何もできなくなってしまう。
こんな話がある。
むかし、徳の高い僧がいた。あるとき、僧の住む寺に、一頭の子鹿が迷い込んできた。それを見た僧は、もっていた棒でその鹿を激しく叩いた。鹿は悲鳴をあげて山に逃げていった。
それを見た村人は、「ふだんは慈悲だの何だのと偉そうな説教をしているくせに、生き物に対してあんなひどいことをする」といって、たちまち悪口が村に広がっていった。
だが、僧の真意は村人が思うようなものではなかった。
もし鹿が人間に警戒心をもたずに近づいていったら、銃で撃ち殺されてしまうかもしれない。そこで僧は、人間は怖いものだ、人間に近づいてはいけない、ということを鹿に教えるために叩いたのである。つまり、鹿を救うという慈悲の心から発せられた行為だったのだ。そんな高僧の気持ちを村人が知るよしもなく、僧は批判されたのである。
世の中には、作家や芸術家というものは、すばらしい作品を書くことが使命なのであり、その人間性までを問われる筋合いはない、という考え方もある。たとえば、第九交響曲で人類愛を高々と謳ったベートーベンその人は、人間嫌いな傾向があり、不機嫌で気難しい面がかなりあったという。確かに、仮に人間性と作品を近づけようとするあまり、作品の質が落ちてしまうのだとすれば、歴史的な視点から判断した場合には、人間性よりも作品の質を向上させるべきであろう。
けれども、音楽や小説といったものは、あくまでも「作品」なので、たとえ人間性がどんなにその作品のすばらしさに似つかわしくないものであっても許されるかもしれないし、あるいはまた、医者自身がどんなに不健康でも、患者を癒すことができるならば、医者自身の不健康性は、責められる筋合いではないのだろうが、自分の主張をそのまま書いたもの(思想や哲学、エッセイ、説教といったもの)は、音楽や小説といった「作品」とは違い、その人そのものなのだ。
たとえば、宗教家が書いた本は、決して「作品」ではない。その本は宗教家そのものである。言い方を変えれば、宗教家にとって「作品」とは、自分自身そのものなのだ。いかにすばらしい本が書けたとしても、自分自身がくだらない人間ならば、彼は作家ではあるかもしれないが、宗教家とは決していえない。「存在」によって人々を教化するのが真の宗教家なのであり、説教や本によってではない。
私自身は、もちろん宗教家ではなく、自分としては作家や詩人、芸術家でありたいと思っている。正直なところ、「作品はすばらしいが人間性は貧しい」ということに対する免罪符が欲しいからだ。
けれども、作品はすばらしいのに人間性が貧しいということは、その作家が、ある種のファンタジーの世界に生きているということの、疑いもない証拠であることも確かである。
愛は抽象的な概念ではなくして、現実世界におけるダイナミックな現象であるにもかかわらず。
愛は説くが愛を実践しないなら、それは「ハリーポッター」のようなファンタジー小説家と同じレベルなのだ。いや、魔法の物語なら誰もが現実には存在しないことがわかっていて楽しんでいるから問題はないが、愛をファンタジーにしてしまったら、本来は現実的に存在しなければならない愛を架空の存在として埋没させてしまっている点において、大きな罪を犯しているといえるだろう。
人生を生きる上で大きな支えとなり、光となるものとは、この暗い世界にも「愛」というものが確かに存在するのだという発見であり確信であって、その重大な発見をするひとつの機会というものが、「この世には、こんなにもすばらしい人(愛に生きる人)が存在していたのか!」と思えるような人との出会いに他ならない。
本を通してこうした愛を発見することもあるかもしれないが、現実に生きている人の中に愛を発見することの方が、数倍も、数百倍も、数千倍も、その光は強い。
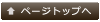
1月23日 真のバランス感覚
私はいつも何かを考えるとき、「バランス」ということを基本にするようにしている。 極端な考えや、片寄ったものは、どこか真実とかけ離れているように思われるのだ。
バランス感覚が大切だ。物質的な世界に浸り、精神的な事柄に無関心な人は好ましいとは思えないが、観念的で精神世界ばかりに没頭している人も好ましいとは思わない。自分のことばかり考えることは好ましくなく、人のことばかり考えているのも好ましいとは思えない。
要するに、何事も中庸というのが大切だと思うのだが、だからといって、「何事もほどほどにする」といったような、いわゆる「事なかれ主義」というのでもない。
真のバランス感覚とは、ある面では非常に極端な傾向をもちながらも、それと反対の極端な傾向をも持ち合わせていることでバランスを取っている状態のことだ。
たとえば、両腕の短いやじろべえは、一応バランスは取っているが、ちょっと揺らすと、すぐに揺れて不安定になる。しかし、長い腕をもったやじろべえは、少しくらい揺らしても、悠々としていて多少のことでは不安定にならない。
人間というものも、同じではないかと思う。若いときから、何事も極端なことをせず、ほどほどにやってきた人、換言すれば、人生の浮き沈みをあまり経験していないとか、狭い世界や経験の中でしか生きてこなかった人は、一見すると安定しているように見えるが、ちょっと何かあるとすぐに動揺して、安定を欠いてしまう。
しかし、人生の浮き沈み、極端なことの両方を経験し、味わい、広い世界を知り、多彩な経験をした人というのは、少しくらいのことでは動揺しない。
それが、私のいう「バランス感覚」だ。
もしも、短い腕をしたやじろべえで、しかも、若かったなら(ちなみに、ここでいう“若さ”とは必ずしも肉体的な若さのことではない。むしろ精神的な、いわばバイタリティがあるかどうかだ)、私は逆に、バランスを崩すような、極端なことをするように勧めるだろう。
その結果、一時的にバランスを崩して苦労することになるだろうが、バイタリティが強ければ、やがてその対極の力が目覚めて、バランスが回復される方向に進んでいく。つまりは、やじろべえの腕が長くなるのだ。そうした経験を積み重ねるにつれて、以前よりも物事に動揺しない、肚の座った、懐の深い人間になる。少しくらいのことで怒ったり気持ちを乱したりすることがなく、人の弱さや欠点を受け入れ、敵対する人さえも許して包容できるような、そんな人間になっていく。これこそが抜群のバランス感覚の人間だ。
そして、そういうバランス感覚の人間は、ほぼ間違いなく「常識的」である。
すなわち、礼儀正しく、挨拶はきちんとして、服装も整っており、社会のルールはよく守る。以前は極端な生き方をしてきたとしても、バランス感覚を得ると、見た目にはきわめて常識的になるということだ。奇抜な格好をしたり、地に足がついておらず、理屈ばかり口走ったり、非常識であったり、自らの意志で日常の生業をしないといったことは、バランス感覚を失っていると思う。
かといって、常識的ではあるといっても、常識で固められているわけでもない。
真のバランス感覚の持ち主は、必要ならいつでも即座に常識を捨てることのできる大胆さ、勇気、行動力といったものも兼ね備えている。
こうしたバランス感覚の持ち主は、誠実で信頼に値する人間であるが、いい意味でその期待を裏切るような人でもある。いい意味で「予想がつかない人」でもある。
小さなやじろべえのように、根本的な力量不足のためフラフラして「予想がつかない」というのではなく、かといって、パターン的な生き方しかしていない(できない)がゆえに、予想がつきすぎて、その人のすべてがわかってしまい、何ら意外な面は期待できないという人間でもない。
真のバランス感覚の持ち主は、ふだんは北極星のごとく確実で信頼に値するが、いざとなると臨機応変にして機転に富んだ大胆な行動に出るなど、どこか「予想がつかない」面をもっている。どこか神秘的な面をもっている。
2005年1月の独想録
1月16日 生きる支えになるもの
本を書く者として、私がとても気をつけていることは、
「本はすばらしいけれど、本人はすばらしくない」
と非難されないようにすることだ。
このような批判は、現実にはよくあることである。
愛を説き、低級な欲望に浸るのではなく高潔な生活を説き、寛容さを説き、誠実さを説いたすばらしい本なので、こんなにすばらしい本を書くのだから、その著者もすばらしい人に違いないと思う。それで会いに行くと、意外にも冷たかったり、傲慢だったり、口が悪かったり、無愛想だったりしてがっかりしてしまう。こういった話をときおり耳にするし、私自身にも経験がある。
そういう経験をすると、本当にがっかりするもので、その著者と会って以後、あれほど感動したその本の内容が、妙に空しいものに感じ、ときには腹立たしいものにさえ覚えてきたりする。あげくには、人間という存在そのものに対する不信感さえ芽生えてくる。すべての人間が「偽善者」ではないかとさえ、思えてしまうこともある。
人を、このような気持ちにさせるということは、あきらかな罪であるに違いない。それゆえに、私は本に書いてある内容と自分自身とを一致させなければならないと気をつけている。そして、自分にできないような偉そうなことは書かないようにするか、あるいは、「自戒を込めて(自分に言い聞かせるつもりで)」という表現を添えるようにしている。
しかしながら、本と著者との間のギャップという問題には、単純ではない要素が絡んでいたりもする。ときには、著者に対する過剰な幻想や誤解といったこともある。
たとえば、これはもうむかしのことだが、「自分の書いた原稿を本にしたいので協力して欲しい」という人物がやってきたことがあった。その原稿の内容とその人自身を見て問題があるように思えたので協力を断ると、「あなたは本の中で愛を説いているくせに、ぜんぜん実践していないじゃないか」といって責められたことがある。
これは、自分の望むことを無条件に十分に満足させてくれることが「愛」であると思い込んでおり、相手がそれを満たしてくれないという理由で、責めているのであろう。
また、私が主催するセミナーにおいて、私が来場者にお茶を入れてさし上げたことがあり、それを見た参加者のひとりが「あなたは、お茶汲みのようなマネをする人間なのか」といって怒り、去っていってしまったこともあった。私はいまだにその理由がよくわからないのだが、おそらく、「お茶汲み」というのは卑しい人間のすることだと、その人は思っていたのだろう。その人にとっては、私が壇上で偉そうに構えていればそれで満足したのかもしれないが、あのイエスでさえ弟子の足を洗ったのだから、この私が壇上で偉そうにしていなければならない理由はない。お茶汲みを卑しいことだと思っていない私からすれば、こうした批判は、その人の偏見によるものとしか考えられない。
かと思うと、病気で苦しんでいる人をサポートする小さな集まりを呼びかけたところ、「そのような慈善的な活動をするのは、あなたのエゴがそうさせるのだ」と、辛辣な言葉に満ちた批判の手紙をもらったこともある。
こうしたことをたびたび経験してわかったことは、
「結局、何をやっても批判されるのだ」
ということであった。頼み事を断れば批判され、お茶汲みをすれば批判され、人助けをすれば批判される。何をやっても批判されるのだとわかれば、批判などは逆に気にならなくなってくる。悪意なきアドバイスには謙虚に耳を傾けなければならないが、基本的には自分が信じることをするまでのことだと、今では開き直っている。
結局、批判というのは、自分の考えとマッチしているか否かということで為されるのであろう。それが本当に正しいか否か、善いか否かというよりも、自分の考え(むしろ感情といった方が近いかもしれないが)に反することが間違いであり悪であるという自分本位の基準によって為されるように思われる。このようなことにいちいち関わっていたら、人生は何もできなくなってしまう。
こんな話がある。
むかし、徳の高い僧がいた。あるとき、僧の住む寺に、一頭の子鹿が迷い込んできた。それを見た僧は、もっていた棒でその鹿を激しく叩いた。鹿は悲鳴をあげて山に逃げていった。
それを見た村人は、「ふだんは慈悲だの何だのと偉そうな説教をしているくせに、生き物に対してあんなひどいことをする」といって、たちまち悪口が村に広がっていった。
だが、僧の真意は村人が思うようなものではなかった。
もし鹿が人間に警戒心をもたずに近づいていったら、銃で撃ち殺されてしまうかもしれない。そこで僧は、人間は怖いものだ、人間に近づいてはいけない、ということを鹿に教えるために叩いたのである。つまり、鹿を救うという慈悲の心から発せられた行為だったのだ。そんな高僧の気持ちを村人が知るよしもなく、僧は批判されたのである。
世の中には、作家や芸術家というものは、すばらしい作品を書くことが使命なのであり、その人間性までを問われる筋合いはない、という考え方もある。たとえば、第九交響曲で人類愛を高々と謳ったベートーベンその人は、人間嫌いな傾向があり、不機嫌で気難しい面がかなりあったという。確かに、仮に人間性と作品を近づけようとするあまり、作品の質が落ちてしまうのだとすれば、歴史的な視点から判断した場合には、人間性よりも作品の質を向上させるべきであろう。
けれども、音楽や小説といったものは、あくまでも「作品」なので、たとえ人間性がどんなにその作品のすばらしさに似つかわしくないものであっても許されるかもしれないし、あるいはまた、医者自身がどんなに不健康でも、患者を癒すことができるならば、医者自身の不健康性は、責められる筋合いではないのだろうが、自分の主張をそのまま書いたもの(思想や哲学、エッセイ、説教といったもの)は、音楽や小説といった「作品」とは違い、その人そのものなのだ。
たとえば、宗教家が書いた本は、決して「作品」ではない。その本は宗教家そのものである。言い方を変えれば、宗教家にとって「作品」とは、自分自身そのものなのだ。いかにすばらしい本が書けたとしても、自分自身がくだらない人間ならば、彼は作家ではあるかもしれないが、宗教家とは決していえない。「存在」によって人々を教化するのが真の宗教家なのであり、説教や本によってではない。
私自身は、もちろん宗教家ではなく、自分としては作家や詩人、芸術家でありたいと思っている。正直なところ、「作品はすばらしいが人間性は貧しい」ということに対する免罪符が欲しいからだ。
けれども、作品はすばらしいのに人間性が貧しいということは、その作家が、ある種のファンタジーの世界に生きているということの、疑いもない証拠であることも確かである。
愛は抽象的な概念ではなくして、現実世界におけるダイナミックな現象であるにもかかわらず。
愛は説くが愛を実践しないなら、それは「ハリーポッター」のようなファンタジー小説家と同じレベルなのだ。いや、魔法の物語なら誰もが現実には存在しないことがわかっていて楽しんでいるから問題はないが、愛をファンタジーにしてしまったら、本来は現実的に存在しなければならない愛を架空の存在として埋没させてしまっている点において、大きな罪を犯しているといえるだろう。
人生を生きる上で大きな支えとなり、光となるものとは、この暗い世界にも「愛」というものが確かに存在するのだという発見であり確信であって、その重大な発見をするひとつの機会というものが、「この世には、こんなにもすばらしい人(愛に生きる人)が存在していたのか!」と思えるような人との出会いに他ならない。
本を通してこうした愛を発見することもあるかもしれないが、現実に生きている人の中に愛を発見することの方が、数倍も、数百倍も、数千倍も、その光は強い。
1月23日 真のバランス感覚
私はいつも何かを考えるとき、「バランス」ということを基本にするようにしている。 極端な考えや、片寄ったものは、どこか真実とかけ離れているように思われるのだ。
バランス感覚が大切だ。物質的な世界に浸り、精神的な事柄に無関心な人は好ましいとは思えないが、観念的で精神世界ばかりに没頭している人も好ましいとは思わない。自分のことばかり考えることは好ましくなく、人のことばかり考えているのも好ましいとは思えない。
要するに、何事も中庸というのが大切だと思うのだが、だからといって、「何事もほどほどにする」といったような、いわゆる「事なかれ主義」というのでもない。
真のバランス感覚とは、ある面では非常に極端な傾向をもちながらも、それと反対の極端な傾向をも持ち合わせていることでバランスを取っている状態のことだ。
たとえば、両腕の短いやじろべえは、一応バランスは取っているが、ちょっと揺らすと、すぐに揺れて不安定になる。しかし、長い腕をもったやじろべえは、少しくらい揺らしても、悠々としていて多少のことでは不安定にならない。
人間というものも、同じではないかと思う。若いときから、何事も極端なことをせず、ほどほどにやってきた人、換言すれば、人生の浮き沈みをあまり経験していないとか、狭い世界や経験の中でしか生きてこなかった人は、一見すると安定しているように見えるが、ちょっと何かあるとすぐに動揺して、安定を欠いてしまう。
しかし、人生の浮き沈み、極端なことの両方を経験し、味わい、広い世界を知り、多彩な経験をした人というのは、少しくらいのことでは動揺しない。
それが、私のいう「バランス感覚」だ。
もしも、短い腕をしたやじろべえで、しかも、若かったなら(ちなみに、ここでいう“若さ”とは必ずしも肉体的な若さのことではない。むしろ精神的な、いわばバイタリティがあるかどうかだ)、私は逆に、バランスを崩すような、極端なことをするように勧めるだろう。
その結果、一時的にバランスを崩して苦労することになるだろうが、バイタリティが強ければ、やがてその対極の力が目覚めて、バランスが回復される方向に進んでいく。つまりは、やじろべえの腕が長くなるのだ。そうした経験を積み重ねるにつれて、以前よりも物事に動揺しない、肚の座った、懐の深い人間になる。少しくらいのことで怒ったり気持ちを乱したりすることがなく、人の弱さや欠点を受け入れ、敵対する人さえも許して包容できるような、そんな人間になっていく。これこそが抜群のバランス感覚の人間だ。
そして、そういうバランス感覚の人間は、ほぼ間違いなく「常識的」である。
すなわち、礼儀正しく、挨拶はきちんとして、服装も整っており、社会のルールはよく守る。以前は極端な生き方をしてきたとしても、バランス感覚を得ると、見た目にはきわめて常識的になるということだ。奇抜な格好をしたり、地に足がついておらず、理屈ばかり口走ったり、非常識であったり、自らの意志で日常の生業をしないといったことは、バランス感覚を失っていると思う。
かといって、常識的ではあるといっても、常識で固められているわけでもない。
真のバランス感覚の持ち主は、必要ならいつでも即座に常識を捨てることのできる大胆さ、勇気、行動力といったものも兼ね備えている。
こうしたバランス感覚の持ち主は、誠実で信頼に値する人間であるが、いい意味でその期待を裏切るような人でもある。いい意味で「予想がつかない人」でもある。
小さなやじろべえのように、根本的な力量不足のためフラフラして「予想がつかない」というのではなく、かといって、パターン的な生き方しかしていない(できない)がゆえに、予想がつきすぎて、その人のすべてがわかってしまい、何ら意外な面は期待できないという人間でもない。
真のバランス感覚の持ち主は、ふだんは北極星のごとく確実で信頼に値するが、いざとなると臨機応変にして機転に富んだ大胆な行動に出るなど、どこか「予想がつかない」面をもっている。どこか神秘的な面をもっている。