HOME>独想録>
2005年10月の独想録
10月10日 何回まで失敗は許されるのか?
たとえば、たまたまレストランに行って、そこの食事がまずかったら、おそらく二度とそのレストランには行かないだろう。出す食事がまずかったら、いくら宣伝をして人を集めても、一度は来てくれるだろうが、もう二度とは来てくれないから、ついにはお客さんは来てくれなくなり、その店はつぶれてしまうだろう。
あるいは、本を書いたとしよう。ある人の書いた本がつまらなかったら、もう二度とその著者の本は買ってもらえないだろう。それでも、これまで面白い本を書いてきて、人気の出ている作家ならば、一度くらいつまらない本を書いたとしても、そうすぐに読者が離れてしまうことはないかもしれない。しかし、もし次の本も面白くなかったら読者は目に見えて減るだろうし、さらに次の本も面白くなかったら、ついには読者からも出版社からも見向きもされなくなるだろう。
人間的な信用といったものも同じであろう。特に初対面で相手によい印象をアピールできなければ、その後、信頼や人気を勝ち得ることは非常に難しくなる。一度信頼と人気を勝ち得れば、その後、少しくらいへまをしたとしても、そうすぐに信頼や人気が下がることはないだろう。けれども、それが二度、三度と続くと、もう取り返しのつかないことになる。「仏の顔も三度」という言葉もある。人間が許される失敗は、3回が限界なのかもしれない。
3回もつまらない本を書いてしまった作家、3回もつまらない話をしてしまった講演者、3回も期待を裏切った人たちが、再び信頼や人気を勝ち得るためには、膨大な努力と時間を要するだろう。もしかしたら、もう二度と再びもとのような信頼や人気を勝ち得ることはできないかもしれない。だから、人間というのは、毎日が、一回一回が、真剣勝負なのではないかと思う。
もちろん、人間である以上、常に人々の期待に応えることは難しい。どうしても出来不出来というものがあるのは仕方がない。
けれども、少なくても情熱的に努力している限り、たとえうまくいかない場合でも、致命的なひどい結果に終わるということは、それほどないと思う。人々の信頼を裏切るほどのひどい結果になってしまうとしたら、それは油断や怠慢、自惚れによってもたらされるのではないだろうか。
自惚れれば、真剣に努力しなくなるし、準備もサボるようになる。「自分は準備なんかしなくたってうまくできるんだ」という驕り、怠慢の温床になる。自惚れること、自信過剰、独善、つまりは謙虚さを失うということが、どんな道を歩むのであれ、たちまち致命的な結果を招く非常に危険な落とし穴になる。
誰がいったのか、とても心すべき言葉がある。
“人生にリハーサルはない”
リハーサルとは、失敗が許される状況ということだ。試行錯誤が許される状況だ。人生にはそんなリハーサルなどはないのだ。
私たちの生活は、私たちの人生は、毎日が真剣に臨まなければならない「本番」なのだ。
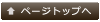
10月22日 神秘というもの
子供だった頃、世界のすべては「神秘」だった。
生命が死に絶えてしまったかのような冬の大地が、春ともなれば緑が芽生え、花が咲き、どこからともなく鳥や蝶がやってくるというのが、とてつもない神秘だった。
自転車が倒れないで走ることができるのも、遠く離れた人と会話できる電話も、小さな箱の中に人間が映るテレビも神秘だった。私は神秘を前にして、何か偉大なるものを前にした畏敬のようなものを感じた。
やがて青年になると、こういうことは神秘ではなくなった。季節の訪れが気象現象であることを知り、自転車が倒れない理由も、電話やテレビのしくみも、すべてが物理現象であると知るようになると、神秘ではなくなった。
青年になると、恋というものが神秘となった。
恋する女の子の甘美な微笑みが、まばゆいばかりの光を放っていることが神秘だった。私は恋の神秘の前で、やはりある種の畏敬のような感情を覚えた。私はいつまでも、恋の神秘に畏敬し続ける人間でありたいと願った。
けれども、歳を重ねるにつれ、まるで色あせた写真のように、恋もむかしの出来事を思い出すかのような感覚になってしまった。それに伴い、私のなかにあった貴重な何かも、色あせてしまった気がした。女の子と見つめ合ったときの、あの未来への無限の可能性のぞくぞくする予感と「生きている」という感覚は、どこに消えてしまったのだろう? 恋人を前にして感じるあの神秘への畏敬は?
青年を過ぎてからは、「神」が神秘となった。
しかし、私が最初に出会った「神」は、言葉や文字によって現出したものに過ぎなかった。言葉や文字を通して得られる畏敬の気持ちは、真に神を前にした人間が感じる畏敬とは違うだろう。恋がリアルな体験であるように、神もリアルな体験でなければならない。私は言葉や文字を超えた神を求めるようになった。それはある種の「恋」なのかもしれない。当時は携帯もメールもなかったが、私はメールという文字だけで満足するような人間ではなかった。間近で女の子を見つめ、抱きしめなければ気がすまなかった。
その思いが、そのまま神へとシフトされていった。この世界の最大にして最後の神秘である神に。私が求めるのは、神についての概念でもなければ、説明でもない。神そのものだ。神に直接触れることだ。
人間は、神秘を前にするからこそ、謙虚にもなるし、敬虔な気持ちにもなる。神秘から目を背ける者、神秘を見出し得ない者は、しだいに腐っていくだけだ。歳を取るということ、すなわち成長して円熟するということは、決して神秘なるものをもたなくなることではない。世の中のすべてにわかったような顔をすることではない。むしろ逆に、円熟するということは、ますますこの世界というものが神秘であること、世の中のことは何もわかっていないのだということを悟っていくことのなかにあるのではないだろうか。歳をとっても、いつまでも春の訪れに神秘を感じ、恋心をもち続け、神の存在に畏敬の念を持ち続けることのなかに……。
2005年10月の独想録
10月10日 何回まで失敗は許されるのか?
たとえば、たまたまレストランに行って、そこの食事がまずかったら、おそらく二度とそのレストランには行かないだろう。出す食事がまずかったら、いくら宣伝をして人を集めても、一度は来てくれるだろうが、もう二度とは来てくれないから、ついにはお客さんは来てくれなくなり、その店はつぶれてしまうだろう。
あるいは、本を書いたとしよう。ある人の書いた本がつまらなかったら、もう二度とその著者の本は買ってもらえないだろう。それでも、これまで面白い本を書いてきて、人気の出ている作家ならば、一度くらいつまらない本を書いたとしても、そうすぐに読者が離れてしまうことはないかもしれない。しかし、もし次の本も面白くなかったら読者は目に見えて減るだろうし、さらに次の本も面白くなかったら、ついには読者からも出版社からも見向きもされなくなるだろう。
人間的な信用といったものも同じであろう。特に初対面で相手によい印象をアピールできなければ、その後、信頼や人気を勝ち得ることは非常に難しくなる。一度信頼と人気を勝ち得れば、その後、少しくらいへまをしたとしても、そうすぐに信頼や人気が下がることはないだろう。けれども、それが二度、三度と続くと、もう取り返しのつかないことになる。「仏の顔も三度」という言葉もある。人間が許される失敗は、3回が限界なのかもしれない。
3回もつまらない本を書いてしまった作家、3回もつまらない話をしてしまった講演者、3回も期待を裏切った人たちが、再び信頼や人気を勝ち得るためには、膨大な努力と時間を要するだろう。もしかしたら、もう二度と再びもとのような信頼や人気を勝ち得ることはできないかもしれない。だから、人間というのは、毎日が、一回一回が、真剣勝負なのではないかと思う。
もちろん、人間である以上、常に人々の期待に応えることは難しい。どうしても出来不出来というものがあるのは仕方がない。
けれども、少なくても情熱的に努力している限り、たとえうまくいかない場合でも、致命的なひどい結果に終わるということは、それほどないと思う。人々の信頼を裏切るほどのひどい結果になってしまうとしたら、それは油断や怠慢、自惚れによってもたらされるのではないだろうか。
自惚れれば、真剣に努力しなくなるし、準備もサボるようになる。「自分は準備なんかしなくたってうまくできるんだ」という驕り、怠慢の温床になる。自惚れること、自信過剰、独善、つまりは謙虚さを失うということが、どんな道を歩むのであれ、たちまち致命的な結果を招く非常に危険な落とし穴になる。
誰がいったのか、とても心すべき言葉がある。
“人生にリハーサルはない”
リハーサルとは、失敗が許される状況ということだ。試行錯誤が許される状況だ。人生にはそんなリハーサルなどはないのだ。
私たちの生活は、私たちの人生は、毎日が真剣に臨まなければならない「本番」なのだ。
10月22日 神秘というもの
子供だった頃、世界のすべては「神秘」だった。
生命が死に絶えてしまったかのような冬の大地が、春ともなれば緑が芽生え、花が咲き、どこからともなく鳥や蝶がやってくるというのが、とてつもない神秘だった。
自転車が倒れないで走ることができるのも、遠く離れた人と会話できる電話も、小さな箱の中に人間が映るテレビも神秘だった。私は神秘を前にして、何か偉大なるものを前にした畏敬のようなものを感じた。
やがて青年になると、こういうことは神秘ではなくなった。季節の訪れが気象現象であることを知り、自転車が倒れない理由も、電話やテレビのしくみも、すべてが物理現象であると知るようになると、神秘ではなくなった。
青年になると、恋というものが神秘となった。
恋する女の子の甘美な微笑みが、まばゆいばかりの光を放っていることが神秘だった。私は恋の神秘の前で、やはりある種の畏敬のような感情を覚えた。私はいつまでも、恋の神秘に畏敬し続ける人間でありたいと願った。
けれども、歳を重ねるにつれ、まるで色あせた写真のように、恋もむかしの出来事を思い出すかのような感覚になってしまった。それに伴い、私のなかにあった貴重な何かも、色あせてしまった気がした。女の子と見つめ合ったときの、あの未来への無限の可能性のぞくぞくする予感と「生きている」という感覚は、どこに消えてしまったのだろう? 恋人を前にして感じるあの神秘への畏敬は?
青年を過ぎてからは、「神」が神秘となった。
しかし、私が最初に出会った「神」は、言葉や文字によって現出したものに過ぎなかった。言葉や文字を通して得られる畏敬の気持ちは、真に神を前にした人間が感じる畏敬とは違うだろう。恋がリアルな体験であるように、神もリアルな体験でなければならない。私は言葉や文字を超えた神を求めるようになった。それはある種の「恋」なのかもしれない。当時は携帯もメールもなかったが、私はメールという文字だけで満足するような人間ではなかった。間近で女の子を見つめ、抱きしめなければ気がすまなかった。
その思いが、そのまま神へとシフトされていった。この世界の最大にして最後の神秘である神に。私が求めるのは、神についての概念でもなければ、説明でもない。神そのものだ。神に直接触れることだ。
人間は、神秘を前にするからこそ、謙虚にもなるし、敬虔な気持ちにもなる。神秘から目を背ける者、神秘を見出し得ない者は、しだいに腐っていくだけだ。歳を取るということ、すなわち成長して円熟するということは、決して神秘なるものをもたなくなることではない。世の中のすべてにわかったような顔をすることではない。むしろ逆に、円熟するということは、ますますこの世界というものが神秘であること、世の中のことは何もわかっていないのだということを悟っていくことのなかにあるのではないだろうか。歳をとっても、いつまでも春の訪れに神秘を感じ、恋心をもち続け、神の存在に畏敬の念を持ち続けることのなかに……。