HOME>独想録>
2005年11月の独想録
11月5日 権威へのとらわれ
人はいかに、権威やイメージによって判断が狂わされることだろうか。
たとえば、芥川賞だとか、何らかの章を受賞した小説、大学教授だとか著名な学者の書いた本、キリストだとか仏陀からメッセージを受けて書いたといわれる、いわゆるチャネリング本、こういった、ある種の権威を背景にしてその本を読んで見ると、なるほどすばらしい内容であると感じる。しかし、同じ本でありながら、何の賞も受けたことがなく、肩書きも学歴もないアマチュアが書いた本、あるいは精神的に病んだ人が書いた本であるといわれて読んだら、おそらく前者ほど感心することはないだろう。もしかしたら、「やっぱり素人が書いた程度の内容だな」と感じるかもしれない。
サルが絵筆をもって描いた絵を見せ、「これはある有名な画家が描いたものだ」といったら、それを鑑賞した人のほとんどが「なるほど、見事な絵だ」といったという話を聞いたことがある。
このように、権威によって評価が大きく分かれてしまう理由は、たとえば「こうした権威をもっている人は、自分よりずっと知識や経験や能力が豊富だから、へたなことをいうと自分の理解力を疑われて恥をかくに違いない」といった思いがあるからなのかもしれない。そこで、とりあえず、権威をもった人の作品をすばらしいといっておけば、自分もそれなりにひとかどの人間に思われるだろうと考えるのかもしれない。
もちろん、それなりに深い作品を理解するというのは、容易なことではない。だから、作品の見識眼の貧しさだとか、批判精神の貧しさといったことをいうつもりはない。
また、何らかの権威をもった人の作品であっても、それは実際にはつまらない作品であることが多いのだ、ということをいいたいわけでもない。
大切なことは、どんな本や作品であっても、そこから学ぶことができるということだ。
私たちは、大学教授の講演には耳を傾け、熱心に学ぼうとするけれども、小さな子供の言葉や、田舎の老女の言葉などは、そこから学ぼうという姿勢もなく、受け流し、軽んじたりする傾向にあるように思われる。
しかし、名もない子供や老人の言葉の中には、いわゆる権威をもった人からは学べない貴重な教えが込められていることも少なくない。どんな人に対しても誠実に接する姿勢をもつならば、そこからすばらしい教え、啓示を受けることがある。それが仮に、神からのメッセージであるとしたらならば、神は権威ある人の口を通してではなく、子供や老人の口を通して代弁させるような、粋なところをもっているようにも思われる。
もし、仰々しい肩書きをもった人の著書を読んで感心したら、今度はもう一度、その本をどこにでもいるような素人が書いた本だと思って読んでみるとよい。人間は最初の印象が強烈だから、本当に素人が書いた本だと心底思いこむことは難しいかもしれないが、それでも、そういうつもりで読んで、最初読んだときと感想が異なったなら、その異なった分だけ、自分は権威に弱いということ、権威に洗脳されやすいことを示しているともいえるし、さらに厳しい言い方をすれば、自分はどれほど相手の人間を肩書きなどで差別しているかといったことを示しているともいえるかもしれない。
逆に、素人が書いた文章でも、それが有名な権威者の書いたものであると思って読んでみると、そこから学ぶことがたくさん発見できるに違いない。
さりげなく平凡に見えるが、実は目の前にいる人は何らかのすごい権威者かもしれない。まだ子供であっても、将来、すごい権威者になる器をもった人かもしれない。
そう思うと、誰をも軽ろんじるようなことはできなくなる。
観音様という菩薩は、あらゆる人の姿に化けて人々を救済するという。どんな人も観音様の化身だと思えば、どんな人も尊ぶ気持ちも出てくる。
とはいえ、こうしたことも、しょせんは「権威」にとらわれている。「観音様」という「権威」にである。相手が観音様の化身であろうとなかろうと、尊重することが真実のあり方ではないだろうか。
権威があるとか、ないといった領域を超え、相手の存在そのものに向けられた誠意と敬意をもって、人やその作品に接するとき、おそらく何か神的なものをそこに学ぶに違いない。
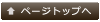
11月13日 美しい愛の想い出
人間を、その苦しみや悪しき誘惑から救ってくれる最後の希望とは何であろうか?
孤独と絶望の中で、苦しみや不条理な運命と闘っている人にとっての希望とは何なのだろう?
おそらくそれは、「美しい愛の想い出」ではないだろうか。
愛は、本質的に美しいものであろうから、「美しい」という形容詞をつけるのは余計なのかもしれない。しかしそれでもなお、愛というものがもつ美しさを強調しないではいられない。愛は目に見えるものではないが、もしも目に見えたとしたら、おそらく言語に絶するほどの美しさであるに違いない。いや、美しさを味わい尽くすよりも前に意識を失ってしまうかもしれない。
美しいという感情は、人の心を浄めてくれるものである。
愛の感情は、人の心に信頼を根付かせてくれるものである。
地上というところは、人を信じるということが、なかなかできない世界だ。世の中には、悪意をもって人をだますような人がいるし、悪意はないにしても、気まぐれや軟弱な心によって人をだましてしまう人、裏切るような人がいる。
こういう人に接すると、私たちは深く傷つき、人を信用できなくなり、疑心暗鬼となって、ついには「だまされる前にだましてやれ」などと、自分も人もだまして裏切るような人間になっていく。まるで吸血鬼に噛みつかれた人間が吸血鬼になっていくように。
こうして、私たちの心は閉ざされていき、腐敗し、混乱し、俗悪になり、誰も、何も信じられなくなる。人に知られなければ悪いことをしてもいいと思うようになり、うわべを繕って善人に見られるようとする虚栄心が育ち、他者の痛みに鈍感になり、傲慢になり、自分勝手になって、知らないうちに臭い汚泥の中で生きているかのような生を送るようになってしまう。
しかし、それでも、ときおり訪れる運命の打撃によって、こうした生き方をしている自分自身がいかに空しく、孤独であり、汚れているかということに気づかされるようになる。
これではいけない、こんな生き方をしていてはいけない、という、心の深い部分からの声が聞こえるようになる。それはまさに魂の叫びともいうべきものだ。
だからといって、お互いがお互いをだまし合うこの世界の中で、いったいどうして自分だけが誠実に生きられるだろうかと悩む。
だが、一度でも魂の声を聞いた人間は、汚泥の中につかりきって生きることはできない。そんな自分を恥じ、その醜悪さに自分というものが嫌になる。やがて、生きていても価値がないと思うようになり、この世界で生きていく自信がなくなってくるかもしれない。
そんなとき、そんな人間を救ってくれるものが、「美しい愛の想い出」ではないだろうか。
それは、かつて、真の誠実さと真心によって愛されたという経験である。
それは、なにもおおげさなものである必要はない。ほんの小さな親切だっていいのだ。愛は火のようなもので、どんなに小さくたって問題ではない。ついには大火となるであろうからだ。
問われるのは純粋性である。ビクトル・ユゴーの小説『レ・ミゼラブル』の主人公ジャン・バルジャンがそうであるように、たった一晩、宿を貸してくれて、盗んだ銀の燭台を「君にあげたのだ」といって許してくれた聖職者の真心からの親切(愛)の想い出によって、その後の彼の人生を最後まで正しい方向に導いたように、愛の想い出というものは、永遠に人の中で燃え続ける炎となる。
たとえ、消えてしまったかのように見えても、その輝きが思い出されるならば、たちまち再燃して心を浄化し、あらゆる恐怖というものを焼き払い、生きる力を復活させ、人に対する信頼を呼び覚まし、誠実さを貫くことのできる勇気と、たくましさをもった人間に変容させるのだ。
そうした、何の打算も野心もない、まったくの純粋な心から親切にされた経験、愛された経験という想い出をもつ人は幸いである。
心が汚れたと思ったとき、生きることに疲れたとき、そんな美しい愛の想い出を静かに振り返るとよい。「そんな経験はない」と思っても、注意深く過去を振り返るならば、ひとつやふたつくらい、見つかるはずだ。
それでも実際に、そんな愛の経験などまったくないという人も、いるかもしれない。孤独と裏切りの中だけで、ずっと生きてきたという人もいるかもしれない。
私はこの世の中で、愛されないということほど悲惨なことはなく、愛されなければ、人は生きていくことはできないとさえ思っている。
しかし反面で、まったく矛盾したことをいうようだが、「愛なんかなくたって生きていけるのだ」とも思っている。実際、この世の中に、真の意味で「愛」といったものが、どのくらい存在しているというのか? 愛されているようでも、実際に愛されているのは、自分の財産、自分の肉体、自分の肩書き、自分の才能といったものかもしれない。そういったものは自分そのものではなく、単なる付属品に過ぎない。多くの人は、愛ではないものを愛と勘違いして生きているだけに過ぎないのかもしれない。それでも立派に生きているのなら、私たちは誰からの愛もなくたって、生きていけるということになる。
とはいえ、愛というものは、同時に美しさでもあるのだ。
愛がない人生は、少なくてもそこに美というものが存在しない可能性がある。その場合、愛する人こそが美の創造者なのであって、「愛される人」ではない。愛されることは喜びではあるが、それだけでは、その人の人生を美しい色彩で染めることはない。その意味では、愛されないことは深刻ではあるが、愛さないことの方がより深刻であるといえる。
美しさというものもまた、火と同じように、その偉大さは大きさによるものではない。爪の上に乗るほどの大きさであっても、美しい宝石は、凡庸な巨石よりも価値をもつ。そして、人間の愛の場合、その美しさというものは、動機の純粋性によって決まる。
たとえ、お年寄りに席を譲るという小さな行為であっても、何の打算もなく、真の純粋性から発した行為であるならば、そこには、あきらかに愛と美がある。たとえいかに小さくても、その愛と美は本物なのであり、本物であるがゆえに、その愛を受けた人の心には炎がともされ、その人の心の中で一生涯燃え続ける可能性をもつようになる。そしていつか、絶望や腐敗や苦悩の中に立たされたとき、その美しい愛の想い出が、誠実な人間らしい生き方へと呼び戻してくれるかもしれない。
現在、この世界がもっとも必要としているのは、腐敗や混乱の中にあってもそれに染まることなく、愛と純粋性と誠実さを断固として貫くことのできる人間に他ならない。すなわち、一人でも多くの人の心の中に「美しい愛の想い出」を書き込んでいく人間である。
2005年11月の独想録
11月5日 権威へのとらわれ
人はいかに、権威やイメージによって判断が狂わされることだろうか。
たとえば、芥川賞だとか、何らかの章を受賞した小説、大学教授だとか著名な学者の書いた本、キリストだとか仏陀からメッセージを受けて書いたといわれる、いわゆるチャネリング本、こういった、ある種の権威を背景にしてその本を読んで見ると、なるほどすばらしい内容であると感じる。しかし、同じ本でありながら、何の賞も受けたことがなく、肩書きも学歴もないアマチュアが書いた本、あるいは精神的に病んだ人が書いた本であるといわれて読んだら、おそらく前者ほど感心することはないだろう。もしかしたら、「やっぱり素人が書いた程度の内容だな」と感じるかもしれない。
サルが絵筆をもって描いた絵を見せ、「これはある有名な画家が描いたものだ」といったら、それを鑑賞した人のほとんどが「なるほど、見事な絵だ」といったという話を聞いたことがある。
このように、権威によって評価が大きく分かれてしまう理由は、たとえば「こうした権威をもっている人は、自分よりずっと知識や経験や能力が豊富だから、へたなことをいうと自分の理解力を疑われて恥をかくに違いない」といった思いがあるからなのかもしれない。そこで、とりあえず、権威をもった人の作品をすばらしいといっておけば、自分もそれなりにひとかどの人間に思われるだろうと考えるのかもしれない。
もちろん、それなりに深い作品を理解するというのは、容易なことではない。だから、作品の見識眼の貧しさだとか、批判精神の貧しさといったことをいうつもりはない。
また、何らかの権威をもった人の作品であっても、それは実際にはつまらない作品であることが多いのだ、ということをいいたいわけでもない。
大切なことは、どんな本や作品であっても、そこから学ぶことができるということだ。
私たちは、大学教授の講演には耳を傾け、熱心に学ぼうとするけれども、小さな子供の言葉や、田舎の老女の言葉などは、そこから学ぼうという姿勢もなく、受け流し、軽んじたりする傾向にあるように思われる。
しかし、名もない子供や老人の言葉の中には、いわゆる権威をもった人からは学べない貴重な教えが込められていることも少なくない。どんな人に対しても誠実に接する姿勢をもつならば、そこからすばらしい教え、啓示を受けることがある。それが仮に、神からのメッセージであるとしたらならば、神は権威ある人の口を通してではなく、子供や老人の口を通して代弁させるような、粋なところをもっているようにも思われる。
もし、仰々しい肩書きをもった人の著書を読んで感心したら、今度はもう一度、その本をどこにでもいるような素人が書いた本だと思って読んでみるとよい。人間は最初の印象が強烈だから、本当に素人が書いた本だと心底思いこむことは難しいかもしれないが、それでも、そういうつもりで読んで、最初読んだときと感想が異なったなら、その異なった分だけ、自分は権威に弱いということ、権威に洗脳されやすいことを示しているともいえるし、さらに厳しい言い方をすれば、自分はどれほど相手の人間を肩書きなどで差別しているかといったことを示しているともいえるかもしれない。
逆に、素人が書いた文章でも、それが有名な権威者の書いたものであると思って読んでみると、そこから学ぶことがたくさん発見できるに違いない。
さりげなく平凡に見えるが、実は目の前にいる人は何らかのすごい権威者かもしれない。まだ子供であっても、将来、すごい権威者になる器をもった人かもしれない。
そう思うと、誰をも軽ろんじるようなことはできなくなる。
観音様という菩薩は、あらゆる人の姿に化けて人々を救済するという。どんな人も観音様の化身だと思えば、どんな人も尊ぶ気持ちも出てくる。
とはいえ、こうしたことも、しょせんは「権威」にとらわれている。「観音様」という「権威」にである。相手が観音様の化身であろうとなかろうと、尊重することが真実のあり方ではないだろうか。
権威があるとか、ないといった領域を超え、相手の存在そのものに向けられた誠意と敬意をもって、人やその作品に接するとき、おそらく何か神的なものをそこに学ぶに違いない。
11月13日 美しい愛の想い出
人間を、その苦しみや悪しき誘惑から救ってくれる最後の希望とは何であろうか?
孤独と絶望の中で、苦しみや不条理な運命と闘っている人にとっての希望とは何なのだろう?
おそらくそれは、「美しい愛の想い出」ではないだろうか。
愛は、本質的に美しいものであろうから、「美しい」という形容詞をつけるのは余計なのかもしれない。しかしそれでもなお、愛というものがもつ美しさを強調しないではいられない。愛は目に見えるものではないが、もしも目に見えたとしたら、おそらく言語に絶するほどの美しさであるに違いない。いや、美しさを味わい尽くすよりも前に意識を失ってしまうかもしれない。
美しいという感情は、人の心を浄めてくれるものである。
愛の感情は、人の心に信頼を根付かせてくれるものである。
地上というところは、人を信じるということが、なかなかできない世界だ。世の中には、悪意をもって人をだますような人がいるし、悪意はないにしても、気まぐれや軟弱な心によって人をだましてしまう人、裏切るような人がいる。
こういう人に接すると、私たちは深く傷つき、人を信用できなくなり、疑心暗鬼となって、ついには「だまされる前にだましてやれ」などと、自分も人もだまして裏切るような人間になっていく。まるで吸血鬼に噛みつかれた人間が吸血鬼になっていくように。
こうして、私たちの心は閉ざされていき、腐敗し、混乱し、俗悪になり、誰も、何も信じられなくなる。人に知られなければ悪いことをしてもいいと思うようになり、うわべを繕って善人に見られるようとする虚栄心が育ち、他者の痛みに鈍感になり、傲慢になり、自分勝手になって、知らないうちに臭い汚泥の中で生きているかのような生を送るようになってしまう。
しかし、それでも、ときおり訪れる運命の打撃によって、こうした生き方をしている自分自身がいかに空しく、孤独であり、汚れているかということに気づかされるようになる。
これではいけない、こんな生き方をしていてはいけない、という、心の深い部分からの声が聞こえるようになる。それはまさに魂の叫びともいうべきものだ。
だからといって、お互いがお互いをだまし合うこの世界の中で、いったいどうして自分だけが誠実に生きられるだろうかと悩む。
だが、一度でも魂の声を聞いた人間は、汚泥の中につかりきって生きることはできない。そんな自分を恥じ、その醜悪さに自分というものが嫌になる。やがて、生きていても価値がないと思うようになり、この世界で生きていく自信がなくなってくるかもしれない。
そんなとき、そんな人間を救ってくれるものが、「美しい愛の想い出」ではないだろうか。
それは、かつて、真の誠実さと真心によって愛されたという経験である。
それは、なにもおおげさなものである必要はない。ほんの小さな親切だっていいのだ。愛は火のようなもので、どんなに小さくたって問題ではない。ついには大火となるであろうからだ。
問われるのは純粋性である。ビクトル・ユゴーの小説『レ・ミゼラブル』の主人公ジャン・バルジャンがそうであるように、たった一晩、宿を貸してくれて、盗んだ銀の燭台を「君にあげたのだ」といって許してくれた聖職者の真心からの親切(愛)の想い出によって、その後の彼の人生を最後まで正しい方向に導いたように、愛の想い出というものは、永遠に人の中で燃え続ける炎となる。
たとえ、消えてしまったかのように見えても、その輝きが思い出されるならば、たちまち再燃して心を浄化し、あらゆる恐怖というものを焼き払い、生きる力を復活させ、人に対する信頼を呼び覚まし、誠実さを貫くことのできる勇気と、たくましさをもった人間に変容させるのだ。
そうした、何の打算も野心もない、まったくの純粋な心から親切にされた経験、愛された経験という想い出をもつ人は幸いである。
心が汚れたと思ったとき、生きることに疲れたとき、そんな美しい愛の想い出を静かに振り返るとよい。「そんな経験はない」と思っても、注意深く過去を振り返るならば、ひとつやふたつくらい、見つかるはずだ。
それでも実際に、そんな愛の経験などまったくないという人も、いるかもしれない。孤独と裏切りの中だけで、ずっと生きてきたという人もいるかもしれない。
私はこの世の中で、愛されないということほど悲惨なことはなく、愛されなければ、人は生きていくことはできないとさえ思っている。
しかし反面で、まったく矛盾したことをいうようだが、「愛なんかなくたって生きていけるのだ」とも思っている。実際、この世の中に、真の意味で「愛」といったものが、どのくらい存在しているというのか? 愛されているようでも、実際に愛されているのは、自分の財産、自分の肉体、自分の肩書き、自分の才能といったものかもしれない。そういったものは自分そのものではなく、単なる付属品に過ぎない。多くの人は、愛ではないものを愛と勘違いして生きているだけに過ぎないのかもしれない。それでも立派に生きているのなら、私たちは誰からの愛もなくたって、生きていけるということになる。
とはいえ、愛というものは、同時に美しさでもあるのだ。
愛がない人生は、少なくてもそこに美というものが存在しない可能性がある。その場合、愛する人こそが美の創造者なのであって、「愛される人」ではない。愛されることは喜びではあるが、それだけでは、その人の人生を美しい色彩で染めることはない。その意味では、愛されないことは深刻ではあるが、愛さないことの方がより深刻であるといえる。
美しさというものもまた、火と同じように、その偉大さは大きさによるものではない。爪の上に乗るほどの大きさであっても、美しい宝石は、凡庸な巨石よりも価値をもつ。そして、人間の愛の場合、その美しさというものは、動機の純粋性によって決まる。
たとえ、お年寄りに席を譲るという小さな行為であっても、何の打算もなく、真の純粋性から発した行為であるならば、そこには、あきらかに愛と美がある。たとえいかに小さくても、その愛と美は本物なのであり、本物であるがゆえに、その愛を受けた人の心には炎がともされ、その人の心の中で一生涯燃え続ける可能性をもつようになる。そしていつか、絶望や腐敗や苦悩の中に立たされたとき、その美しい愛の想い出が、誠実な人間らしい生き方へと呼び戻してくれるかもしれない。
現在、この世界がもっとも必要としているのは、腐敗や混乱の中にあってもそれに染まることなく、愛と純粋性と誠実さを断固として貫くことのできる人間に他ならない。すなわち、一人でも多くの人の心の中に「美しい愛の想い出」を書き込んでいく人間である。