HOME>独想録>
2002年11月の独想録
11月2日 クリシュナムルティについて
クリシュナムルティは、1986年に90歳で世を去ったインドの思想家である。最初、救世主として神智学協会に見いだされ、しばらく活動するが、やがて「真理に至るには自分をよりどころとせよ」という講演をした後で協会を脱会。以後、単独でインド、アメリカ、ヨーロッパを巡り、講演や対話を行った。また、彼の思想に基づく学校の運営にもあたった。
クリシュナムルティの本は、哲学書のコーナーではなく、精神世界コーナーに置かれている。ともすると、怪しげなオカルト本などと肩を並べていたりするので、あまり知らない人は、カルト教祖か何かだと誤解されるかもしれない。
しかし、クリシュナムルティは、「組織は真理探究の妨げになる」として、いかなる宗教組織も認めなかった。また、宗教に関しても否定していた。正確には、宗教のもつ独断的な教義を否定したのであるが、同時に、あらゆるオカルト的な事柄も否定した。ただし、オカルト的な現象の存在そのものを否定したわけではない。実際、彼は少年時代、リードビーターという霊能者とアストラル世界(霊界)へ魂の状態で移行し、そこに存在するといわれる世界教師(マスター)から教えを受け、その内容を書いた本まで出している(『大使のみ足のもとに』)。
けれども、そうしたことは、真実に生きることとは無縁であるばかりか、独善的な幻想に埋没してしまうと彼は主張した。
クリシュナムルティは、何か特定の教義や価値観などを説いたわけではなく、自分を見つめることにより、真実に気づくということだけを、ひたすら説き続けただけである。
彼によれば、私たちは、あらゆる偏見や主観的にゆがめられた価値観に汚染されている。ひらたくいえば「真理とはこうだ」と勝手に信じ込んでいる。それが、あらゆる争いや不幸の根本的な原因であるとする。そのためクリシュナムルティは、「何も信じるな」というのである。グルなどに頼ってはならない。また、苦しみや現実から逃げるなと説くのだ。ただ、事実をありのままに見つめなさいと。彼の教えは、さまざまなテーマについて言及されているが、つきつめれば、これだけである。
こう紹介すると、さぞかし堅物でクールな人物だと思われるかもしれないが、実に紳士的であたたかい人柄だった。だが、その優しさは、さりげなく自然で、演技じみていたり、わざとらしさといったものがなかった。クリシュナムルティが亡くなる直前にそばにいた、ある人からこんな話を聞いた。その人は、「今までやさしくしてくれて、ありがとう」とお礼をいったそうだ。するとクリシュナムルティは、「ただ、自分自身であり続けただけだよ」と答えたという。彼の人柄をにじませる言葉ではないだろうか。
私は、クリシュナムルティほど厳しい見解はもっていない。宗教や組織を、必ずしも否定はしない。しかし、基本的には彼の考え方に賛成で、私自身の精神世界に関する基礎を築くに際して、もっとも影響を受けたひとりである。
1989年、日本のクリシュナムルティ・センターの主催で、マドラス、リシバレー、ラジガートなどにある彼の学校をまわり、国際的な集会に参加した。だが、彼はもう存命していなかったわけで、このような場所を巡って、では何を得たのかといわれると、観光旅行以上のものではないというのが正直な感想である。彼が活動していたところを見てまわっても、彼の教えがよりよく理解できる、というわけでもない。ただ、生前、彼と交流した人たちの話は、いくぶん、参考にはなったけれども。したがって、旅行の内容そのものについては、特に報告することはない。
世の中には、実にさまざまな教えがあり、教義があり、さまざまなことをいう人がいる。多くの人がそのような教えなり組織なり指導者にすがる。そして、何らかの情報を与えてもらう。「さあよいか。これを信じれば救われるのだよ」といわれて。そして、ほとんど鵜呑みにするように、それを信じ込む。そして、その教えが形成する「世界」に埋没する。そこには、自分を傷つけたり否定するような「現実」がシャットアウトされている。ゆりかごのような心地よさがある。「癒し」を求める人の、かっこうの避難所が提供されている。
だが、「癒し」と「麻痺」を混同してはならない。特定の価値観で精神を染めることで得られる心の安定は、麻痺であって癒しではない。麻酔で痛みが消失しても病が治ったことにはならないように。心が麻痺させられると、自分の教えだけが最高で、その他はすべて邪道だというようなことを口にし、自分の教えを批判する人に対して異様なまでの攻撃性を向けるようになる。それは、麻痺の状態から覚めさせられるのが恐ろしいからである。つまり、まったく癒されてはいないのだ。
癒しとは、現実の世界で実現する。ありのままを、ありのままに見ることによって。苦悩の正体が見破られたときに、癒しが訪れる。それには、苦しみと向き合わなければならない。辛いことだけれども、真の癒しを求める人が、いつかは直面しなければならないことである。
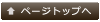
11月11日 なぜ「善い人」が苦しむのか?
再び、内面的な随想を語ることにしよう。
ときどきため息混じりに思うことは、なぜ「善い人」が不幸にあったり苦しんだりするのか、ということである。もちろん、これは絶対にいつもそうだというわけではないけれども、そういうことがけっこう多い。反面、陰で人をいじめたり不正を行っているような人が幸運で、その悪意や傲慢さや、人を虐げる権威などを失うことなく、安定した生活を悠々と送っていたりする。こういう現実を見ると、果たしてこの世に正義だとか、神などは存在するのか、と思ってしまう。いったいなぜ神は、善い人を救ってくれないのだろうかと。
こうした不条理を仏教的に解釈すれば、因果応報ということになるのだろう。つまり、前世で悪いことをしたから、たとえ善人でも不幸になるのだと。悪い人は、前世で善いことをしたから、いわば「貯金」があるから、この世で幸せなのであると。
これもまた、ひとつの解釈ではあろう。
しかしながら、こうした考え方に「神」の入る余地はない。世界は純然たる「メカニズム」である。実際、仏教に「神」は登場しない(仏教でいう神は、西洋でいう精霊にあたる)。あえていえば「法(ダルマ)」が、神にあたるといえばあたるのかもしれないが、これは宇宙の法則のことで、人格的な神をさすものではない。
もしも神が存在していなければ、あるいは存在しても、それは法則のようなもので人格をもたなければ、私たちは自分に襲いかかり、誰にもわかってもらえない苦しみを、何という孤独のまま抱え込まなければならないことだろう。それは北極で、独り迷子になったような、耐え難いものである。この苦しみを、誰かがわかってくれている、誰かが心配してくれている、という思いがあればこそ、人間は耐えていけるのではないのか? 「私は決して独りではない」という思いが、苦しみにおいてもなお、生きる力を与えてくれるのではないのか?
私たちは、たとえ自分の苦しみを少しも解決できなくても、理解し、共感してくれる人がいるだけで、励まされ、癒される思いがする。それは、高い場所から憐れみを垂れるような「同情」ではなく、自分のことのように苦しんでくれる「共感」である。共感してくれる人がいるというだけで、何と癒されることか。これこそが「救い」ではないだろうか?
ならば、神も「共感」によって、私たちを救おうとしているのではないだろうか。つまり、神もまた、私たちの苦しみを、自分のことのように苦しんでいるのかもしれない。
しかし、私たちは、神を見ることはできない。たとえ神が私たちに共感してくれているとしても、そのことを知ることはできない。
そのかわり、神は、「僕(しもべ)」を通して、自らも苦しんでいることを告げようとしているのかもしれない。つまり、神の心をもった人間を通して。
そして、真の救いが「共感」であるとするなら、その「僕」は、共感する人たちということになるだろう。
けれども、共感するには、自分も苦しみや悲しみが何であるかを知らなければならない。何不自由なく恵まれて育った人は、同情はできるかもしれないが、共感することはできない。共感は、多少なりとも、同じような苦しみや悲しみを経験した者だけがもつことのできる特別な資質である。
「善い人」とは、疑いもなく、神の心に近い人のことであろう。神の愛を自分自身のものとしている人のことだ。そして神の愛は、繰り返し述べているように、同情ではなく共感である。ともに苦しむことである。人は、ともに苦しんでくれる人の存在を通して、救われるのであるから。
これが、「善い人」が、不幸や苦しみに遭遇する理由なのかもしれない。
すなわち、悪いことをした報いのせいというよりも、反対に、神の愛に近づくほど進歩した魂の持ち主ではないのかと。神の救いの触媒になるために、触媒となって、苦しむ人たちを癒すために、あえて苦しみを経験しているのではないのかと。
。
私たちは、苦しみや悲しみを背負い、目に涙を浮かべながらも、なお人間としての道を踏み外さずに生きている人に接するとき、大いなる癒しと励ましを得る。
そんな人を通してこそ、私たちは神の救いの手をリアルに感じることができる。
いま、さまざまな苦しみや悲しみを抱えながらも、人を愛することを忘れない人は、いつの日かきっと、人を癒す不思議な力を発揮するときがくるに違いない。
それは小手先のテクニックではなく、人格的な中枢から放たれる神の光によるものである。
2002年11月の独想録
11月2日 クリシュナムルティについて
クリシュナムルティは、1986年に90歳で世を去ったインドの思想家である。最初、救世主として神智学協会に見いだされ、しばらく活動するが、やがて「真理に至るには自分をよりどころとせよ」という講演をした後で協会を脱会。以後、単独でインド、アメリカ、ヨーロッパを巡り、講演や対話を行った。また、彼の思想に基づく学校の運営にもあたった。
クリシュナムルティの本は、哲学書のコーナーではなく、精神世界コーナーに置かれている。ともすると、怪しげなオカルト本などと肩を並べていたりするので、あまり知らない人は、カルト教祖か何かだと誤解されるかもしれない。
しかし、クリシュナムルティは、「組織は真理探究の妨げになる」として、いかなる宗教組織も認めなかった。また、宗教に関しても否定していた。正確には、宗教のもつ独断的な教義を否定したのであるが、同時に、あらゆるオカルト的な事柄も否定した。ただし、オカルト的な現象の存在そのものを否定したわけではない。実際、彼は少年時代、リードビーターという霊能者とアストラル世界(霊界)へ魂の状態で移行し、そこに存在するといわれる世界教師(マスター)から教えを受け、その内容を書いた本まで出している(『大使のみ足のもとに』)。
けれども、そうしたことは、真実に生きることとは無縁であるばかりか、独善的な幻想に埋没してしまうと彼は主張した。
クリシュナムルティは、何か特定の教義や価値観などを説いたわけではなく、自分を見つめることにより、真実に気づくということだけを、ひたすら説き続けただけである。
彼によれば、私たちは、あらゆる偏見や主観的にゆがめられた価値観に汚染されている。ひらたくいえば「真理とはこうだ」と勝手に信じ込んでいる。それが、あらゆる争いや不幸の根本的な原因であるとする。そのためクリシュナムルティは、「何も信じるな」というのである。グルなどに頼ってはならない。また、苦しみや現実から逃げるなと説くのだ。ただ、事実をありのままに見つめなさいと。彼の教えは、さまざまなテーマについて言及されているが、つきつめれば、これだけである。
こう紹介すると、さぞかし堅物でクールな人物だと思われるかもしれないが、実に紳士的であたたかい人柄だった。だが、その優しさは、さりげなく自然で、演技じみていたり、わざとらしさといったものがなかった。クリシュナムルティが亡くなる直前にそばにいた、ある人からこんな話を聞いた。その人は、「今までやさしくしてくれて、ありがとう」とお礼をいったそうだ。するとクリシュナムルティは、「ただ、自分自身であり続けただけだよ」と答えたという。彼の人柄をにじませる言葉ではないだろうか。
私は、クリシュナムルティほど厳しい見解はもっていない。宗教や組織を、必ずしも否定はしない。しかし、基本的には彼の考え方に賛成で、私自身の精神世界に関する基礎を築くに際して、もっとも影響を受けたひとりである。
1989年、日本のクリシュナムルティ・センターの主催で、マドラス、リシバレー、ラジガートなどにある彼の学校をまわり、国際的な集会に参加した。だが、彼はもう存命していなかったわけで、このような場所を巡って、では何を得たのかといわれると、観光旅行以上のものではないというのが正直な感想である。彼が活動していたところを見てまわっても、彼の教えがよりよく理解できる、というわけでもない。ただ、生前、彼と交流した人たちの話は、いくぶん、参考にはなったけれども。したがって、旅行の内容そのものについては、特に報告することはない。
世の中には、実にさまざまな教えがあり、教義があり、さまざまなことをいう人がいる。多くの人がそのような教えなり組織なり指導者にすがる。そして、何らかの情報を与えてもらう。「さあよいか。これを信じれば救われるのだよ」といわれて。そして、ほとんど鵜呑みにするように、それを信じ込む。そして、その教えが形成する「世界」に埋没する。そこには、自分を傷つけたり否定するような「現実」がシャットアウトされている。ゆりかごのような心地よさがある。「癒し」を求める人の、かっこうの避難所が提供されている。
だが、「癒し」と「麻痺」を混同してはならない。特定の価値観で精神を染めることで得られる心の安定は、麻痺であって癒しではない。麻酔で痛みが消失しても病が治ったことにはならないように。心が麻痺させられると、自分の教えだけが最高で、その他はすべて邪道だというようなことを口にし、自分の教えを批判する人に対して異様なまでの攻撃性を向けるようになる。それは、麻痺の状態から覚めさせられるのが恐ろしいからである。つまり、まったく癒されてはいないのだ。
癒しとは、現実の世界で実現する。ありのままを、ありのままに見ることによって。苦悩の正体が見破られたときに、癒しが訪れる。それには、苦しみと向き合わなければならない。辛いことだけれども、真の癒しを求める人が、いつかは直面しなければならないことである。
11月11日 なぜ「善い人」が苦しむのか?
再び、内面的な随想を語ることにしよう。
ときどきため息混じりに思うことは、なぜ「善い人」が不幸にあったり苦しんだりするのか、ということである。もちろん、これは絶対にいつもそうだというわけではないけれども、そういうことがけっこう多い。反面、陰で人をいじめたり不正を行っているような人が幸運で、その悪意や傲慢さや、人を虐げる権威などを失うことなく、安定した生活を悠々と送っていたりする。こういう現実を見ると、果たしてこの世に正義だとか、神などは存在するのか、と思ってしまう。いったいなぜ神は、善い人を救ってくれないのだろうかと。
こうした不条理を仏教的に解釈すれば、因果応報ということになるのだろう。つまり、前世で悪いことをしたから、たとえ善人でも不幸になるのだと。悪い人は、前世で善いことをしたから、いわば「貯金」があるから、この世で幸せなのであると。
これもまた、ひとつの解釈ではあろう。
しかしながら、こうした考え方に「神」の入る余地はない。世界は純然たる「メカニズム」である。実際、仏教に「神」は登場しない(仏教でいう神は、西洋でいう精霊にあたる)。あえていえば「法(ダルマ)」が、神にあたるといえばあたるのかもしれないが、これは宇宙の法則のことで、人格的な神をさすものではない。
もしも神が存在していなければ、あるいは存在しても、それは法則のようなもので人格をもたなければ、私たちは自分に襲いかかり、誰にもわかってもらえない苦しみを、何という孤独のまま抱え込まなければならないことだろう。それは北極で、独り迷子になったような、耐え難いものである。この苦しみを、誰かがわかってくれている、誰かが心配してくれている、という思いがあればこそ、人間は耐えていけるのではないのか? 「私は決して独りではない」という思いが、苦しみにおいてもなお、生きる力を与えてくれるのではないのか?
私たちは、たとえ自分の苦しみを少しも解決できなくても、理解し、共感してくれる人がいるだけで、励まされ、癒される思いがする。それは、高い場所から憐れみを垂れるような「同情」ではなく、自分のことのように苦しんでくれる「共感」である。共感してくれる人がいるというだけで、何と癒されることか。これこそが「救い」ではないだろうか?
ならば、神も「共感」によって、私たちを救おうとしているのではないだろうか。つまり、神もまた、私たちの苦しみを、自分のことのように苦しんでいるのかもしれない。
しかし、私たちは、神を見ることはできない。たとえ神が私たちに共感してくれているとしても、そのことを知ることはできない。
そのかわり、神は、「僕(しもべ)」を通して、自らも苦しんでいることを告げようとしているのかもしれない。つまり、神の心をもった人間を通して。
そして、真の救いが「共感」であるとするなら、その「僕」は、共感する人たちということになるだろう。
けれども、共感するには、自分も苦しみや悲しみが何であるかを知らなければならない。何不自由なく恵まれて育った人は、同情はできるかもしれないが、共感することはできない。共感は、多少なりとも、同じような苦しみや悲しみを経験した者だけがもつことのできる特別な資質である。
「善い人」とは、疑いもなく、神の心に近い人のことであろう。神の愛を自分自身のものとしている人のことだ。そして神の愛は、繰り返し述べているように、同情ではなく共感である。ともに苦しむことである。人は、ともに苦しんでくれる人の存在を通して、救われるのであるから。
これが、「善い人」が、不幸や苦しみに遭遇する理由なのかもしれない。
すなわち、悪いことをした報いのせいというよりも、反対に、神の愛に近づくほど進歩した魂の持ち主ではないのかと。神の救いの触媒になるために、触媒となって、苦しむ人たちを癒すために、あえて苦しみを経験しているのではないのかと。
。
私たちは、苦しみや悲しみを背負い、目に涙を浮かべながらも、なお人間としての道を踏み外さずに生きている人に接するとき、大いなる癒しと励ましを得る。
そんな人を通してこそ、私たちは神の救いの手をリアルに感じることができる。
いま、さまざまな苦しみや悲しみを抱えながらも、人を愛することを忘れない人は、いつの日かきっと、人を癒す不思議な力を発揮するときがくるに違いない。
それは小手先のテクニックではなく、人格的な中枢から放たれる神の光によるものである。