HOME>独想録>
2002年2月の独想録
2月7日 経験から美徳を学ぶ人と悪徳を増長させる人の違い
人間が、本当に自分を向上させたいと思うときというのは、何か願望があるとき、あるいは、苦しい状況から脱出したいと思うとき、大きくわけて、この2つがあるように思われる。いずれも、願望であることに違いはない。
ところで、これら両者の願望によって、人はその行く先に差がでてくるのだろうか?
前者の場合、何か願望があり、その成就に向けて努力するときには、(その願望の内容にもよるが)自分の「能力」の向上に磨きをかけるという傾向があるようだ。
一方、苦しい状況から脱出したい、苦しみを解決したいという場合、「能力向上」だけでなく、「人間性の向上」という要素が強く現れるように思う。
つまり、苦しい経験をすることにより、他者への思いやりとか、謙虚な気持ちといったことを学ぶようになるのではないかと。
前者の場合は、自分の願望獲得のために、他者への思いやりを増そうとしたり、謙虚な気持ちを養おうと心がけようとすることは、あまりないように思われる。むしろ、冷徹で高慢な気持ちを助長させてしまうことの方が多いかもしれない。
とはいえ、苦しい経験をしても、かえって人をねたんだり、いじけたり、自分の苦しみを人のせいにする人もいる。幸せな経験をしても、そのことから他者への思いやりを目覚めさせたり、謙虚になる人もいる。だから、本当にこのような問題は、一概にこうだと決めつけることはできないと思うのだが、ある程度の傾向はあるかもしれない。
これは、あまり根拠のない、私の勝手な憶測から出た数字なのだが、だいたい10人のうち1人いるかいないかくらいの人が、幸運に恵まれながら、人間性を向上させていく人である。こういう人は、本当の意味で幸せな人だ。自らの成功や幸運を誇らず、自慢せず、謙虚で、やさしく、思いやりを、ますます育てていくのだ。こういう性格だから、ますます成功と幸運を呼び寄せていくだろう。
一方、不運や苦しみに悩んでも、自らを反省することなく世の中を呪い、ますます不正直で狡猾で、傲慢で冷たくなってしまう人もいる。こういう人は、残念ながら、10人に3人くらいはいるように思われる。こういう人は、逆に幸運が訪れると、それは自分の偉大さのためだと思って高慢となり、専制的になってしまう。結局、こういう性格なので、幸運も長続きせず、苦しみや不運に突き落とされることになるだろう。本当の意味で、気の毒な人である。
そして、残りの6人くらいが、人生の経験から、そこそこ教訓を学びながら、進歩していく平均的な人ではないかと思う。
では、幸運から美徳を養う人がいるかと思えば、そこから悪徳を増長させる人もおり、苦しみから美徳を学ぶ人がいるかと思えば、それから悪徳を増長させてしまう人がいるというのは、どこに違いがあるのだろうか?
思うに、それはおそらく人生の初期の段階で、どのような人間関係を経験したかによって、決定されてしまうのではないだろうか。信頼できるよい人から影響を受けた人と、信用できない不誠実な人から影響を受けた人の違い、つまり、人間への信頼感を持つか、不信感を持つか、その違いではないかと思うのだ。何事もそうであるが、最初の経験というのは、強いインパクトとして、その人の心の中に刻印され、それがその人の生き様に、少なからぬ影響を与えるものである。
こう考えると、私たちが子供たちに接するときには、注意しなければならないと思うのだ。すなわち、私たちの接し方、その態度は、その子供の生涯に少なからぬ影響を与えるほどの、重い責任があるということを。子供に接するときには、私たちはひそかに襟を正し、ある種の緊張感を持って接しなければならない。真剣に、優しく、誠実に接し、この世界には信頼できる人間が存在するのだということを、しっかりと彼の胸に刻印してあげる必要があると思うのだ。
さらにまた、子供に限らず、感受性の豊かな人に接するときも、私たちは同様の責任を持っているという点で緊張する必要があるだろう。感受性の豊かな人は、自分と接する相手から、大きく影響を受けるからである。
人間は、関係する相手によって世界観を形成する。信頼と誠意で接すれば、彼は世界を信頼できるものと見るだろう。そして、そんな世界観からは善意と幸せが湧き上がってくる。だが、信頼できず不誠実な世界観を持たせてしまったならば、そこから湧き上がるものは、悪意と混乱と悲しみだけである。
私たちは、自分と接するすべての人の幸福に対して、想像する以上に、大きな責任を負っているのではないかと思う。
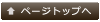
2月18日 修養の道と宗教の道
道徳や倫理といった修養の道と、宗教の道とは、どのように違うのだろうか?
宗教においても、修養の道は説かれる。すなわち、隣人を愛しなさい、生きとし生けるものに慈悲を施しなさい、淫らな行いをしてはいけません、嘘をついてはいけません……といったように、自分自身を訓練して、正しい生き方が送れるように努力することが要請される。その点では、修養の道も宗教の道も、ほとんど変わらないように思われる。
しかし、宗教の道というのは、たとえそのような修養をしているときであっても、「自分がそうしているのだ」とは思わない。「神様にそうさせていただいているのだ」と思う。あるいは「神様が自分を使って、そのようにさせているのだ」と思う。
結局のところ、宗教の道とは、自分というものを、すべて神に手渡してしまう道ではないだろうか。
私たちは、ともすると、神様を自分の中にひきづりこもうとする。つまり、神を自分の都合のいい存在として利用しようとする。だが、本当の宗教の道は反対だ。
それは逆に、自分を神様の中に捧げてしまう道である。「自分を神の都合のいい存在にする道」である。聖フランチェスコの言葉を借りれば「私をあなたの平和の道具としてお使いください」ということなのだろう。
宗教の道は、自我を抹殺する道であり、キリスト教の説く「謙虚」の美徳を追い求める道である。そして、何が起きても、「これでいいのだ、神の御心のままになさしめたまえ」と感謝できる心境を養う道である。何をやるにしても、自分がやるんではないんだ、神様がやるんだ、と思う心境への道なのだと思う。
修養の道は、(おそらく)反道徳的な人を排除し、憎み、悪を責めるであろう。しかし宗教の道は、そのようなことはしない。そのようなことが起こったのも、神がそれを認めたからだと思う。そのため、反道徳的な人を排除することも、憎むことも、責めることもしない。もちろんこのことは、反道徳的な行為を野放しにしていい、という意味ではない。反道徳的な行為をして人を苦しめているなら、それは是正していかなければならない。
だが、その是正行為の根底にあるのは、排除でも憎しみでも、責めることでもなく、深い理解に基づく愛とやさしさである。たとえその愛が峻厳という形をとらざるを得ない場合であっても、愛を根底にすることが、宗教者の道である。
真の宗教であれば、反道徳も、悪も、認めることはない。ただあるのは「未熟さ」だけだ。どんな人間(魂)であっても、最初は未熟であろう。未熟そのものは悪いことではない。未熟の結果として犯された「反道徳」や「悪」は、たとえ社会ではそう定義されようと、実はそうではなく、ひとつの学びのための失敗にすぎない。人間の成長の多くは、失敗を通してこそ促進されるものだ。本来は、失敗などという言葉も適当ではなく、それは自分の都合で勝手に決めつけたものであって、私たちのいう失敗とは、実は「学びのチャンス」以外のなにものでもない。
それゆえ、この世には「悪」も、「悪人」も、存在しない。相手が犯した「悪」を、「失敗」と見てあげること、そしてそんな相手を「悪人」ではなく、「失敗から教訓を学んで成長しようとしている人」と見ることによって、相手を善へと、また相手の魂を覚醒へと、促してあげることができるのだと思う。
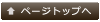
2月23日 自殺という人生の危機を乗り越える
毎年、3万人を超える人たちが自らの生命を断っているというのは、驚きである。1日にしておよそ80人。20分に一人以上が、日本のどこかで死んでいることになる。未遂を含めると、その数は10倍から20倍にのぼるのではないかといわれている。
かつて、交通事故で年間1万人以上もの死亡者がでたとき、「交通戦争」という言葉が口にされた。ならば、自殺者の数こそは、まさに「戦争」ではないのだろうか。
おおざっぱにいえば、5年間で15万人が死ぬことになるわけだから、まさに世界的な規模の戦争に匹敵するといっても過言ではないだろう。じわじわと、あるいは、ある日突然、自殺という観念が頭に宿り、ついにそれが決行される。まるで、ひとりひとりに突如として赤紙(召集令状)が来て、戦地に連れて行かれ、そして死んでいくかのように。
これを戦争というならば、いったい敵は誰なのだろうか?
私たちは、いったい何と戦っているのだろう?
自殺とは、自分で自分を殺すことであるが、このことは、「自分の中に、自分を殺す何かが存在している」という表現ができるのではないだろうか?
自殺の具体的なきっかけとしては、病気や経済苦などがあげられるが、病気や経済苦そのものによって死んでしまう前に、自分の中にいる何かが、自分を殺してしまうわけだ。もし、その何かが自分の中にいなければ、同じ状況に陥っても、その人は殺されることはない(死ぬことはない)。
あるいは、そのような何かが自分のなかに潜んでいても、それにうち勝てば、殺されずにすむことになる。私たちは、自分の中にいる、自分を殺そうとする敵と戦っているのだ。
もしもこの文章を読んでくださっている皆様の中で、死にたいと思う人がいたら、とりあえずこう考えていただきたい。
すなわち、自分がしようとしていることは「自殺」ではなく、「殺人」、すなわち殺されようとしているのだと。自分の中にいる敵が、あなたを殺そうとしているのだと思っていただきたい。この敵はずる賢く、いかにも自分で自分の命を断つのだと私たちを思いこませ、だまそうとする。
だが、どうか、だまされないで欲しい。あなたは“死にたい”のではない。“死にたい”と思いこまされているだけなのだ。本当のあなた自身は、決して“死にたい”などと思ってはいない。正気を取り戻し、早くそのことを見抜いて欲しい。
そして、この敵を倒すため、あなたは兵士となって、戦って欲しい。
人生というものは、なるべく平穏に過ごす方が望ましいとはいえ、ときには戦うことも必要だ。そして戦いながら、心の痛手を癒すような工夫をしていこう。そうして、自殺という人生の危機を乗り越えていこう。
人生は確かに楽なことばかりではない。死にたくなることもたくさんある。
しかし、死なずに生きていたときに開花されるであろう、そのすばらしい可能性を考えてみて欲しい。たとえばもしあなたが自殺の危機を乗り越え、人に親切にしたり、優しい言葉をかけてあげたり、なんらかの奉仕などをして人々に貢献できたら、どれほど多くの人が、その顔を笑顔で明るくさせることだろう。親切にされた人は他の人も親切にする。たったひとつの親切な行為が、時代を経るにつれて連鎖していき、ついには膨大な人々を幸せにするかもしれない。
だが、もしあなたが死んでしまったならば、あなたのおかげで明るい笑顔となったはずの数え切れない人々が存在する未来世界のひとつの枝が、永久に失われてしまうことになる。
死ぬほど辛いときこそが、真に生まれ変わり、真の幸福を見いだすターニング・ポイントなのだ。すばらしい人生という赤ちゃんは、難産の末に生まれてくるということを、どうか忘れないで欲しい。
2002年2月の独想録
2月7日 経験から美徳を学ぶ人と悪徳を増長させる人の違い
人間が、本当に自分を向上させたいと思うときというのは、何か願望があるとき、あるいは、苦しい状況から脱出したいと思うとき、大きくわけて、この2つがあるように思われる。いずれも、願望であることに違いはない。
ところで、これら両者の願望によって、人はその行く先に差がでてくるのだろうか?
前者の場合、何か願望があり、その成就に向けて努力するときには、(その願望の内容にもよるが)自分の「能力」の向上に磨きをかけるという傾向があるようだ。
一方、苦しい状況から脱出したい、苦しみを解決したいという場合、「能力向上」だけでなく、「人間性の向上」という要素が強く現れるように思う。
つまり、苦しい経験をすることにより、他者への思いやりとか、謙虚な気持ちといったことを学ぶようになるのではないかと。
前者の場合は、自分の願望獲得のために、他者への思いやりを増そうとしたり、謙虚な気持ちを養おうと心がけようとすることは、あまりないように思われる。むしろ、冷徹で高慢な気持ちを助長させてしまうことの方が多いかもしれない。
とはいえ、苦しい経験をしても、かえって人をねたんだり、いじけたり、自分の苦しみを人のせいにする人もいる。幸せな経験をしても、そのことから他者への思いやりを目覚めさせたり、謙虚になる人もいる。だから、本当にこのような問題は、一概にこうだと決めつけることはできないと思うのだが、ある程度の傾向はあるかもしれない。
これは、あまり根拠のない、私の勝手な憶測から出た数字なのだが、だいたい10人のうち1人いるかいないかくらいの人が、幸運に恵まれながら、人間性を向上させていく人である。こういう人は、本当の意味で幸せな人だ。自らの成功や幸運を誇らず、自慢せず、謙虚で、やさしく、思いやりを、ますます育てていくのだ。こういう性格だから、ますます成功と幸運を呼び寄せていくだろう。
一方、不運や苦しみに悩んでも、自らを反省することなく世の中を呪い、ますます不正直で狡猾で、傲慢で冷たくなってしまう人もいる。こういう人は、残念ながら、10人に3人くらいはいるように思われる。こういう人は、逆に幸運が訪れると、それは自分の偉大さのためだと思って高慢となり、専制的になってしまう。結局、こういう性格なので、幸運も長続きせず、苦しみや不運に突き落とされることになるだろう。本当の意味で、気の毒な人である。
そして、残りの6人くらいが、人生の経験から、そこそこ教訓を学びながら、進歩していく平均的な人ではないかと思う。
では、幸運から美徳を養う人がいるかと思えば、そこから悪徳を増長させる人もおり、苦しみから美徳を学ぶ人がいるかと思えば、それから悪徳を増長させてしまう人がいるというのは、どこに違いがあるのだろうか?
思うに、それはおそらく人生の初期の段階で、どのような人間関係を経験したかによって、決定されてしまうのではないだろうか。信頼できるよい人から影響を受けた人と、信用できない不誠実な人から影響を受けた人の違い、つまり、人間への信頼感を持つか、不信感を持つか、その違いではないかと思うのだ。何事もそうであるが、最初の経験というのは、強いインパクトとして、その人の心の中に刻印され、それがその人の生き様に、少なからぬ影響を与えるものである。
こう考えると、私たちが子供たちに接するときには、注意しなければならないと思うのだ。すなわち、私たちの接し方、その態度は、その子供の生涯に少なからぬ影響を与えるほどの、重い責任があるということを。子供に接するときには、私たちはひそかに襟を正し、ある種の緊張感を持って接しなければならない。真剣に、優しく、誠実に接し、この世界には信頼できる人間が存在するのだということを、しっかりと彼の胸に刻印してあげる必要があると思うのだ。
さらにまた、子供に限らず、感受性の豊かな人に接するときも、私たちは同様の責任を持っているという点で緊張する必要があるだろう。感受性の豊かな人は、自分と接する相手から、大きく影響を受けるからである。
人間は、関係する相手によって世界観を形成する。信頼と誠意で接すれば、彼は世界を信頼できるものと見るだろう。そして、そんな世界観からは善意と幸せが湧き上がってくる。だが、信頼できず不誠実な世界観を持たせてしまったならば、そこから湧き上がるものは、悪意と混乱と悲しみだけである。
私たちは、自分と接するすべての人の幸福に対して、想像する以上に、大きな責任を負っているのではないかと思う。
2月18日 修養の道と宗教の道
道徳や倫理といった修養の道と、宗教の道とは、どのように違うのだろうか?
宗教においても、修養の道は説かれる。すなわち、隣人を愛しなさい、生きとし生けるものに慈悲を施しなさい、淫らな行いをしてはいけません、嘘をついてはいけません……といったように、自分自身を訓練して、正しい生き方が送れるように努力することが要請される。その点では、修養の道も宗教の道も、ほとんど変わらないように思われる。
しかし、宗教の道というのは、たとえそのような修養をしているときであっても、「自分がそうしているのだ」とは思わない。「神様にそうさせていただいているのだ」と思う。あるいは「神様が自分を使って、そのようにさせているのだ」と思う。
結局のところ、宗教の道とは、自分というものを、すべて神に手渡してしまう道ではないだろうか。
私たちは、ともすると、神様を自分の中にひきづりこもうとする。つまり、神を自分の都合のいい存在として利用しようとする。だが、本当の宗教の道は反対だ。
それは逆に、自分を神様の中に捧げてしまう道である。「自分を神の都合のいい存在にする道」である。聖フランチェスコの言葉を借りれば「私をあなたの平和の道具としてお使いください」ということなのだろう。
宗教の道は、自我を抹殺する道であり、キリスト教の説く「謙虚」の美徳を追い求める道である。そして、何が起きても、「これでいいのだ、神の御心のままになさしめたまえ」と感謝できる心境を養う道である。何をやるにしても、自分がやるんではないんだ、神様がやるんだ、と思う心境への道なのだと思う。
修養の道は、(おそらく)反道徳的な人を排除し、憎み、悪を責めるであろう。しかし宗教の道は、そのようなことはしない。そのようなことが起こったのも、神がそれを認めたからだと思う。そのため、反道徳的な人を排除することも、憎むことも、責めることもしない。もちろんこのことは、反道徳的な行為を野放しにしていい、という意味ではない。反道徳的な行為をして人を苦しめているなら、それは是正していかなければならない。
だが、その是正行為の根底にあるのは、排除でも憎しみでも、責めることでもなく、深い理解に基づく愛とやさしさである。たとえその愛が峻厳という形をとらざるを得ない場合であっても、愛を根底にすることが、宗教者の道である。
真の宗教であれば、反道徳も、悪も、認めることはない。ただあるのは「未熟さ」だけだ。どんな人間(魂)であっても、最初は未熟であろう。未熟そのものは悪いことではない。未熟の結果として犯された「反道徳」や「悪」は、たとえ社会ではそう定義されようと、実はそうではなく、ひとつの学びのための失敗にすぎない。人間の成長の多くは、失敗を通してこそ促進されるものだ。本来は、失敗などという言葉も適当ではなく、それは自分の都合で勝手に決めつけたものであって、私たちのいう失敗とは、実は「学びのチャンス」以外のなにものでもない。
それゆえ、この世には「悪」も、「悪人」も、存在しない。相手が犯した「悪」を、「失敗」と見てあげること、そしてそんな相手を「悪人」ではなく、「失敗から教訓を学んで成長しようとしている人」と見ることによって、相手を善へと、また相手の魂を覚醒へと、促してあげることができるのだと思う。
2月23日 自殺という人生の危機を乗り越える
毎年、3万人を超える人たちが自らの生命を断っているというのは、驚きである。1日にしておよそ80人。20分に一人以上が、日本のどこかで死んでいることになる。未遂を含めると、その数は10倍から20倍にのぼるのではないかといわれている。
かつて、交通事故で年間1万人以上もの死亡者がでたとき、「交通戦争」という言葉が口にされた。ならば、自殺者の数こそは、まさに「戦争」ではないのだろうか。
おおざっぱにいえば、5年間で15万人が死ぬことになるわけだから、まさに世界的な規模の戦争に匹敵するといっても過言ではないだろう。じわじわと、あるいは、ある日突然、自殺という観念が頭に宿り、ついにそれが決行される。まるで、ひとりひとりに突如として赤紙(召集令状)が来て、戦地に連れて行かれ、そして死んでいくかのように。
これを戦争というならば、いったい敵は誰なのだろうか?
私たちは、いったい何と戦っているのだろう?
自殺とは、自分で自分を殺すことであるが、このことは、「自分の中に、自分を殺す何かが存在している」という表現ができるのではないだろうか?
自殺の具体的なきっかけとしては、病気や経済苦などがあげられるが、病気や経済苦そのものによって死んでしまう前に、自分の中にいる何かが、自分を殺してしまうわけだ。もし、その何かが自分の中にいなければ、同じ状況に陥っても、その人は殺されることはない(死ぬことはない)。
あるいは、そのような何かが自分のなかに潜んでいても、それにうち勝てば、殺されずにすむことになる。私たちは、自分の中にいる、自分を殺そうとする敵と戦っているのだ。
もしもこの文章を読んでくださっている皆様の中で、死にたいと思う人がいたら、とりあえずこう考えていただきたい。
すなわち、自分がしようとしていることは「自殺」ではなく、「殺人」、すなわち殺されようとしているのだと。自分の中にいる敵が、あなたを殺そうとしているのだと思っていただきたい。この敵はずる賢く、いかにも自分で自分の命を断つのだと私たちを思いこませ、だまそうとする。
だが、どうか、だまされないで欲しい。あなたは“死にたい”のではない。“死にたい”と思いこまされているだけなのだ。本当のあなた自身は、決して“死にたい”などと思ってはいない。正気を取り戻し、早くそのことを見抜いて欲しい。
そして、この敵を倒すため、あなたは兵士となって、戦って欲しい。
人生というものは、なるべく平穏に過ごす方が望ましいとはいえ、ときには戦うことも必要だ。そして戦いながら、心の痛手を癒すような工夫をしていこう。そうして、自殺という人生の危機を乗り越えていこう。
人生は確かに楽なことばかりではない。死にたくなることもたくさんある。
しかし、死なずに生きていたときに開花されるであろう、そのすばらしい可能性を考えてみて欲しい。たとえばもしあなたが自殺の危機を乗り越え、人に親切にしたり、優しい言葉をかけてあげたり、なんらかの奉仕などをして人々に貢献できたら、どれほど多くの人が、その顔を笑顔で明るくさせることだろう。親切にされた人は他の人も親切にする。たったひとつの親切な行為が、時代を経るにつれて連鎖していき、ついには膨大な人々を幸せにするかもしれない。
だが、もしあなたが死んでしまったならば、あなたのおかげで明るい笑顔となったはずの数え切れない人々が存在する未来世界のひとつの枝が、永久に失われてしまうことになる。
死ぬほど辛いときこそが、真に生まれ変わり、真の幸福を見いだすターニング・ポイントなのだ。すばらしい人生という赤ちゃんは、難産の末に生まれてくるということを、どうか忘れないで欲しい。