HOME>独想録>
2002年4月の独想録
4月5日 自分は幸せかどうかをどうやって知るか?
幸せの定義、というのは難しい。自分が本当に幸せかどうかは、どうやって知ればいいのだろう?
そのために、こんな喩えをしてみたい。
あるレストランへ入ったとしよう。もしもそのレストランが、ハンバーガーや焼きそばといったジャンクフードしかないと思い、それだけを食べて、それなりに満足していたとする。彼は自分を幸せだと思うかもしれない。だが、よく調べてみると、このレストランには、同じ値段でもっと豊かでおいしい料理のメニューがあったことがわかる。彼は、そのことをレストランから出た直後に知った。おそらく彼は、おおいに後悔するに違いない。
つまり、彼の「幸せ」は、ある種の誤解と無知の上に成り立っていたことになる。彼は、そのときは幸せを感じていたが、本当はあまり幸せなことではなかったと後で気づくのだ。
結局、彼は幸せだったのだろうか?
それとも幸せではなかったのだろうか?
また別の客がやってきたとしよう。彼は、このレストランにはハンバーガーよりもずっとおいしいメニューがあることを、最初に気づいたとしよう。
だが、所持金がないために、なにも食べることができなかった。ところが、皿洗いをすれば、お金がなくてもおいしい料理が食べられるといわれ、彼は希望に燃えて懸命に皿洗いをした。そのとき彼は幸せを感じた。
ところが、その途中、急に心臓発作を起こして死んでしまったとする。
彼は、幸せだったのだろうか?
おいしい料理が食べられなかったという意味では、幸せではなかったかもしれない。しかし彼自身は、自分が食べられなかったということさえ自覚できずに(つまりそのことを悔やむ間もなく)、「もうすぐおいしい料理が食べられるぞ」という幸せを感じたまま死んでしまったのだ。
結局、彼は幸せだったのだろうか? それとも、幸せではなかったのだろうか?
さらに、次のような状況を考えてみたい。
次の客が、そのレストランに入った。彼はおいしい料理のあることを知っていたが、所持金がまったくなく、皿洗いする元気もなかったので、お情けで、スープの残り汁をめぐんでもらった。彼はみじめに思い、幸せを感じなかった。
ところが、そのスープには滋養が溶け込んでいたので、そのおかげで、今まで自分を悩ましていた病気が治って元気になってしまった。
では、(レストランにいたときの)彼は、幸せだったのだろうか。
それとも、幸せではなかったのだろうか?
宿題をやらされている子供は幸せを感じない。だが、宿題をやらされたおかげで、将来、自分の好きな職業に就くことができたなら、宿題という苦しみを与えられたことは、幸せなことであったといえるだろう。
私たちの人生に生じるさまざまな苦しみは、こうした「宿題」の連続なのかもしれない。そのときは、苦しみ以外の何ものでもないかもしれないが、実はそれが後になって、おおいなる幸せであったと気づくこともある。
要するに、全体の時間(人生で生じる因果関係のすべて)を見渡すことのできない私たちには、眼の先に起こる出来事が、幸せであるとか、そうではないと判断する能力は、持ち合わせていないことになる。自分が幸せか、そうではないかということを知る完全な方法は、存在していないということなのだ。
そう思うと、自分は幸せだとか、そうではないということを考えること自体、実はあまり意味がないのかもしれない。
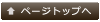
4月11日 人生がリセットできたら
ゲームをやっていて、まずい結果になったら、リセットして、最初から、あるいは自分の都合のいい場面からやり直すことができる。人生にも、この「リセット・ボタン」があればいいなと思ったことはないだろうか。もしも人生のある地点に戻って、そこからやり直すことができるとしたら、間違った進路を修正できるし、失敗を防ぐこともできる。それはなんとすばらしいことだろう。もしそんなことが可能だとしたら、地点にまで戻ってリセットしたいだろうか?
ただし、ここで考慮しなければならない大きな問題があるように思う。
それは、リセットしたいと思うような、失敗や辛い経験から学んだ教訓や智恵なども抹消されてその地点に戻るのか、それとも、そういう教訓や智恵はそのままで戻るのか、ということだ。ゲームの場合は、リセット・ボタンを教えても、失敗から学んだ知識や智恵は消えない。だからリセットしてゲームをやり直しても、今度はうまくやれる。
人生も、そのように智恵を残したままやり直せるのなら、すばらしいかもしれない。換言すれば、人間的に成長したままで過去に戻れるとしたならば。
しかしそうではなく、未熟な状態に戻ってやり直すとなると、果たしてそれはいいことなのだろうか?
人生で愚かな選択や行為をしたのは、自分が愚かで未熟だったからで、そのままの状態で過去に戻ったとしても、結局は、いずれ同じような失敗をすることになるのではないだろうか。
過去に戻ってやり直したいと思うのは、要するに、取り返しのつかない重大なことをしたからだろう。しかし、この人生において、どれほど「取り返しのつかない重大なこと」は、あるだろうか? それはただ、自分が勝手にそう思っているだけかもしれない。たとえば、面接のときに失敗して一流企業に就職できなかったとか、好きな人とささいなことで喧嘩をして結婚できなかったといった場合、もしかしたら、その企業には就職しない方がよかったのかもしれないし、その人と結婚しない方がよかったのかもしれない。案外、リセットしてやり直せたとしても、リセットする前の人生の方がよかったということも、多々あるのではないだろうか。
人生の目的というのは、一流企業に就職することでも、特定の人と結婚することでもない。そうしたことは目的ではなく手段にすぎない。目的はあくまでも、幸せになることだろう。
それゆえ、手段にさえこだわらなければ、人生の目的を達成するために、たいていのことは、いつだってやり直しができるのではないだろうか。なにも過去に戻ってリセットする必要はないかもしれない。
それに、理想的な人生を考えたら、それこそきりがないだろう。欲張れば、いくらだってリセットしたくなる。もしも本当に人生のリセット・ボタンがあったら、ほとんどの人はボタンを押してばかりいて、人生がちっとも前に進まないかもしれない。
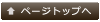
4月18日 逃げるのではなく追いかけることによって
以前、プロのバイオリニストを夢見る親子のテレビ番組を見た。父親もプロで、息子を何とかしてコンクールに優勝させようと、二人で一所懸命に練習に励んでいた。ところが、息子は曲のある部分で、同じミスを繰り返した。父親はそのたびに、いらついた口調で、「そんなことでは本番のときに必ず間違うぞ」と注意しながら指導をしていた。だが、また息子は同じ部分で間違える。そのたびに父親はいう。「何度いえばわかるんだ。そんなことでは本番のときに必ず間違うぞ」と。
そして息子は本番に臨んだ。そして、やはり同じ部分で間違いをしてしまった。
この父親は、なんとしても息子を立派なバイオリニストにしたいと思っていたのだと思うが、指導の仕方がまずかったのではないかと思った。
すなわち、父親が実際に息子にしていたことは、「本番はその部分で間違いなさい」という暗示であった。人間は、それがたとえ表面的な意識でいけないことだとわかっていても、それを意識してしまうと、暗示になって失敗してしまうようになっている。
ゴルフをする人の話だと、あっちの方にボールがいかなければいいなと思って打つと、逆にその方向に飛んでいってしまうという。
人間の心というものは、それが肯定的なものであれ、否定的なものであれ、意識すると現実になってしまうようだ。
そんな心の力を応用したのが、いわゆる「成功哲学」といった類の本で、そうした本を読むと、「自分の願望することを念じなさい。そうすればそれが実現します」などといったことが書かれている。これは確かに真理ではあるとしても、断りが必要であろう。すなわち、以上の例からわかるように、その願望が「恐怖から逃げるため」である場合、逆効果になってしまう可能性があるからだ。
たとえば、お金持ちになりたいと願う動機が、「貧乏になりたくないから」だとすると、お金持ちになるのだという信念を強くもてばもつほど、貧乏になってしまう可能性があるかもしれない。「結婚相手を見つけたい」という動機が、オールドミスになり、老後が孤独になることがイヤだから、という理由であれば、あまりいい結果をもたらさないかもしれない。どちらも恐怖が背後にあって、それから逃避するのが動機になっているからである。
そうではなく、お金持ちになりたいのであれば、そのお金によって前向きな夢を達成するためという動機、結婚相手であれば、人生を豊かに生きるためという前向きな動機に基づいた方がいいと思う。
どんなことも、恐怖が背後にあると、うまくいかないことが多い。たとえば、部下を脅して業績を伸ばそうとする場合、短期的には効果を得る場合もなくはないが、長期的には決してうまくいかない。人生は、恐怖にかられて逃げるのではなく、希望をもって、それを追いかけるように努力するときに、うまくいくようにできているからだ。
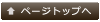
4月23日 天国にいっては味わえない二つの喜び
暗いニュースばかり目にしたり、人生の不遇に襲われたりすると、こんな世の中なんか棄てて、さっさと天国に帰り、平和に楽しく暮らしたいものだと思う人もいるのではないだろうか。人情として、そう思うのも自然なことだと思う。
しかし、天国にはすべての喜びがあるかというと、そうでもない。この地上から天国へ移行したとき、少なくても二つの「喜び」が失われてしまう。天国では、この喜びを味わうことはできないのだ。
ひとつは、苦しんでいる人が存在しなくなるわけだから、苦しむ人、悲しむ人の力になる喜び、そんな人々に奉仕したり、援助したりする喜びは、天国で味わうことはできなくなるだろう。
もうひとつは、苦しみを乗り越える喜びだ。これも天国へ行ってしまったら、決して味わうことができなくなる。天国には苦しみなどないのだから。
以上の二つの喜びは、この地上でなくては、味わうチャンスがないのだ。
いつの日か、老年まで生きて、今までの人生を振り返ったときに、そこに価値を見いだすとすれば、おそらくこの二つの喜びではないのかと思う。
老年になると、過去の人生を広い視野から大局的に見ることができるようになってくる。そのときには、当時、深刻に悩んだほとんどのことが、実際にはたいしたことがないこと、失敗なども取るに足らないものだったことを知る。怖れていたことの九十パーセント以上は起こらなかったことを知る。
また、本当につまらないことで腹を立て、ささいなことでいがみあい、貴重な友人を失ったことを苦笑する。
ちょうど、小学生にとって、宿題を忘れたとか、跳び箱に失敗してみんなの前で醜態をさらしたことなどが、人生の一大事のように思われてしまうように、私たちの人生もまた、実際にはほとんど何の心配もなく笑ってやり過ごしてよかったことばかりだったことを知る。
そして、そんな日々の中で、もっとも貴重な可能性であったことといえば、困っている人を助けるチャンス、困難を乗り越えるチャンスだったことを知るに違いない。
天国へいったら味わうことのできないこれらの喜びを、せいぜい今のうちに、できるだけ味わうようにしたいものだ。
2002年4月の独想録
4月5日 自分は幸せかどうかをどうやって知るか?
幸せの定義、というのは難しい。自分が本当に幸せかどうかは、どうやって知ればいいのだろう?
そのために、こんな喩えをしてみたい。
あるレストランへ入ったとしよう。もしもそのレストランが、ハンバーガーや焼きそばといったジャンクフードしかないと思い、それだけを食べて、それなりに満足していたとする。彼は自分を幸せだと思うかもしれない。だが、よく調べてみると、このレストランには、同じ値段でもっと豊かでおいしい料理のメニューがあったことがわかる。彼は、そのことをレストランから出た直後に知った。おそらく彼は、おおいに後悔するに違いない。
つまり、彼の「幸せ」は、ある種の誤解と無知の上に成り立っていたことになる。彼は、そのときは幸せを感じていたが、本当はあまり幸せなことではなかったと後で気づくのだ。
結局、彼は幸せだったのだろうか?
それとも幸せではなかったのだろうか?
また別の客がやってきたとしよう。彼は、このレストランにはハンバーガーよりもずっとおいしいメニューがあることを、最初に気づいたとしよう。
だが、所持金がないために、なにも食べることができなかった。ところが、皿洗いをすれば、お金がなくてもおいしい料理が食べられるといわれ、彼は希望に燃えて懸命に皿洗いをした。そのとき彼は幸せを感じた。
ところが、その途中、急に心臓発作を起こして死んでしまったとする。
彼は、幸せだったのだろうか?
おいしい料理が食べられなかったという意味では、幸せではなかったかもしれない。しかし彼自身は、自分が食べられなかったということさえ自覚できずに(つまりそのことを悔やむ間もなく)、「もうすぐおいしい料理が食べられるぞ」という幸せを感じたまま死んでしまったのだ。
結局、彼は幸せだったのだろうか? それとも、幸せではなかったのだろうか?
さらに、次のような状況を考えてみたい。
次の客が、そのレストランに入った。彼はおいしい料理のあることを知っていたが、所持金がまったくなく、皿洗いする元気もなかったので、お情けで、スープの残り汁をめぐんでもらった。彼はみじめに思い、幸せを感じなかった。
ところが、そのスープには滋養が溶け込んでいたので、そのおかげで、今まで自分を悩ましていた病気が治って元気になってしまった。
では、(レストランにいたときの)彼は、幸せだったのだろうか。
それとも、幸せではなかったのだろうか?
宿題をやらされている子供は幸せを感じない。だが、宿題をやらされたおかげで、将来、自分の好きな職業に就くことができたなら、宿題という苦しみを与えられたことは、幸せなことであったといえるだろう。
私たちの人生に生じるさまざまな苦しみは、こうした「宿題」の連続なのかもしれない。そのときは、苦しみ以外の何ものでもないかもしれないが、実はそれが後になって、おおいなる幸せであったと気づくこともある。
要するに、全体の時間(人生で生じる因果関係のすべて)を見渡すことのできない私たちには、眼の先に起こる出来事が、幸せであるとか、そうではないと判断する能力は、持ち合わせていないことになる。自分が幸せか、そうではないかということを知る完全な方法は、存在していないということなのだ。
そう思うと、自分は幸せだとか、そうではないということを考えること自体、実はあまり意味がないのかもしれない。
4月11日 人生がリセットできたら
ゲームをやっていて、まずい結果になったら、リセットして、最初から、あるいは自分の都合のいい場面からやり直すことができる。人生にも、この「リセット・ボタン」があればいいなと思ったことはないだろうか。もしも人生のある地点に戻って、そこからやり直すことができるとしたら、間違った進路を修正できるし、失敗を防ぐこともできる。それはなんとすばらしいことだろう。もしそんなことが可能だとしたら、地点にまで戻ってリセットしたいだろうか?
ただし、ここで考慮しなければならない大きな問題があるように思う。
それは、リセットしたいと思うような、失敗や辛い経験から学んだ教訓や智恵なども抹消されてその地点に戻るのか、それとも、そういう教訓や智恵はそのままで戻るのか、ということだ。ゲームの場合は、リセット・ボタンを教えても、失敗から学んだ知識や智恵は消えない。だからリセットしてゲームをやり直しても、今度はうまくやれる。
人生も、そのように智恵を残したままやり直せるのなら、すばらしいかもしれない。換言すれば、人間的に成長したままで過去に戻れるとしたならば。
しかしそうではなく、未熟な状態に戻ってやり直すとなると、果たしてそれはいいことなのだろうか?
人生で愚かな選択や行為をしたのは、自分が愚かで未熟だったからで、そのままの状態で過去に戻ったとしても、結局は、いずれ同じような失敗をすることになるのではないだろうか。
過去に戻ってやり直したいと思うのは、要するに、取り返しのつかない重大なことをしたからだろう。しかし、この人生において、どれほど「取り返しのつかない重大なこと」は、あるだろうか? それはただ、自分が勝手にそう思っているだけかもしれない。たとえば、面接のときに失敗して一流企業に就職できなかったとか、好きな人とささいなことで喧嘩をして結婚できなかったといった場合、もしかしたら、その企業には就職しない方がよかったのかもしれないし、その人と結婚しない方がよかったのかもしれない。案外、リセットしてやり直せたとしても、リセットする前の人生の方がよかったということも、多々あるのではないだろうか。
人生の目的というのは、一流企業に就職することでも、特定の人と結婚することでもない。そうしたことは目的ではなく手段にすぎない。目的はあくまでも、幸せになることだろう。
それゆえ、手段にさえこだわらなければ、人生の目的を達成するために、たいていのことは、いつだってやり直しができるのではないだろうか。なにも過去に戻ってリセットする必要はないかもしれない。
それに、理想的な人生を考えたら、それこそきりがないだろう。欲張れば、いくらだってリセットしたくなる。もしも本当に人生のリセット・ボタンがあったら、ほとんどの人はボタンを押してばかりいて、人生がちっとも前に進まないかもしれない。
4月18日 逃げるのではなく追いかけることによって
以前、プロのバイオリニストを夢見る親子のテレビ番組を見た。父親もプロで、息子を何とかしてコンクールに優勝させようと、二人で一所懸命に練習に励んでいた。ところが、息子は曲のある部分で、同じミスを繰り返した。父親はそのたびに、いらついた口調で、「そんなことでは本番のときに必ず間違うぞ」と注意しながら指導をしていた。だが、また息子は同じ部分で間違える。そのたびに父親はいう。「何度いえばわかるんだ。そんなことでは本番のときに必ず間違うぞ」と。
そして息子は本番に臨んだ。そして、やはり同じ部分で間違いをしてしまった。
この父親は、なんとしても息子を立派なバイオリニストにしたいと思っていたのだと思うが、指導の仕方がまずかったのではないかと思った。
すなわち、父親が実際に息子にしていたことは、「本番はその部分で間違いなさい」という暗示であった。人間は、それがたとえ表面的な意識でいけないことだとわかっていても、それを意識してしまうと、暗示になって失敗してしまうようになっている。
ゴルフをする人の話だと、あっちの方にボールがいかなければいいなと思って打つと、逆にその方向に飛んでいってしまうという。
人間の心というものは、それが肯定的なものであれ、否定的なものであれ、意識すると現実になってしまうようだ。
そんな心の力を応用したのが、いわゆる「成功哲学」といった類の本で、そうした本を読むと、「自分の願望することを念じなさい。そうすればそれが実現します」などといったことが書かれている。これは確かに真理ではあるとしても、断りが必要であろう。すなわち、以上の例からわかるように、その願望が「恐怖から逃げるため」である場合、逆効果になってしまう可能性があるからだ。
たとえば、お金持ちになりたいと願う動機が、「貧乏になりたくないから」だとすると、お金持ちになるのだという信念を強くもてばもつほど、貧乏になってしまう可能性があるかもしれない。「結婚相手を見つけたい」という動機が、オールドミスになり、老後が孤独になることがイヤだから、という理由であれば、あまりいい結果をもたらさないかもしれない。どちらも恐怖が背後にあって、それから逃避するのが動機になっているからである。
そうではなく、お金持ちになりたいのであれば、そのお金によって前向きな夢を達成するためという動機、結婚相手であれば、人生を豊かに生きるためという前向きな動機に基づいた方がいいと思う。
どんなことも、恐怖が背後にあると、うまくいかないことが多い。たとえば、部下を脅して業績を伸ばそうとする場合、短期的には効果を得る場合もなくはないが、長期的には決してうまくいかない。人生は、恐怖にかられて逃げるのではなく、希望をもって、それを追いかけるように努力するときに、うまくいくようにできているからだ。
4月23日 天国にいっては味わえない二つの喜び
暗いニュースばかり目にしたり、人生の不遇に襲われたりすると、こんな世の中なんか棄てて、さっさと天国に帰り、平和に楽しく暮らしたいものだと思う人もいるのではないだろうか。人情として、そう思うのも自然なことだと思う。
しかし、天国にはすべての喜びがあるかというと、そうでもない。この地上から天国へ移行したとき、少なくても二つの「喜び」が失われてしまう。天国では、この喜びを味わうことはできないのだ。
ひとつは、苦しんでいる人が存在しなくなるわけだから、苦しむ人、悲しむ人の力になる喜び、そんな人々に奉仕したり、援助したりする喜びは、天国で味わうことはできなくなるだろう。
もうひとつは、苦しみを乗り越える喜びだ。これも天国へ行ってしまったら、決して味わうことができなくなる。天国には苦しみなどないのだから。
以上の二つの喜びは、この地上でなくては、味わうチャンスがないのだ。
いつの日か、老年まで生きて、今までの人生を振り返ったときに、そこに価値を見いだすとすれば、おそらくこの二つの喜びではないのかと思う。
老年になると、過去の人生を広い視野から大局的に見ることができるようになってくる。そのときには、当時、深刻に悩んだほとんどのことが、実際にはたいしたことがないこと、失敗なども取るに足らないものだったことを知る。怖れていたことの九十パーセント以上は起こらなかったことを知る。
また、本当につまらないことで腹を立て、ささいなことでいがみあい、貴重な友人を失ったことを苦笑する。
ちょうど、小学生にとって、宿題を忘れたとか、跳び箱に失敗してみんなの前で醜態をさらしたことなどが、人生の一大事のように思われてしまうように、私たちの人生もまた、実際にはほとんど何の心配もなく笑ってやり過ごしてよかったことばかりだったことを知る。
そして、そんな日々の中で、もっとも貴重な可能性であったことといえば、困っている人を助けるチャンス、困難を乗り越えるチャンスだったことを知るに違いない。
天国へいったら味わうことのできないこれらの喜びを、せいぜい今のうちに、できるだけ味わうようにしたいものだ。