HOME>独想録>
2003年12月の独想録
12月13日 人間嫌い
かつて、こんな夢を見て目が覚めたことがある。
私は、海の近くの街に、ひとりドライブに来たらしい。そして、午前中に海を見て、午後になって、そろそろ帰ろうとしていたようである。夢はここから始まっている。私は帰る前にあの美しい海をもう一度見たいと思った(夢の中で午前中に見たことになっている海を想像した)。その海はまるで南国のように明るく美しく、そして懐かしく、そこにいると心が癒されるような思いがした。そこで車のハンドルを握り、すぐ近くにあるはずの海岸に向かおうとするのだが、なぜか道が思い出せないのだ。私は精神を集中した。おかしい。何時間か前に行き、それもすぐ近くだというのに、なぜ思い出せないのだろう? そして、あせっていたところ、目が覚めたのだった。
こんな夢を見るのも、ここ一ヶ月近く、毎日休みなく文章を書き続けていたので、神経が疲れているせいなのかもしれないと思った。実際、起きると鈍い頭痛がして、まるで鉛を注射されたような疲労を覚えた。こんなときは、誰もがそうなのかもしれないが、気分も落ち込むものである。そして、どのように落ち込むのかというと、これまでの人生において、悲しかったこと、挫折したこと、愛されなかったこと、期待していたものが失望に終わったこと……といったように、否定的な想い出と一緒なのだ。元気なときは、そういうものは心の底に沈殿して表面には現れてこない。しかし、疲れたり不調だったりすると、まるでむかしの古傷が痛むように、「心の傷」も痛み出してくる。自分自身と自分の人生が空しいものに思えてくる。そこで、何の痛みも不安もない楽園のような場所に行きたいと思うのだ。私の場合、それが美しい海という形で夢の中に現れたのかもしれない。だが、道が思い出せなかったのだ。
そこで、今日は少し休むことにした。ふと本棚を見ると、少し読みかけてそのままになっていたヘルマン・ヘッセの『郷愁』という小説があったので、それを読んだ。田舎育ちの詩人が都会にきて、青春のあらゆる楽しみを謳歌するのだが、たったひとつだけ、この主人公に恵まれないものがあった。それは「女性からの愛」だった。愛を告白してもふられたり、あるいは一歩遅くて婚約されてしまったりしたのだ。そのため、いつしか大酒のみの人間嫌いになってしまうのである。しかし、姿は醜いが心の美しい身障者に奉仕することになり、それによって心境が変化していき、その身障者が死んで故郷に戻ったとき、そこに安住の地を見いだすというストーリーである。
私は、何となく今日の夢と共通するものを感じた。決して意図的にこの本を読んだのではない。まったくの偶然だったのだ。この本は、私に何かを教えてくれようとしたのかもしれない。
人間は、おそらく「愛されない」という経験ほど、心につきささっていつまでも癒されることのない傷はないのかもしれない。私の友人でこんなことをいった人がいた。両親と妹の四人で一緒の部屋に布団を敷いて寝ていた子供のとき、彼女の布団は一番外側で、玄関に一番近かったのだそうだ。すると彼女は子供心に、「もしも泥棒が入ってきたら、私が一番最初に殺されるかもしれない。きっと私のことなんか、どうだっていいんだ」と感じたという。もちろん、親はそんなつもりで彼女を玄関に近い場所に寝かせたのではないだろうし、こんなことを子供が考えているなどとは予想もできなかったに違いない。だが、彼女はそう感じて寂しい思いをしたという。そして、それが30歳を過ぎた今になっても、忘れられない記憶として残っているという。
私に関していえば、3歳のときに父の離婚のために突然、母がいなくなった。次に二番目の母親がきた(この女性と父は正式に結婚していたのかどうかはわからないが、とにかく一年ほど一緒に住んだ)。ところが、この母親も一夜にして突然いなくなり、二度と会うことはなかった。その後、しばらく祖母が東北の田舎から私の世話をするためにきて、半年くらい一緒に生活したが、朝起きたとき、祖母が姿を消していた。東京の生活は嫌になったと叔父にもらしたところ、叔父が早朝に祖母を田舎にこっそりと連れ去ってしまったのである。このように、私は自分のことを愛してくれる女性を失う経験、それも、何の予告もなく突然にいなくなるという経験をしてきた。このような経験からくる心の空しさといったものを、心の奥に抱えているのかもしれない。
しかし、私は大酒のみにも人間嫌いにもなっていない。たぶん、私は人間嫌いではないと思う。ただ、私のライフスタイルを客観的に評価するならば、人間とつきあうよりも、自然とつきあっている時間の方が圧倒的に多いのも確かである。ヘッセの小説では、主人公が嵐の夜に、「あの野原に立っている一本の樹は、今頃、どうしているのだろう」と心配になってベッドから起き、その樹の様子を見に行ったシーンが書かれている。この気持ちが私にはよくわかる。もしかしたら私は、本当は人間嫌いなのかもしれない。人間と会っていて孤独を感じることはあるが、自然の中にいて孤独を感じたことはない。私の家の周りには、湖も森も、広大な田園を見渡す土手も、川もある。唯一、海がないのが惜しまれるだけだ。海があればどんなにいいだろうかと思う。いずれにしろ、こうした環境が、私には大きな慰めとなっている。要するに、こういうタイプの人間は、実際に作品を残すかどうかは別として、「詩人」のタイプなのだろう。
けれども、人間嫌いの主人公は、最後には真実の愛の奉仕に目覚めて安住の地を見いだした。人間嫌いというのは、本当に人間嫌いなのだろうか? それとも、それは人一倍、愛を求めている人の仮の呼び名にすぎないのではないだろうか?
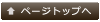
12月16日 日野原重明先生との面会
昨日、『生き方上手』などのベストセラーで有名な聖路加国際病院理事長の日野原重明先生にお会いしてきた。私の新刊『ブーバーに学ぶ』(日本教文社)の推薦文を書いて下さったお礼に伺ったのである。今度の本は、人と人との関係性と世界の平和を追求したユダヤ人哲学者マルティン・ブーバーを解説したものであるが、早くから日野原先生はブーバーを高く評価されており、著書や講演でしばしばブーバーをご紹介されてきた。それで今回、日野原先生に推薦文をお願いしたところ、快く引き受けていただいたしだいである。
約束の午後1時30分、出版社の編集者と友人の三人で、築地の聖路加国際病院に行った。都心の一等地にそびえたつ巨大な病院の5階にある理事長室を訪れると、日野原先生の日常を紹介するというテレビ局のスタッフが、理事長室の扉から中の様子をずっと撮影していた。理事長室といっても、非常にこじんまりしており、さまざまな書類でおおわれたテーブルを前にして、ソファーに日野原先生が座っておられた。面会の順番がくるまで、その理事長室を医師をはじめさまざまな人がひっきりなしに出入りしており、その間を縫うように日野原先生は電話をかけておられたようだ。まさに「超多忙」というのは、このことなのだと思った。
部屋に入ると、「どうですか、できましたか、ブーバーの本は?」と声をかけて下さった。とても92歳とは思えないほどハリのある声と表情であった。もちろん、耳が遠いということもまったくない。そうして15分くらい本に関する話をしたのだが、驚いたのは、「よくできましたね」といったようなねぎらいの抽象的な応対ではなく、この本を売るためにどうしたらいいかといった、きわめて具体的なアドバイスを下さったことである。「私の紹介だと伝えなさい」といって、いくつかの出版社を紹介してくださり、その出版社が出している印刷物の書評に載せてもらうように指示をいただいた。また、講演のときにもこの本の紹介をしてあげるといって下さった。
この場に漂っていた雰囲気は、和気あいあいとした、ホンワカとしたムードというよりは、まるで社長が部下に対して事業の指示を出しているような、張りつめた緊張感が漂っていた。
これは意外なことであった。私はおそらく、つきなみな精神的な励ましをいただいて帰るのだろうなと思っていたのだが、日野原先生は、とにかくこの本を売ってあげようという具体的で現実的な支援をして下さったからである。先生の目は非常にシャープで、ある意味ではクールであった。『生き方上手』といった本から感じられる、温厚でにこやかなお人柄とは、また違った側面をお持ちであった(さもなければ、医師や大病院の運営などできないであろう)。
しかし、本当に人を助けてあげようという気持ちがあるなら、このようなアドバイスをするのだなと思った。口先だけなら、いくらだって相手を喜ばせるような甘い言葉を投げかけることはできる。もちろん、そうした励ましも大切かもしれないが、本当に相手が何を求めているのか、それを知って、それにふさわしいアドバイスをすることが、本当に相手のことを思いやる愛なのだといえよう。
事実、私は今回の本だけは、とにかく売りたいという希望が強い。もちろん、今までの本だって売れることを希望していたわけであるが、今回の場合は、何としてもブーバーという思想家を日本に定着させたい。ブーバーの思想こそが、この現代社会にとってもっとも重要であると信じているからである。
日野原先生も「ブーバーは二十世紀最高の哲学者だ」といわれるが、私もそう思う。ブーバーの思想は、まさに哲学や宗教がめざす究極レベルにまで達していると思う。世の中にはたくさんのすぐれた思想家や宗教家がおり、多くの思想を学ぶことは意義がある。だがしかし、どのような思想を学ぼうと、ブーバーだけは取りこぼしてはならない。私はそう信じている。
2003年12月の独想録
12月13日 人間嫌い
かつて、こんな夢を見て目が覚めたことがある。
私は、海の近くの街に、ひとりドライブに来たらしい。そして、午前中に海を見て、午後になって、そろそろ帰ろうとしていたようである。夢はここから始まっている。私は帰る前にあの美しい海をもう一度見たいと思った(夢の中で午前中に見たことになっている海を想像した)。その海はまるで南国のように明るく美しく、そして懐かしく、そこにいると心が癒されるような思いがした。そこで車のハンドルを握り、すぐ近くにあるはずの海岸に向かおうとするのだが、なぜか道が思い出せないのだ。私は精神を集中した。おかしい。何時間か前に行き、それもすぐ近くだというのに、なぜ思い出せないのだろう? そして、あせっていたところ、目が覚めたのだった。
こんな夢を見るのも、ここ一ヶ月近く、毎日休みなく文章を書き続けていたので、神経が疲れているせいなのかもしれないと思った。実際、起きると鈍い頭痛がして、まるで鉛を注射されたような疲労を覚えた。こんなときは、誰もがそうなのかもしれないが、気分も落ち込むものである。そして、どのように落ち込むのかというと、これまでの人生において、悲しかったこと、挫折したこと、愛されなかったこと、期待していたものが失望に終わったこと……といったように、否定的な想い出と一緒なのだ。元気なときは、そういうものは心の底に沈殿して表面には現れてこない。しかし、疲れたり不調だったりすると、まるでむかしの古傷が痛むように、「心の傷」も痛み出してくる。自分自身と自分の人生が空しいものに思えてくる。そこで、何の痛みも不安もない楽園のような場所に行きたいと思うのだ。私の場合、それが美しい海という形で夢の中に現れたのかもしれない。だが、道が思い出せなかったのだ。
そこで、今日は少し休むことにした。ふと本棚を見ると、少し読みかけてそのままになっていたヘルマン・ヘッセの『郷愁』という小説があったので、それを読んだ。田舎育ちの詩人が都会にきて、青春のあらゆる楽しみを謳歌するのだが、たったひとつだけ、この主人公に恵まれないものがあった。それは「女性からの愛」だった。愛を告白してもふられたり、あるいは一歩遅くて婚約されてしまったりしたのだ。そのため、いつしか大酒のみの人間嫌いになってしまうのである。しかし、姿は醜いが心の美しい身障者に奉仕することになり、それによって心境が変化していき、その身障者が死んで故郷に戻ったとき、そこに安住の地を見いだすというストーリーである。
私は、何となく今日の夢と共通するものを感じた。決して意図的にこの本を読んだのではない。まったくの偶然だったのだ。この本は、私に何かを教えてくれようとしたのかもしれない。
人間は、おそらく「愛されない」という経験ほど、心につきささっていつまでも癒されることのない傷はないのかもしれない。私の友人でこんなことをいった人がいた。両親と妹の四人で一緒の部屋に布団を敷いて寝ていた子供のとき、彼女の布団は一番外側で、玄関に一番近かったのだそうだ。すると彼女は子供心に、「もしも泥棒が入ってきたら、私が一番最初に殺されるかもしれない。きっと私のことなんか、どうだっていいんだ」と感じたという。もちろん、親はそんなつもりで彼女を玄関に近い場所に寝かせたのではないだろうし、こんなことを子供が考えているなどとは予想もできなかったに違いない。だが、彼女はそう感じて寂しい思いをしたという。そして、それが30歳を過ぎた今になっても、忘れられない記憶として残っているという。
私に関していえば、3歳のときに父の離婚のために突然、母がいなくなった。次に二番目の母親がきた(この女性と父は正式に結婚していたのかどうかはわからないが、とにかく一年ほど一緒に住んだ)。ところが、この母親も一夜にして突然いなくなり、二度と会うことはなかった。その後、しばらく祖母が東北の田舎から私の世話をするためにきて、半年くらい一緒に生活したが、朝起きたとき、祖母が姿を消していた。東京の生活は嫌になったと叔父にもらしたところ、叔父が早朝に祖母を田舎にこっそりと連れ去ってしまったのである。このように、私は自分のことを愛してくれる女性を失う経験、それも、何の予告もなく突然にいなくなるという経験をしてきた。このような経験からくる心の空しさといったものを、心の奥に抱えているのかもしれない。
しかし、私は大酒のみにも人間嫌いにもなっていない。たぶん、私は人間嫌いではないと思う。ただ、私のライフスタイルを客観的に評価するならば、人間とつきあうよりも、自然とつきあっている時間の方が圧倒的に多いのも確かである。ヘッセの小説では、主人公が嵐の夜に、「あの野原に立っている一本の樹は、今頃、どうしているのだろう」と心配になってベッドから起き、その樹の様子を見に行ったシーンが書かれている。この気持ちが私にはよくわかる。もしかしたら私は、本当は人間嫌いなのかもしれない。人間と会っていて孤独を感じることはあるが、自然の中にいて孤独を感じたことはない。私の家の周りには、湖も森も、広大な田園を見渡す土手も、川もある。唯一、海がないのが惜しまれるだけだ。海があればどんなにいいだろうかと思う。いずれにしろ、こうした環境が、私には大きな慰めとなっている。要するに、こういうタイプの人間は、実際に作品を残すかどうかは別として、「詩人」のタイプなのだろう。
けれども、人間嫌いの主人公は、最後には真実の愛の奉仕に目覚めて安住の地を見いだした。人間嫌いというのは、本当に人間嫌いなのだろうか? それとも、それは人一倍、愛を求めている人の仮の呼び名にすぎないのではないだろうか?
12月16日 日野原重明先生との面会
昨日、『生き方上手』などのベストセラーで有名な聖路加国際病院理事長の日野原重明先生にお会いしてきた。私の新刊『ブーバーに学ぶ』(日本教文社)の推薦文を書いて下さったお礼に伺ったのである。今度の本は、人と人との関係性と世界の平和を追求したユダヤ人哲学者マルティン・ブーバーを解説したものであるが、早くから日野原先生はブーバーを高く評価されており、著書や講演でしばしばブーバーをご紹介されてきた。それで今回、日野原先生に推薦文をお願いしたところ、快く引き受けていただいたしだいである。
約束の午後1時30分、出版社の編集者と友人の三人で、築地の聖路加国際病院に行った。都心の一等地にそびえたつ巨大な病院の5階にある理事長室を訪れると、日野原先生の日常を紹介するというテレビ局のスタッフが、理事長室の扉から中の様子をずっと撮影していた。理事長室といっても、非常にこじんまりしており、さまざまな書類でおおわれたテーブルを前にして、ソファーに日野原先生が座っておられた。面会の順番がくるまで、その理事長室を医師をはじめさまざまな人がひっきりなしに出入りしており、その間を縫うように日野原先生は電話をかけておられたようだ。まさに「超多忙」というのは、このことなのだと思った。
部屋に入ると、「どうですか、できましたか、ブーバーの本は?」と声をかけて下さった。とても92歳とは思えないほどハリのある声と表情であった。もちろん、耳が遠いということもまったくない。そうして15分くらい本に関する話をしたのだが、驚いたのは、「よくできましたね」といったようなねぎらいの抽象的な応対ではなく、この本を売るためにどうしたらいいかといった、きわめて具体的なアドバイスを下さったことである。「私の紹介だと伝えなさい」といって、いくつかの出版社を紹介してくださり、その出版社が出している印刷物の書評に載せてもらうように指示をいただいた。また、講演のときにもこの本の紹介をしてあげるといって下さった。
この場に漂っていた雰囲気は、和気あいあいとした、ホンワカとしたムードというよりは、まるで社長が部下に対して事業の指示を出しているような、張りつめた緊張感が漂っていた。
これは意外なことであった。私はおそらく、つきなみな精神的な励ましをいただいて帰るのだろうなと思っていたのだが、日野原先生は、とにかくこの本を売ってあげようという具体的で現実的な支援をして下さったからである。先生の目は非常にシャープで、ある意味ではクールであった。『生き方上手』といった本から感じられる、温厚でにこやかなお人柄とは、また違った側面をお持ちであった(さもなければ、医師や大病院の運営などできないであろう)。
しかし、本当に人を助けてあげようという気持ちがあるなら、このようなアドバイスをするのだなと思った。口先だけなら、いくらだって相手を喜ばせるような甘い言葉を投げかけることはできる。もちろん、そうした励ましも大切かもしれないが、本当に相手が何を求めているのか、それを知って、それにふさわしいアドバイスをすることが、本当に相手のことを思いやる愛なのだといえよう。
事実、私は今回の本だけは、とにかく売りたいという希望が強い。もちろん、今までの本だって売れることを希望していたわけであるが、今回の場合は、何としてもブーバーという思想家を日本に定着させたい。ブーバーの思想こそが、この現代社会にとってもっとも重要であると信じているからである。
日野原先生も「ブーバーは二十世紀最高の哲学者だ」といわれるが、私もそう思う。ブーバーの思想は、まさに哲学や宗教がめざす究極レベルにまで達していると思う。世の中にはたくさんのすぐれた思想家や宗教家がおり、多くの思想を学ぶことは意義がある。だがしかし、どのような思想を学ぼうと、ブーバーだけは取りこぼしてはならない。私はそう信じている。