HOME>独想録>
2006年5月の独想録
5月2日 体罰と人生を真剣に生きること
戸塚ヨットスクールの戸塚校長が刑期を終えて社会に復帰し、これまで通り仕事を続けていくニュースが報道されていた。体罰を肯定する過酷なヨット訓練を通して、社会的に不適応な若者を矯正する施設で、訓練中に2人の死者、2人の行方不明(たぶん、死んでしまったのだろう)を出して逮捕されたとき、世の中は「体罰は是か非か」といった論議が盛んに行われた。
私自身は、できれば体罰などしない方がよいが、何が何でも体罰はダメだとも思っていない。むしろ、今の若い人たちのだらしない現状(すべての若者ではない。私の感じでは、すばらしく立派な若者と、どうしようもなくだらしない若者との“格差”が広がっているように思う)を考えるなら、けっこう体罰というのは有効かもしれないと思うときもある。
何事もそうだが、「これは是か非か」といったことを決めるときには、根本的にめざすものは何かをしっかりと決めておかなければならない。
たとえば、「苦痛を与えるのはいけない」というのが根本的な目的なら、体罰は認められないだろう。癌患者に副作用の強い抗ガン剤を投与することもできない。子供に宿題(という苦痛)を与えるのもいけないということになる。
しかし、癌患者が副作用の強い抗ガン剤をあえて服用するのも、もっとひどい苦痛を回避するためであるともいえるし、子供に宿題を与えるのも、「宿題をしないことによって将来待っている苦痛」を回避させるためにあるのだともいえる。こうなると、「苦痛を与えるのはいけない」といっても、それは「何の苦痛なのか」というところまで踏み込んで定義していかなければならない。
問題は、すべて目的にある。
仮に体罰そのものを目的とした体罰であれば、あるいは自分の個人的な腹いせの対象として暴力をふるうのであれば、そのような体罰が認められるはずもない。
しかし、相手の成長のために貢献するという目的をもっているなら認められるかもしれない。ただし、体罰にはリスクがつきまとう。そのリスクの大きさを考慮したとき、もっと他にリスクの少ない方法があるなら、そちらを採用した方がよい。つまり、体罰よりリスクの少ない方法が他にあるのに、あえて体罰を用いるというのは、認めることはできないということになる。効果が同じなら、副作用の強い薬よりも副作用の少ない薬を用いるというのは、まっとうな判断である。
では、体罰以外の方法しかない、という状態はいかなる状態なのだろうか?
「飴とムチ」という言葉がある。動物などを調教する際には、飴つまりエサという快楽、ムチという痛み(体罰)を与える。なぜなら、動物とは会話ができないからだ。また、動物の意思に反して人間の都合のいいように操ろうとするためだ。
同じことは人間にも当てはまる。もし会話ができない相手、要するに理屈で説明しても理解してもらえないような相手であるか、あるいは相手の意思を無視して自分の思うように操ろうとする場合は、「飴」か、さもなければ「ムチ」しかない。現実には、相手を思うように操れるほど魅力的な「飴」を用意することは難しいから、結局は「ムチ」しかないことになる。
戸塚ヨットスクールも、営利を目的とした団体だから、ある意味では「自分の利益のために生徒を操ろうとして体罰をふるった」といえなくもない。だが、その学校に入るのは自由であり、あらかじめそのような指導が行われることを理解した上でその学校に入ったわけであるから、必ずしも「自分の利益のために体罰を与えた」という非難は通用しない。
では、理屈で説得して理解できない相手というのは、いるのだろうか?
残念ながら、そういう人は世の中にたくさんいる。犯罪者は、犯罪はよくないことは知っているはずだ。人を殺してはいけないことも頭では知っているはずだ。交通ルールを守らなければいけないこともみんな知っている。もし世の中の人が理屈で説得して理解してもらえるのであれば、そもそも世の中に殺人も犯罪も、交通事故も存在しないことになる。すべての子供たちは、テレビゲームを必ずするのと同じくらい宿題も必ずするようになるだろう。
しかし、実際にはそうはならないから、国は収監や死刑という「体罰」を与えなければならない(死刑は少し意味が違うかもしれないが)。
戸塚ヨットスクールに入らなければならない若者は、たとえば不良であったり、仕事も何もせずぶらぶらしているような若者であろう。彼らに理屈が通用するくらいなら、あのような場所に連れてこられることはなかったであろう。
不良であったり、仕事もせず家に引きこもってゲームばかりしている生活の果てに待っているものが、決してバラ色の未来ではないことは明白である。やがては監獄に行くか、生活保護を受けてぎりぎりの生活をし一人寂しく老いて死んでいくか、自殺していっきに人生を終わらせるか、たいていそうした選択肢しか待っていない。一念発起して生き方を改めない限りは。
そのような悲惨な人生に比べれば、戸塚ヨットスクールの厳しい生活の方がずっとマシであるといえるかもしれない。
以上のような極端な若者たちのみならず、今の若い人たち全般によく見られる社会常識や礼儀の欠如、ちょっと嫌なことがあると投げ出してしまう忍耐力のなさ、甘え、わがまま・・・、こういった性格で幸せな未来が待ち受けている可能性も、極めて低いといえる。親の財産で一生仕事せずに暮らしていけるなら大丈夫かもしれないが、こういう性格では仕事などうまくいくはずもなく、他の人ともうまくいかず、そのため結局は職を転々としたあげく孤立して経済的にもいきずまってしまうだろう。
それと、人生で「幸せだな」と感じる瞬間というものは、金に飽かせて欲しいモノを手に入れることにあるのではなく、辛い状況に耐えながらそれを自分の力と周囲の人たちの温かい支援によってついには見事に乗り越え克服できたときなのである。
幸か不幸か、今の若い人(若い人だけではないが)は、「必死になる」「真剣になる」という機会がない。なので人生の真の幸福を味わうことができない。「必死」というのは文字通り「必ず死ぬような状況」であり、「真剣」というのは、木刀ではなく真剣を使って相手と勝負するということだ。つまり、刃が触れたら死んでしまうのだ。今の生活で、それほど真剣になるということがあるだろうか?
だが、そのように真剣に生きたときこそ、人は生きることの尊さ、人の優しさの有り難さ、人生の美や愛、気高さといったものが感じられるようになる。そして、そのようなものを感じたことがないという人は、たとえいかにお金があり何不自由なくモノに溢れた生活をしていたとしても「不幸」なのである。そういう人生の真のスピリチュアルな側面を知らず、「そのままでいいんだよ」「自分を愛せばいいんだよ」などと甘えを助長させてきた「スピリチュアル本」にも、責任の一端があるかもしれない。
戦時中、親はいつ子供に召集令状が来るかという思いをもちながら生活していた。召集令状とは要するに子供の死刑宣告だ。そんな緊迫した状況で毎日を生きていた。だから、子供に対する愛情も今とは違うものだったと思う。いつ別れることになるかわからないのだから、親として精一杯のことをしてやろうと「必死」であり「真剣」だったに違いない。今日のように、子供に金やモノを(エサのように)与えておけば親として事が足りているなどという考えはなかったはずだ。第一、当時はモノなんてなかったから、親は精一杯の精神的な愛(つまり本当の愛)を注いだ。結局、子供が求めているのは、そんな真剣な精神的な愛なのだが、それは皮肉なことに、戦争という、もっとも忌むべき過酷な状況の中で発揮されることがあったのかもしれない。
人は学ばなければならない。人生というものは、辛いことがあってもじっと我慢し努力していればそれなりに乗り越えられるということ、お金やモノよりも心を大切にする気持ち、恥ずかしいことはたとえそれがどんなに利益をもたらすことであっても手を出さない凛とした姿勢、人から何かしてもらったら「ありがとう」、悪いことをしたら「ごめんなさい」という最低限の常識、花鳥風月を愛する感性、仕事に対するプロフェッショナルな取り組み・・・こういったことを学ばなければ、それは真に成熟した人間であるとはいえない。
そのためには、人生を、毎日を、真剣に生きるようにしなければならない。
そんな生活は、さぞかしストレスがたまるに違いないって?
そんなことはない。ほとんどの場合、ストレスなどは甘やかされて育ち、それが当たり前だと錯覚してしまっている軟弱な心が作りだす文明病にすぎない。生きるか死ぬか必死に生きている野生動物の中にストレス性潰瘍で胃に穴があいたなんて聞いたことがない。それどころか、真剣に生きている動物たちは引き締まった身体をもち、バランス感覚ある心をもち、バイタリティ溢れ、美しくて、イキイキしているではないか。
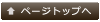
5月17日 病気という「免罪符」
かつて、私がカウンセリングをしていた患者さんの中に、“自称”鬱病患者がいた。
“自称”というのは、その初老の女性は、あちこち病院を回ったものの、どこも自分を鬱病と診断してくれないのが不満で、あくまでも自分は鬱病なんだと言い張っていたからだ。
なぜ自分を鬱病患者だと思っていたのか、というより、なぜ自分に鬱病患者のレッテルを貼りたかったのかというと、「病人」と認めてもらえれば、周囲に対して自分の我が儘が通ると考えていたからである。すなわち、「自分は病気なんだから、少しくらい家事をしなくたって許される、自分は病気なんだから、夫も子供も自分に優しくして当然だ……」と。
病人と健常者との境界は、しばしばあいまいだ。特に精神的な領域はさらにこの境界があいまいになる。誰だって気分がふさぎ込むこともあるが、これが鬱病なのかそうでないのかは、判断が難しい。単に人生が自分の思うようにいかずに落ち込んでいるだけなのか、それとも正真正銘の鬱病なのか、よくわからないことが多い。
悲劇なのは、本当に鬱病なのに、「甘えている、根性が足りない、怠けている……」といった言葉を浴びせかけ、ますます病人を追いつめてしまうことだ。がいして、鬱病患者は責任感が人一倍強く、本当に精一杯頑張っている。それなのに「まだダメだ、まだ努力が足りない」と思っていることが多い。
しかし、中には本当に「甘え、根性の不足、怠け心」のために気分がふさぎ込んでいる人もいる(人間というものは暇すぎると倦怠感や鬱っぽい気持ちになってしまうものだ)。そういう人が「鬱病」と診断され、仕事をしたり勉強をしたりしなくてもいい「免罪符」を手に入れ、いつまでもブラブラしているといったこともある。
また、こうした「病気であれば嫌なことをしなくてもいい」、「病気だと人から大切にしてもらえる」という思いが、本人も自覚できない無意識の領域で働いてしまい、そのために、いつまでも慢性的な病気が治らないといったこともある。本人は病気に苦しんでおり、早く治りたいという気持ちに嘘はないのだが、心の深いところで、治ることを拒絶しているのである。
カウンセラーをしていると、慢性的な不調に長期に渡って悩んでいる人は、経済的にゆとりがある人が多いように感じることがある。厳密な統計をとったわけではないからはっきりとしたことはいえない。けれど、病気であることが許される環境に生きていることと、長期に渡って病気に苦しんでいることの間には、もちろんすべてそうだというわけではないが、何らかの関係があるように思えてならない。「病気になれば自分の願いが通る」などという思いを、意識レベルでも無意識レベルでも徹底的にぬぐい去ってしまう厳しさが、病気を克服する上においては必要な場合もある。優しさだけが人を癒すのではない。
もしも長いこと慢性病に悩んでいるなら、思いきって逃げ道のない過酷な状況に、捨て身の覚悟で飛び込んでみるといいかもしれない。逃げ道があってはダメだ。逃げようとする心が病気を作り続けてきたのだから。いっさいの逃げ道をなくし、乗り越えるか、さもなければ死あるのみというくらい、決死の覚悟で辛いことに身を捧げてみると、案外、簡単に治ってしまうかもしれない。鬱なんか、いっぺんで吹き飛んでしまうかもしれない。
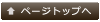
5月29日 日本的感性
私の住んでいるところには、たんぼや畑、森や林がたくさんあるので、季節感をとてもよく感じることができる。初夏の夕刻、外から聞こえているのは、数多くのカエルたちの合唱だ。真夏になるとセミの、秋になると虫たちの合唱が聞こえる。小鳥の声はいつも聞くことができる。
ところで、大脳生理学の研究によれば、カエルや虫の声を、メッセージ性が込められた風情ある音としてとらえるのは、どうも日本人だけらしい。外国人はそうした音を「雑音」ととらえる。同じアジアでも、中国や韓国などは、やはり雑音ととらえるようだ。
雑音だから、カエルや虫の声を「やかましい」と感じるかもしれない。それはある種の「公害」のようなもので、あまりにもやかましいと、カエルや虫を駆除してしまうといった、そんなことが起きてしまうかもしれない。
日本人は、カエルや虫の声を単なる雑音としか耳に入らない外国人を不思議に思うが、外国人からすれば、カエルや虫の声を雑音ではなく、音楽のような心地よいものとしてとらえる日本人の感性は、理解しがたいのかもしれない。
だが、環境を大切にしようという意識が世界的に広まっているが、カエルや虫の声を「雑音」にしか聞こえない外国人と、それを音楽のように聞く日本人とでは、おそらく「環境」に対する考え方には大きなズレがあるように思われる。
外国人にとって、自然環境とは、あくまでも人間を活かす限りにおいて大切であるに過ぎないのかもしれない。つまり、環境を破壊し続けると人間が生きていけなくなるから、(仕方なく)環境を大切にする……という発想なのかもしれない。
しかし、日本人の自然環境に対する意識は、そういったものではない。自然が人間にとって有用だろうとそうでなかろうと、日本人は自然に対して畏敬の念をもち、無条件でそれを大切にしようとする心がある。日本人の自然に対する美的センスは抜群で、カラフルな春や夏の景色に美を感じるだけでなく、モノトーンで枯れ果てた冬の景色にも、そこに美を感じ取ることができる。それはしばしば、「わび」、「さび」、「もののあわれ」といった言葉で表現される。
「わび」、「さび」、「もののあわれ」といった言葉に相当する英語はないようだ。「わび」という言葉を辞書で調べてみると「elegant rusticity(優雅な素朴)」だとか「austerity beauty(質素な美)」といった英訳が出てくる。意味としては近いけれども、「わび」という感覚は、「優雅な素朴」だとか「質素な美」といった表現以上のものがある。
結局、その感覚は言葉や理屈で説明できるものではなく、感覚的につかむしかないのだろうが、人生の味わい、人と人との触れあい、さらには宗教的な真実といったものの究極は、言葉や理屈で説明できるものではなく、「わび」、「さび」、「もののあわれ」としか表現しようのない何かなのだと思う。
禅の大家、鈴木大拙は、日本独特の宗教的感性を「日本的霊性」と呼んだが、「霊性」であれ「感性」であれ、そうした微妙な感覚や直感というものは、何も日本人の特徴をあらわしたものというだけでなく、あらゆる人類、人間存在が、その究極的な霊的真理に到達する上でなくてはならない資質なのであると、私は考えている。
2006年5月の独想録
5月2日 体罰と人生を真剣に生きること
戸塚ヨットスクールの戸塚校長が刑期を終えて社会に復帰し、これまで通り仕事を続けていくニュースが報道されていた。体罰を肯定する過酷なヨット訓練を通して、社会的に不適応な若者を矯正する施設で、訓練中に2人の死者、2人の行方不明(たぶん、死んでしまったのだろう)を出して逮捕されたとき、世の中は「体罰は是か非か」といった論議が盛んに行われた。
私自身は、できれば体罰などしない方がよいが、何が何でも体罰はダメだとも思っていない。むしろ、今の若い人たちのだらしない現状(すべての若者ではない。私の感じでは、すばらしく立派な若者と、どうしようもなくだらしない若者との“格差”が広がっているように思う)を考えるなら、けっこう体罰というのは有効かもしれないと思うときもある。
何事もそうだが、「これは是か非か」といったことを決めるときには、根本的にめざすものは何かをしっかりと決めておかなければならない。
たとえば、「苦痛を与えるのはいけない」というのが根本的な目的なら、体罰は認められないだろう。癌患者に副作用の強い抗ガン剤を投与することもできない。子供に宿題(という苦痛)を与えるのもいけないということになる。
しかし、癌患者が副作用の強い抗ガン剤をあえて服用するのも、もっとひどい苦痛を回避するためであるともいえるし、子供に宿題を与えるのも、「宿題をしないことによって将来待っている苦痛」を回避させるためにあるのだともいえる。こうなると、「苦痛を与えるのはいけない」といっても、それは「何の苦痛なのか」というところまで踏み込んで定義していかなければならない。
問題は、すべて目的にある。
仮に体罰そのものを目的とした体罰であれば、あるいは自分の個人的な腹いせの対象として暴力をふるうのであれば、そのような体罰が認められるはずもない。
しかし、相手の成長のために貢献するという目的をもっているなら認められるかもしれない。ただし、体罰にはリスクがつきまとう。そのリスクの大きさを考慮したとき、もっと他にリスクの少ない方法があるなら、そちらを採用した方がよい。つまり、体罰よりリスクの少ない方法が他にあるのに、あえて体罰を用いるというのは、認めることはできないということになる。効果が同じなら、副作用の強い薬よりも副作用の少ない薬を用いるというのは、まっとうな判断である。
では、体罰以外の方法しかない、という状態はいかなる状態なのだろうか?
「飴とムチ」という言葉がある。動物などを調教する際には、飴つまりエサという快楽、ムチという痛み(体罰)を与える。なぜなら、動物とは会話ができないからだ。また、動物の意思に反して人間の都合のいいように操ろうとするためだ。
同じことは人間にも当てはまる。もし会話ができない相手、要するに理屈で説明しても理解してもらえないような相手であるか、あるいは相手の意思を無視して自分の思うように操ろうとする場合は、「飴」か、さもなければ「ムチ」しかない。現実には、相手を思うように操れるほど魅力的な「飴」を用意することは難しいから、結局は「ムチ」しかないことになる。
戸塚ヨットスクールも、営利を目的とした団体だから、ある意味では「自分の利益のために生徒を操ろうとして体罰をふるった」といえなくもない。だが、その学校に入るのは自由であり、あらかじめそのような指導が行われることを理解した上でその学校に入ったわけであるから、必ずしも「自分の利益のために体罰を与えた」という非難は通用しない。
では、理屈で説得して理解できない相手というのは、いるのだろうか?
残念ながら、そういう人は世の中にたくさんいる。犯罪者は、犯罪はよくないことは知っているはずだ。人を殺してはいけないことも頭では知っているはずだ。交通ルールを守らなければいけないこともみんな知っている。もし世の中の人が理屈で説得して理解してもらえるのであれば、そもそも世の中に殺人も犯罪も、交通事故も存在しないことになる。すべての子供たちは、テレビゲームを必ずするのと同じくらい宿題も必ずするようになるだろう。
しかし、実際にはそうはならないから、国は収監や死刑という「体罰」を与えなければならない(死刑は少し意味が違うかもしれないが)。
戸塚ヨットスクールに入らなければならない若者は、たとえば不良であったり、仕事も何もせずぶらぶらしているような若者であろう。彼らに理屈が通用するくらいなら、あのような場所に連れてこられることはなかったであろう。
不良であったり、仕事もせず家に引きこもってゲームばかりしている生活の果てに待っているものが、決してバラ色の未来ではないことは明白である。やがては監獄に行くか、生活保護を受けてぎりぎりの生活をし一人寂しく老いて死んでいくか、自殺していっきに人生を終わらせるか、たいていそうした選択肢しか待っていない。一念発起して生き方を改めない限りは。
そのような悲惨な人生に比べれば、戸塚ヨットスクールの厳しい生活の方がずっとマシであるといえるかもしれない。
以上のような極端な若者たちのみならず、今の若い人たち全般によく見られる社会常識や礼儀の欠如、ちょっと嫌なことがあると投げ出してしまう忍耐力のなさ、甘え、わがまま・・・、こういった性格で幸せな未来が待ち受けている可能性も、極めて低いといえる。親の財産で一生仕事せずに暮らしていけるなら大丈夫かもしれないが、こういう性格では仕事などうまくいくはずもなく、他の人ともうまくいかず、そのため結局は職を転々としたあげく孤立して経済的にもいきずまってしまうだろう。
それと、人生で「幸せだな」と感じる瞬間というものは、金に飽かせて欲しいモノを手に入れることにあるのではなく、辛い状況に耐えながらそれを自分の力と周囲の人たちの温かい支援によってついには見事に乗り越え克服できたときなのである。
幸か不幸か、今の若い人(若い人だけではないが)は、「必死になる」「真剣になる」という機会がない。なので人生の真の幸福を味わうことができない。「必死」というのは文字通り「必ず死ぬような状況」であり、「真剣」というのは、木刀ではなく真剣を使って相手と勝負するということだ。つまり、刃が触れたら死んでしまうのだ。今の生活で、それほど真剣になるということがあるだろうか?
だが、そのように真剣に生きたときこそ、人は生きることの尊さ、人の優しさの有り難さ、人生の美や愛、気高さといったものが感じられるようになる。そして、そのようなものを感じたことがないという人は、たとえいかにお金があり何不自由なくモノに溢れた生活をしていたとしても「不幸」なのである。そういう人生の真のスピリチュアルな側面を知らず、「そのままでいいんだよ」「自分を愛せばいいんだよ」などと甘えを助長させてきた「スピリチュアル本」にも、責任の一端があるかもしれない。
戦時中、親はいつ子供に召集令状が来るかという思いをもちながら生活していた。召集令状とは要するに子供の死刑宣告だ。そんな緊迫した状況で毎日を生きていた。だから、子供に対する愛情も今とは違うものだったと思う。いつ別れることになるかわからないのだから、親として精一杯のことをしてやろうと「必死」であり「真剣」だったに違いない。今日のように、子供に金やモノを(エサのように)与えておけば親として事が足りているなどという考えはなかったはずだ。第一、当時はモノなんてなかったから、親は精一杯の精神的な愛(つまり本当の愛)を注いだ。結局、子供が求めているのは、そんな真剣な精神的な愛なのだが、それは皮肉なことに、戦争という、もっとも忌むべき過酷な状況の中で発揮されることがあったのかもしれない。
人は学ばなければならない。人生というものは、辛いことがあってもじっと我慢し努力していればそれなりに乗り越えられるということ、お金やモノよりも心を大切にする気持ち、恥ずかしいことはたとえそれがどんなに利益をもたらすことであっても手を出さない凛とした姿勢、人から何かしてもらったら「ありがとう」、悪いことをしたら「ごめんなさい」という最低限の常識、花鳥風月を愛する感性、仕事に対するプロフェッショナルな取り組み・・・こういったことを学ばなければ、それは真に成熟した人間であるとはいえない。
そのためには、人生を、毎日を、真剣に生きるようにしなければならない。
そんな生活は、さぞかしストレスがたまるに違いないって?
そんなことはない。ほとんどの場合、ストレスなどは甘やかされて育ち、それが当たり前だと錯覚してしまっている軟弱な心が作りだす文明病にすぎない。生きるか死ぬか必死に生きている野生動物の中にストレス性潰瘍で胃に穴があいたなんて聞いたことがない。それどころか、真剣に生きている動物たちは引き締まった身体をもち、バランス感覚ある心をもち、バイタリティ溢れ、美しくて、イキイキしているではないか。
5月17日 病気という「免罪符」
かつて、私がカウンセリングをしていた患者さんの中に、“自称”鬱病患者がいた。
“自称”というのは、その初老の女性は、あちこち病院を回ったものの、どこも自分を鬱病と診断してくれないのが不満で、あくまでも自分は鬱病なんだと言い張っていたからだ。
なぜ自分を鬱病患者だと思っていたのか、というより、なぜ自分に鬱病患者のレッテルを貼りたかったのかというと、「病人」と認めてもらえれば、周囲に対して自分の我が儘が通ると考えていたからである。すなわち、「自分は病気なんだから、少しくらい家事をしなくたって許される、自分は病気なんだから、夫も子供も自分に優しくして当然だ……」と。
病人と健常者との境界は、しばしばあいまいだ。特に精神的な領域はさらにこの境界があいまいになる。誰だって気分がふさぎ込むこともあるが、これが鬱病なのかそうでないのかは、判断が難しい。単に人生が自分の思うようにいかずに落ち込んでいるだけなのか、それとも正真正銘の鬱病なのか、よくわからないことが多い。
悲劇なのは、本当に鬱病なのに、「甘えている、根性が足りない、怠けている……」といった言葉を浴びせかけ、ますます病人を追いつめてしまうことだ。がいして、鬱病患者は責任感が人一倍強く、本当に精一杯頑張っている。それなのに「まだダメだ、まだ努力が足りない」と思っていることが多い。
しかし、中には本当に「甘え、根性の不足、怠け心」のために気分がふさぎ込んでいる人もいる(人間というものは暇すぎると倦怠感や鬱っぽい気持ちになってしまうものだ)。そういう人が「鬱病」と診断され、仕事をしたり勉強をしたりしなくてもいい「免罪符」を手に入れ、いつまでもブラブラしているといったこともある。
また、こうした「病気であれば嫌なことをしなくてもいい」、「病気だと人から大切にしてもらえる」という思いが、本人も自覚できない無意識の領域で働いてしまい、そのために、いつまでも慢性的な病気が治らないといったこともある。本人は病気に苦しんでおり、早く治りたいという気持ちに嘘はないのだが、心の深いところで、治ることを拒絶しているのである。
カウンセラーをしていると、慢性的な不調に長期に渡って悩んでいる人は、経済的にゆとりがある人が多いように感じることがある。厳密な統計をとったわけではないからはっきりとしたことはいえない。けれど、病気であることが許される環境に生きていることと、長期に渡って病気に苦しんでいることの間には、もちろんすべてそうだというわけではないが、何らかの関係があるように思えてならない。「病気になれば自分の願いが通る」などという思いを、意識レベルでも無意識レベルでも徹底的にぬぐい去ってしまう厳しさが、病気を克服する上においては必要な場合もある。優しさだけが人を癒すのではない。
もしも長いこと慢性病に悩んでいるなら、思いきって逃げ道のない過酷な状況に、捨て身の覚悟で飛び込んでみるといいかもしれない。逃げ道があってはダメだ。逃げようとする心が病気を作り続けてきたのだから。いっさいの逃げ道をなくし、乗り越えるか、さもなければ死あるのみというくらい、決死の覚悟で辛いことに身を捧げてみると、案外、簡単に治ってしまうかもしれない。鬱なんか、いっぺんで吹き飛んでしまうかもしれない。
5月29日 日本的感性
私の住んでいるところには、たんぼや畑、森や林がたくさんあるので、季節感をとてもよく感じることができる。初夏の夕刻、外から聞こえているのは、数多くのカエルたちの合唱だ。真夏になるとセミの、秋になると虫たちの合唱が聞こえる。小鳥の声はいつも聞くことができる。
ところで、大脳生理学の研究によれば、カエルや虫の声を、メッセージ性が込められた風情ある音としてとらえるのは、どうも日本人だけらしい。外国人はそうした音を「雑音」ととらえる。同じアジアでも、中国や韓国などは、やはり雑音ととらえるようだ。
雑音だから、カエルや虫の声を「やかましい」と感じるかもしれない。それはある種の「公害」のようなもので、あまりにもやかましいと、カエルや虫を駆除してしまうといった、そんなことが起きてしまうかもしれない。
日本人は、カエルや虫の声を単なる雑音としか耳に入らない外国人を不思議に思うが、外国人からすれば、カエルや虫の声を雑音ではなく、音楽のような心地よいものとしてとらえる日本人の感性は、理解しがたいのかもしれない。
だが、環境を大切にしようという意識が世界的に広まっているが、カエルや虫の声を「雑音」にしか聞こえない外国人と、それを音楽のように聞く日本人とでは、おそらく「環境」に対する考え方には大きなズレがあるように思われる。
外国人にとって、自然環境とは、あくまでも人間を活かす限りにおいて大切であるに過ぎないのかもしれない。つまり、環境を破壊し続けると人間が生きていけなくなるから、(仕方なく)環境を大切にする……という発想なのかもしれない。
しかし、日本人の自然環境に対する意識は、そういったものではない。自然が人間にとって有用だろうとそうでなかろうと、日本人は自然に対して畏敬の念をもち、無条件でそれを大切にしようとする心がある。日本人の自然に対する美的センスは抜群で、カラフルな春や夏の景色に美を感じるだけでなく、モノトーンで枯れ果てた冬の景色にも、そこに美を感じ取ることができる。それはしばしば、「わび」、「さび」、「もののあわれ」といった言葉で表現される。
「わび」、「さび」、「もののあわれ」といった言葉に相当する英語はないようだ。「わび」という言葉を辞書で調べてみると「elegant rusticity(優雅な素朴)」だとか「austerity beauty(質素な美)」といった英訳が出てくる。意味としては近いけれども、「わび」という感覚は、「優雅な素朴」だとか「質素な美」といった表現以上のものがある。
結局、その感覚は言葉や理屈で説明できるものではなく、感覚的につかむしかないのだろうが、人生の味わい、人と人との触れあい、さらには宗教的な真実といったものの究極は、言葉や理屈で説明できるものではなく、「わび」、「さび」、「もののあわれ」としか表現しようのない何かなのだと思う。
禅の大家、鈴木大拙は、日本独特の宗教的感性を「日本的霊性」と呼んだが、「霊性」であれ「感性」であれ、そうした微妙な感覚や直感というものは、何も日本人の特徴をあらわしたものというだけでなく、あらゆる人類、人間存在が、その究極的な霊的真理に到達する上でなくてはならない資質なのであると、私は考えている。