HOME>独想録>
2009年12月の独想録
12月1日 山田一雄先生の想い出
もう25年以上も前の、私が二十代の頃の話。
今日ほどマーラーの音楽がポピュラーでなかった当時、好きで好きでたまらなかったその音楽を聴くために、コンサート会場によく足を運んだ。そして、日本人としてただひとりともいえるマーラーのスペシャリスト、山田一雄の指揮による演奏に、どれほど感銘を受けたことか(ちなみに山田一雄はマーラーの弟子であるハンス・プリングスハイムに指揮法を教わっているので、マーラーからすれば孫弟子ということになる)。
山田一雄の演奏は、細かい技術をあれこれ問うよりも、音楽そのものに生命を宿す、実にダイナミックで熱いものだった。音楽というより、マーラーの魂が現前したかのような、とても言葉では表現できない迫力と感動があった。当時、70歳を越えていたが、青年のように若々しく情熱的な指揮ぶりは、本当にカッコよかった。
そんな山田先生は、私にとっては天上の人であり、英雄であり、神様のような存在で、ただ静かに客席から、ステージの上で神がかったように指揮しているその姿を、憧れに満ちたまなざしで遠巻きに見ているだけであった。
ところが、山田先生はマーラー協会の理事長をしており、その協会に入った私は、山田先生と近くで接することができるようになった。休日に会員のみんなで新宿御苑を散歩したこともあったし、コンサートの帰りなど、数人で楽屋に行くと、その後できさくに喫茶店に行って話などをしてくれたのである。
私はおそるおそる、山田先生の隣に座り、緊張しながら、勇気を出して、いくつか質問をしてみた。あの偉大な英雄であり、神様が、いま、自分の隣に座っているのだ!
どんな質問をしたかは、覚えていない。本当にくだらない質問をしたと思うが、山田先生は私のどんな馬鹿な質問に対しても、決して軽蔑したり馬鹿にするような態度はされず、真剣に誠実に、それでいてユーモアを交えながら、親切に答えてくださったのである。
そのことが、若かった私のハートを、どれほど熱くしてくれたことだろう。今でもそのときのことを思い出すと涙が溢れてくるほどだ。
私はそのとき、たとえどんなにくだらない馬鹿らしい質問であっても、その人が真剣に尋ねてくるならば、決して馬鹿にしたり軽蔑したりせず、真剣に誠実に対応しなければならないということを学んだ。もしも今の私が、そのような人間であると評価していただけるなら、それは山田先生から教わったものだ。
そして、さらに嬉しかったことは、どこの馬の骨かわからない若者である私のことなど、覚えてくれるはずがないと思っていたのだが、次に協会の会合があって、山田先生とお会いしたとき、先生が「やあ、斉藤君、元気だったかい?」と、私の名前を呼んで声をかけてくださったことである。私はもう、思いを寄せていた女性から「あなたが好きです」と愛の告白を受けたかのように嬉しくて、頭が真っ白になった。
山田先生は、最高の芸術家であり、当時も今も、もっともっと高い評価が与えられるべきである。山田先生の残された数少ないマーラーの録音、たとえば交響曲第2番(タワーレコード&ビクター)や交響曲第8番(ソニーミュージック)などをいま耳にしても、そのマーラー解釈のすばらしさにはあらためて驚かされる。当時の評論家や聴衆は、まだそこまで耳が肥えていなかったのかもしれない。今日、テクニック的にはすばらしいが、いまひとつ感動を覚えない演奏が少なくないのに対して、山田先生の演奏を聴くと、「これぞ音楽だ!」と思う。なにをするにしても、そこに情熱や生命力がなければならないという思いにさせられる。
私はそんな山田先生の演奏から、人生に対する基本的な生きる姿勢を学んだような気がした。すなわち、テクニックも大切だが、もっと大切なものはテクニックを超えたところにあるということ、どんなことも魂の底から情熱をもって体当たりしていくこと、そこに生命の力を宿すようにすること・・・、そんなことを学んだ。
そういった芸術家としてのすばらしさは置いておくとしても、山田先生は、人間的にも本当にすばらしかった。70歳を過ぎても若い奥様を連れておられ、ダンディで若々しく、やさしく、あたたかく、こだわりなく、ユーモアに溢れ、誰に対しても誠実で、とにかく魅力的な人だった。
あれから四半世紀たっていい歳になってしまった私は、今更ながらあらためて山田先生の偉大さや魅力がわかるようになってきたように思う。先生は1991年に心臓の病で急逝されたが、私にとって山田先生は、私の人間性を育ててくれた、いつまでも心のなかで生きている恩人なのだ。
私も晩年は、山田先生のようになりたいと、そんなことを思い始めているこの頃である。
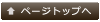
12月19日 人生のどん底で支えてくれるもの
生きていれば、多くの人は「人生のどん底」と思われる経験をするだろう。
人生のどん底とは、文字通り、これ以上はひどくなりようがないと思えるような経験である。仕事だけがうまくいかない、人間関係だけがうまくいかない、というのではない。こういうときは、仕事もうまくいかない、そのためお金にも困る。そのうえ、家族だとかその他の人間関係もうまくいかない。争ったり、裏切られたり、冷たくされたり、意地悪されたり、助けを求めても無視されたり、自分の辛さを理解してもらえず、去っていかれたりする。さらにそのうえ、健康を害したりなど、二重にも三重にも苦しみが襲いかかり、途方に暮れ、なぜ人生はこんなにもひどい仕打ちをするのか、いったい自分が何をしたのかと叫びたくなるような、絶望と悲しみと不条理に打ちひしがれる。そして自暴自棄になったり、いっそのこと死んでしまいたくなる。
そんなとき、自分を支えてくれるものは、いったい何なのだろうか?
信仰だろうか?
確かに、まったく揺るぎない強い信仰を持っている人なら、そうした苦難も神の試練と受け入れることができるかもしれない。しかしそこまで強い信仰心を持っている人は、そう多くないのではないだろうか。
ならば、いったい何が、人生のどん底において支えてくれるのだろうか?
私が思うに、それには二つある(もちろん、他にもたくさんあるだろうが)。
ひとつは、誰かから優しくされた経験である。
それは何も、おおげさなものである必要はない。ほんのちょっとした優しい励ましの言葉だとか、ちょっとした親切といったものが、その人の心にずっと残り、人生のどん底におかれたときに、その人を支えることになる。
今年の9月に亡くなった父も、東北の田舎から東京に出てきて人生のどん底を味わったとき、身内の人からかけてもらった優しい言葉に支えられたといっていた。
また、母も、そんな父と結婚してどん底の生活をしていたとき、父の友人が家に訪ねてきて「奥さん、悪いときばかりは続きませんよ」と言われ、その言葉がすごくありがたかったと、後に人並みな生活が送れるようになったときに回想していた。
優しい言葉や親切な行為が、たとえそれがいかにささいなものであっても、人を救うことだってあるのだ。人生のどん底で自殺するしかないと思い詰めた人を、自殺から引き留めることだってきっとあるのだ。優しい言葉や小さな親切の威力は、われわれが想像するよりおそらくずっと強力である。それがついには連鎖的に拡大していき、世界を救うことになるかもしれないのだ。
そして、人生のどん底において支えになってくれるもうひとつのものは、「自分は人に親切にしてきた」という思いではないかと思う。
人生のどん底を経験すると、自分という存在が取るに足らないものに思え、世の中から必要とされていない、まったく価値のない無意味な存在に思われてくる。しかしそんななかで、多少なりとも人に親切にしてきた、優しくしてきたなら、その想い出が、人生のどん底を救ってくれることになるかもしれない。
すなわち、「今はこんなにも惨めな状態であるが、それでも私は、少しは人のためにいいことをしてきた」という、ある種の誇りのようなものを持つことができ、どんな惨めな状態におかれても、自分自身の価値を自分で認めることができるだろうからだ。自分自身を、価値も意味もない存在であるとは思わないでいられるのである。人生のどん底のときには、自分自身を信頼できる心、自分自身を尊敬できる心ほど、強い支えはない。そのような心さえあれば、いかなる人生のどん底であろうと、必ずはい上がることができると思う。
人から優しさや親切を受けられるかどうかは、運などもあり、すべての人がそうした想い出を持てるとは限らない。しかし、人に優しくしたり親切にすることは、そのつもりならだれだってできる。
もちろん、「どん底のとき」に備えるために、人に親切にしたり優しくしたりするわけではないし、そのような行為は無条件で打算なく純粋に行われるべきではあるにしても、そのような行為を重ねていけば、いざとなったときに自分が救われるのは確かなのである。まさに「情けは人のためならず」ということなのだろう。
2009年12月の独想録
12月1日 山田一雄先生の想い出
もう25年以上も前の、私が二十代の頃の話。
今日ほどマーラーの音楽がポピュラーでなかった当時、好きで好きでたまらなかったその音楽を聴くために、コンサート会場によく足を運んだ。そして、日本人としてただひとりともいえるマーラーのスペシャリスト、山田一雄の指揮による演奏に、どれほど感銘を受けたことか(ちなみに山田一雄はマーラーの弟子であるハンス・プリングスハイムに指揮法を教わっているので、マーラーからすれば孫弟子ということになる)。
山田一雄の演奏は、細かい技術をあれこれ問うよりも、音楽そのものに生命を宿す、実にダイナミックで熱いものだった。音楽というより、マーラーの魂が現前したかのような、とても言葉では表現できない迫力と感動があった。当時、70歳を越えていたが、青年のように若々しく情熱的な指揮ぶりは、本当にカッコよかった。
そんな山田先生は、私にとっては天上の人であり、英雄であり、神様のような存在で、ただ静かに客席から、ステージの上で神がかったように指揮しているその姿を、憧れに満ちたまなざしで遠巻きに見ているだけであった。
ところが、山田先生はマーラー協会の理事長をしており、その協会に入った私は、山田先生と近くで接することができるようになった。休日に会員のみんなで新宿御苑を散歩したこともあったし、コンサートの帰りなど、数人で楽屋に行くと、その後できさくに喫茶店に行って話などをしてくれたのである。
私はおそるおそる、山田先生の隣に座り、緊張しながら、勇気を出して、いくつか質問をしてみた。あの偉大な英雄であり、神様が、いま、自分の隣に座っているのだ!
どんな質問をしたかは、覚えていない。本当にくだらない質問をしたと思うが、山田先生は私のどんな馬鹿な質問に対しても、決して軽蔑したり馬鹿にするような態度はされず、真剣に誠実に、それでいてユーモアを交えながら、親切に答えてくださったのである。
そのことが、若かった私のハートを、どれほど熱くしてくれたことだろう。今でもそのときのことを思い出すと涙が溢れてくるほどだ。
私はそのとき、たとえどんなにくだらない馬鹿らしい質問であっても、その人が真剣に尋ねてくるならば、決して馬鹿にしたり軽蔑したりせず、真剣に誠実に対応しなければならないということを学んだ。もしも今の私が、そのような人間であると評価していただけるなら、それは山田先生から教わったものだ。
そして、さらに嬉しかったことは、どこの馬の骨かわからない若者である私のことなど、覚えてくれるはずがないと思っていたのだが、次に協会の会合があって、山田先生とお会いしたとき、先生が「やあ、斉藤君、元気だったかい?」と、私の名前を呼んで声をかけてくださったことである。私はもう、思いを寄せていた女性から「あなたが好きです」と愛の告白を受けたかのように嬉しくて、頭が真っ白になった。
山田先生は、最高の芸術家であり、当時も今も、もっともっと高い評価が与えられるべきである。山田先生の残された数少ないマーラーの録音、たとえば交響曲第2番(タワーレコード&ビクター)や交響曲第8番(ソニーミュージック)などをいま耳にしても、そのマーラー解釈のすばらしさにはあらためて驚かされる。当時の評論家や聴衆は、まだそこまで耳が肥えていなかったのかもしれない。今日、テクニック的にはすばらしいが、いまひとつ感動を覚えない演奏が少なくないのに対して、山田先生の演奏を聴くと、「これぞ音楽だ!」と思う。なにをするにしても、そこに情熱や生命力がなければならないという思いにさせられる。
私はそんな山田先生の演奏から、人生に対する基本的な生きる姿勢を学んだような気がした。すなわち、テクニックも大切だが、もっと大切なものはテクニックを超えたところにあるということ、どんなことも魂の底から情熱をもって体当たりしていくこと、そこに生命の力を宿すようにすること・・・、そんなことを学んだ。
そういった芸術家としてのすばらしさは置いておくとしても、山田先生は、人間的にも本当にすばらしかった。70歳を過ぎても若い奥様を連れておられ、ダンディで若々しく、やさしく、あたたかく、こだわりなく、ユーモアに溢れ、誰に対しても誠実で、とにかく魅力的な人だった。
あれから四半世紀たっていい歳になってしまった私は、今更ながらあらためて山田先生の偉大さや魅力がわかるようになってきたように思う。先生は1991年に心臓の病で急逝されたが、私にとって山田先生は、私の人間性を育ててくれた、いつまでも心のなかで生きている恩人なのだ。
私も晩年は、山田先生のようになりたいと、そんなことを思い始めているこの頃である。
12月19日 人生のどん底で支えてくれるもの
生きていれば、多くの人は「人生のどん底」と思われる経験をするだろう。
人生のどん底とは、文字通り、これ以上はひどくなりようがないと思えるような経験である。仕事だけがうまくいかない、人間関係だけがうまくいかない、というのではない。こういうときは、仕事もうまくいかない、そのためお金にも困る。そのうえ、家族だとかその他の人間関係もうまくいかない。争ったり、裏切られたり、冷たくされたり、意地悪されたり、助けを求めても無視されたり、自分の辛さを理解してもらえず、去っていかれたりする。さらにそのうえ、健康を害したりなど、二重にも三重にも苦しみが襲いかかり、途方に暮れ、なぜ人生はこんなにもひどい仕打ちをするのか、いったい自分が何をしたのかと叫びたくなるような、絶望と悲しみと不条理に打ちひしがれる。そして自暴自棄になったり、いっそのこと死んでしまいたくなる。
そんなとき、自分を支えてくれるものは、いったい何なのだろうか?
信仰だろうか?
確かに、まったく揺るぎない強い信仰を持っている人なら、そうした苦難も神の試練と受け入れることができるかもしれない。しかしそこまで強い信仰心を持っている人は、そう多くないのではないだろうか。
ならば、いったい何が、人生のどん底において支えてくれるのだろうか?
私が思うに、それには二つある(もちろん、他にもたくさんあるだろうが)。
ひとつは、誰かから優しくされた経験である。
それは何も、おおげさなものである必要はない。ほんのちょっとした優しい励ましの言葉だとか、ちょっとした親切といったものが、その人の心にずっと残り、人生のどん底におかれたときに、その人を支えることになる。
今年の9月に亡くなった父も、東北の田舎から東京に出てきて人生のどん底を味わったとき、身内の人からかけてもらった優しい言葉に支えられたといっていた。
また、母も、そんな父と結婚してどん底の生活をしていたとき、父の友人が家に訪ねてきて「奥さん、悪いときばかりは続きませんよ」と言われ、その言葉がすごくありがたかったと、後に人並みな生活が送れるようになったときに回想していた。
優しい言葉や親切な行為が、たとえそれがいかにささいなものであっても、人を救うことだってあるのだ。人生のどん底で自殺するしかないと思い詰めた人を、自殺から引き留めることだってきっとあるのだ。優しい言葉や小さな親切の威力は、われわれが想像するよりおそらくずっと強力である。それがついには連鎖的に拡大していき、世界を救うことになるかもしれないのだ。
そして、人生のどん底において支えになってくれるもうひとつのものは、「自分は人に親切にしてきた」という思いではないかと思う。
人生のどん底を経験すると、自分という存在が取るに足らないものに思え、世の中から必要とされていない、まったく価値のない無意味な存在に思われてくる。しかしそんななかで、多少なりとも人に親切にしてきた、優しくしてきたなら、その想い出が、人生のどん底を救ってくれることになるかもしれない。
すなわち、「今はこんなにも惨めな状態であるが、それでも私は、少しは人のためにいいことをしてきた」という、ある種の誇りのようなものを持つことができ、どんな惨めな状態におかれても、自分自身の価値を自分で認めることができるだろうからだ。自分自身を、価値も意味もない存在であるとは思わないでいられるのである。人生のどん底のときには、自分自身を信頼できる心、自分自身を尊敬できる心ほど、強い支えはない。そのような心さえあれば、いかなる人生のどん底であろうと、必ずはい上がることができると思う。
人から優しさや親切を受けられるかどうかは、運などもあり、すべての人がそうした想い出を持てるとは限らない。しかし、人に優しくしたり親切にすることは、そのつもりならだれだってできる。
もちろん、「どん底のとき」に備えるために、人に親切にしたり優しくしたりするわけではないし、そのような行為は無条件で打算なく純粋に行われるべきではあるにしても、そのような行為を重ねていけば、いざとなったときに自分が救われるのは確かなのである。まさに「情けは人のためならず」ということなのだろう。