HOME>独想録>
2004年4月の独想録
4月14日 看護師の学校に不合格になった女性
看護師の学校の入試に落ち、そのショックで身体的に具合が悪くなってしまった若い女性がカウンセリングにやってきた。友達のほとんどは合格しており、そのため彼女は、かつて仲のよかった友達からも遠ざかり、ひとり阻害されたように引きこもってしまっていた。彼女の合格は自分も周囲も確信していたのに、意外な結果であった。
「(合格した)友達は、私の前で、平気で自分たちがしている看護の勉強の話ばかりするんです。どうしてそんなことができるんだろう……」
そういって、彼女は「無神経な友達」の仕打ちに涙を浮かべた。
「辛いですね。ところで、あなたはどうして、看護師になりたいと思ったのですか?」
「かつて入院していたとき、そこの看護師さんと深く触れあえた感覚をもったんです。それは本当にすばらしい喜びでした。そのとき思ったんです。私の道は看護師しかないんだって」
「それは、看護師をめざす動機として大変にすばらしいものですね。患者さんとの触れあいを大切にする看護師さんですね。きっとあなたは、すばらしい看護師さんになれるでしょう」
「でも、試験に落ちてしまったんです……」
「あきらめるつもりですか?」
「いいえ……」と、彼女は首を横に振った。その強い動機は、決して色あせていなかった。ただ、自信を失いかけている様子だった。
「一年くらい出遅れたからといって、長い人生、何のハンデにもなりません。それよりどうなんでしょう。看護師にとって、もっとも大切な資質とは、何だと思いますか?」
「?……」
「薬の知識だとか、介護の技術といったことなんか、少し勉強すればすぐに覚えられます。看護師にとって一番求められるのは、患者さんの痛みや苦しみを共感して理解することのできる資質なんです。患者さんは、そういう看護師を求めているのだし、そういう看護師に出会えたときにこそ、癒されるのではないでしょうか」
「ええ、そうですね……」
「そのためには、実際に自分が痛み、苦しむ経験をもたなければ、他者の痛みや苦しみに共感することは難しいでしょう。あなたは今、とても苦しみ、身も心も痛んでいます。それは、看護師に必要な共感や理解という資質を養うための“学び”であるといえないでしょうか? 友達は合格して看護の勉強をしているかもしれませんが、あなたもまた、目には見えない“学校”で、非常に大切な勉強をしているのではないでしょうか」
彼女は、真剣に耳を傾けていた。
「神様は、あなたのすばらしい看護師への動機と意欲を賞賛し、あなたの夢を叶えてすばらしい看護師にさせるために、あえて“不合格”という“恩恵”を与えたのかもしれません。もしあのまま合格していたら、あなたの友達のように、不合格になった人を前に平気で授業の話をするような、無神経で冷たい看護師になっていたかもしれません。そんな看護師が、患者さんを癒せるはずはないのです。だから、本当に“合格”したのは、友達なんかではなく、あなたなのですよ。あなたこそ“選ばれた”のです」
彼女の目に生気が宿ってきた。
「ええ、そうですね。でも、まだ気持ちは辛いです。どうしたらいいんでしょう?」
「自らの辛い経験を通して他者への共感と理解が深まるのですから、逃げたりしないで、じっくりとその辛さを受け止めて下さい。おおいに苦しみましょう。今は苦しみ痛むのがよい時なのです。看護師となったら、忙しくて痛み苦しんでいる暇なんてなくなりますからね。つまり、共感と理解の資質を身につけるのは、今しかないのです」
そうして、明るい希望に満ちて彼女は帰っていった。
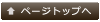
4月15日 私は死ぬのですか? 教えてください
癌の末期で余命も長くないと診断されていた、その中年の女性患者さんは、回復への希望を捨てず、民間療法などあらゆる手段を尽くしてこられた。とはいえ、じわじわと状態は思わしくない方向へ進んでいき、本人もうすうす絶望的な未来が否定できないようになってきた。医師や私たち医療スタッフは、治りたいという患者さんの希望を否定する権利はないし、実際、わずかとはいえ奇跡的に回復するような人もいないわけではないので、悲観的な見解を述べるのは控えてきた。
「私は死ぬのですか? 教えてください」
患者さんは、穏やかでありながら、どこか怨念のようなものがこめられた口調で私に尋ねた。
「はっきりとしたことはいえません。しかし、人間は誰だって、いつ死んでもおかしくないのですから、死ぬことを覚悟しておくことは、必要かもしれません」
患者さんは泣きながらいった。
「私は、これからどう生きたらいいのか、わからないのです。どこまでも生(治ること)をめざして生きるべきなのか、それとも死をめざして生きるべきなのかと……。私は知りたいんです。治る可能性は、あるのですか?」
私は責められているような気持ちになり、返答に困った。医師からは、だいたいどの程度の病状で、余命もどのくらいなのか教えてもらっているが、私は医師ではないので、私の口からそれを告げることはできないし、仮に告げることが許されていたとしても、果たして告げただろうか? 告げるべきなのか? 告げるべきではないのか? どちらが患者さんにとっていいことなのだろうか?
私は迷う心を抑えながら、次のような、やや問題からそらしたことを述べた。
「二つの可能性があるわけです。もし、治ることをめざして、つまり、そのために家族や愛する人と楽しい想い出を残すとか、今までやりたかったことをするといった“死の準備”ができないで、そのうえ治らずに死んでしまったら、まるで書きかけの途中で終わってしまった未完の小説のように、あなたの人生は終わってしまうでしょう。しかし、もし余命を死の準備に費やすならば、あなたの人生という小説は完結され、残された人は、見事に完結されて“作品”となったあなたの人生を、いつまでも心の中にとどめておくことになるでしょう」
患者さんの目からは、尽きることなく、涙が頬を伝わって流れていた。
私は、どのようにいえば、患者さんの、この悲痛な気持ちを楽にしてあげられるのか、必死で考えたけれども、結局、何もいい言葉が出せないで、沈黙だけが部屋を満たすだけになった。そして次の予定があるために部屋を出なければならなくなった。私のカウンセリングはまさに「未完」に終わってしまった。
「ありがとうございました」と、扉をあける私の背後から言葉が聞こえた。
振り返ると、笑みを浮かべながら、悲しい目をした患者さんの顔が見えた。私はなんだか、闇の中にひとり置き去りにされたような気持ちになった。
2004年4月の独想録
4月14日 看護師の学校に不合格になった女性
看護師の学校の入試に落ち、そのショックで身体的に具合が悪くなってしまった若い女性がカウンセリングにやってきた。友達のほとんどは合格しており、そのため彼女は、かつて仲のよかった友達からも遠ざかり、ひとり阻害されたように引きこもってしまっていた。彼女の合格は自分も周囲も確信していたのに、意外な結果であった。
「(合格した)友達は、私の前で、平気で自分たちがしている看護の勉強の話ばかりするんです。どうしてそんなことができるんだろう……」
そういって、彼女は「無神経な友達」の仕打ちに涙を浮かべた。
「辛いですね。ところで、あなたはどうして、看護師になりたいと思ったのですか?」
「かつて入院していたとき、そこの看護師さんと深く触れあえた感覚をもったんです。それは本当にすばらしい喜びでした。そのとき思ったんです。私の道は看護師しかないんだって」
「それは、看護師をめざす動機として大変にすばらしいものですね。患者さんとの触れあいを大切にする看護師さんですね。きっとあなたは、すばらしい看護師さんになれるでしょう」
「でも、試験に落ちてしまったんです……」
「あきらめるつもりですか?」
「いいえ……」と、彼女は首を横に振った。その強い動機は、決して色あせていなかった。ただ、自信を失いかけている様子だった。
「一年くらい出遅れたからといって、長い人生、何のハンデにもなりません。それよりどうなんでしょう。看護師にとって、もっとも大切な資質とは、何だと思いますか?」
「?……」
「薬の知識だとか、介護の技術といったことなんか、少し勉強すればすぐに覚えられます。看護師にとって一番求められるのは、患者さんの痛みや苦しみを共感して理解することのできる資質なんです。患者さんは、そういう看護師を求めているのだし、そういう看護師に出会えたときにこそ、癒されるのではないでしょうか」
「ええ、そうですね……」
「そのためには、実際に自分が痛み、苦しむ経験をもたなければ、他者の痛みや苦しみに共感することは難しいでしょう。あなたは今、とても苦しみ、身も心も痛んでいます。それは、看護師に必要な共感や理解という資質を養うための“学び”であるといえないでしょうか? 友達は合格して看護の勉強をしているかもしれませんが、あなたもまた、目には見えない“学校”で、非常に大切な勉強をしているのではないでしょうか」
彼女は、真剣に耳を傾けていた。
「神様は、あなたのすばらしい看護師への動機と意欲を賞賛し、あなたの夢を叶えてすばらしい看護師にさせるために、あえて“不合格”という“恩恵”を与えたのかもしれません。もしあのまま合格していたら、あなたの友達のように、不合格になった人を前に平気で授業の話をするような、無神経で冷たい看護師になっていたかもしれません。そんな看護師が、患者さんを癒せるはずはないのです。だから、本当に“合格”したのは、友達なんかではなく、あなたなのですよ。あなたこそ“選ばれた”のです」
彼女の目に生気が宿ってきた。
「ええ、そうですね。でも、まだ気持ちは辛いです。どうしたらいいんでしょう?」
「自らの辛い経験を通して他者への共感と理解が深まるのですから、逃げたりしないで、じっくりとその辛さを受け止めて下さい。おおいに苦しみましょう。今は苦しみ痛むのがよい時なのです。看護師となったら、忙しくて痛み苦しんでいる暇なんてなくなりますからね。つまり、共感と理解の資質を身につけるのは、今しかないのです」
そうして、明るい希望に満ちて彼女は帰っていった。
4月15日 私は死ぬのですか? 教えてください
癌の末期で余命も長くないと診断されていた、その中年の女性患者さんは、回復への希望を捨てず、民間療法などあらゆる手段を尽くしてこられた。とはいえ、じわじわと状態は思わしくない方向へ進んでいき、本人もうすうす絶望的な未来が否定できないようになってきた。医師や私たち医療スタッフは、治りたいという患者さんの希望を否定する権利はないし、実際、わずかとはいえ奇跡的に回復するような人もいないわけではないので、悲観的な見解を述べるのは控えてきた。
「私は死ぬのですか? 教えてください」
患者さんは、穏やかでありながら、どこか怨念のようなものがこめられた口調で私に尋ねた。
「はっきりとしたことはいえません。しかし、人間は誰だって、いつ死んでもおかしくないのですから、死ぬことを覚悟しておくことは、必要かもしれません」
患者さんは泣きながらいった。
「私は、これからどう生きたらいいのか、わからないのです。どこまでも生(治ること)をめざして生きるべきなのか、それとも死をめざして生きるべきなのかと……。私は知りたいんです。治る可能性は、あるのですか?」
私は責められているような気持ちになり、返答に困った。医師からは、だいたいどの程度の病状で、余命もどのくらいなのか教えてもらっているが、私は医師ではないので、私の口からそれを告げることはできないし、仮に告げることが許されていたとしても、果たして告げただろうか? 告げるべきなのか? 告げるべきではないのか? どちらが患者さんにとっていいことなのだろうか?
私は迷う心を抑えながら、次のような、やや問題からそらしたことを述べた。
「二つの可能性があるわけです。もし、治ることをめざして、つまり、そのために家族や愛する人と楽しい想い出を残すとか、今までやりたかったことをするといった“死の準備”ができないで、そのうえ治らずに死んでしまったら、まるで書きかけの途中で終わってしまった未完の小説のように、あなたの人生は終わってしまうでしょう。しかし、もし余命を死の準備に費やすならば、あなたの人生という小説は完結され、残された人は、見事に完結されて“作品”となったあなたの人生を、いつまでも心の中にとどめておくことになるでしょう」
患者さんの目からは、尽きることなく、涙が頬を伝わって流れていた。
私は、どのようにいえば、患者さんの、この悲痛な気持ちを楽にしてあげられるのか、必死で考えたけれども、結局、何もいい言葉が出せないで、沈黙だけが部屋を満たすだけになった。そして次の予定があるために部屋を出なければならなくなった。私のカウンセリングはまさに「未完」に終わってしまった。
「ありがとうございました」と、扉をあける私の背後から言葉が聞こえた。
振り返ると、笑みを浮かべながら、悲しい目をした患者さんの顔が見えた。私はなんだか、闇の中にひとり置き去りにされたような気持ちになった。