HOME>独想録>
2004年7月の独想録
7月22日 ドボルザークの「ユーモレスク」
私の好きな曲のひとつに、ドボルザークの「ユーモレスク」がある。
5分足らずの小品であるが、ピアノやバイオリンなどでよく演奏される有名な曲なので、ご存じの方も多いと思う。
この曲は、雰囲気の異なる三つのメロディから構成されている。最初は、題名通りのひょうひょうとしたユーモア溢れるメロディ、次に、何ともいえない優美で上品なメロディ、そして三つ目は、困難に対して真剣に立ち向かっていくかのような勇壮なメロディである。ひとつの曲の中にタイプの異なるこうした三つの旋律が組み込まれていること自体、とてもチャーミングなのだが、私にはこの曲が、人生そのもの、人間としてあるべき生き方を示しているような気がしてならない。
すなわち、人間というものは、ユーモアをもってひょうひょうとしながらも、優美な上品さをもち、ときに勇気をもって挑戦的に生きていくひたむきさをもって生きるべきではないのかと。
作曲家のドボルザークは、交響曲第9番「新世界から」で有名だが、SLの趣味があって、長いこと駅にたたずんで汽車を見るのが好きだといった天真爛漫な面があった。その一方で、幼い子供と死別するなど、辛酸をなめ悲しみを乗り越えてきた経験をもっていた。「新世界から」を聴くと、まさにそんな彼の生き様とでもいうべき内容が感じられ、郷愁を誘う優美なメロディ(有名な第二楽章「家路」)もあれば、勇壮でたくましく情熱的なメロディもあるのだ(最終楽章)。
ところで、この交響曲の中では、シンバルが使われるのだが、実はそれが、たったの一回、それも終楽章の終わりの方の、「こんなところにシンバルの音がなぜ鳴るの?」と思ってしまうようなヘンな部分で、そのうえ小さい音で「シャン!」と控えめに鳴らされるだけなのである。
オーケストラでシンバルを担当する打楽器奏者は、この、ほとんど意味がないとさえ思いたくなるような、たった一回のシンバル演奏のためだけに、わざわざホールに来てステージの上に登り、出番がくるまでひたすら待ち続けるのである(たった一回のシンバルを鳴らすためだけに、オーケストラは高い人件費を払わなければならない!)。
ドボルザークが、なぜこのような、オーケストラ泣かせともいうべき「嫌がらせ」のようなことをしたのか、私にはわからない(知っている人がいたら教えて下さい)。
ただ、ドボルザークがどう考えていたかはともかく、私はこのことを肯定的に解釈したい。全体でたった一回だけ、誰が聴いても、「こんなところにシンバルを鳴らす必然性」を感じないところで、そのうえ、注意していないと聞き逃してしまうくらい小さな音で鳴らされるというところに、人生の妙味というようなものが表現されているような気がしてならない。
真にプロフェッショナルなオーケストラ奏者なら、このたった一回のシンバルの演奏に、全身全霊を傾けるだろう。「一期一会」ともいうべきこの一発を、真剣に心を込めて鳴らすだろう。「たいした意味のない音だから、いい加減にやってやろう」なんて思わないだろう(余談だが、むかしむかし、フランキー堺だったと思うが、オーケストラの打楽器奏者の役で、居眠りしていてこの部分のシンバルを忘れてしまってクビになるという映画があった)。
世の中には、一見すると、何の意味もないように思えるものが、実は(神の目から見れば)非常に意味があるということもある。人間の限られた小賢しい頭で「これは意味がない」なんて決めつけることはできないのだろう。どんなささいに思えることにも意味があるのだという謙虚さというか、人生のあらゆることを、おおらかに広く深く見つめる感性といったものが大切なのだと思う。
そんな感性をもった人たちは、たとえ日常のさりげない掃除だとか、地味すぎて誰も振り向かないような単調な仕事でさえ、心を込めて真剣に、誠実に、淡々とやるに違いない。
社会的な基準からいえば、あまり価値がないとされる人たちに対しても、また、地位が高いとか低いとか、生産的であるとか、そうでないとか、そういったものに一切こだわらず、存在する限りはどんなにちっぽけであっても、かけがえのない存在であるということ、どんなに小さな存在でも、それはこの地上の空間を占めているのだということ、こうしたことを、陳腐な社会道徳や倫理といった範疇からではなく、もっと深い、生命の奥から自然とわき上がる畏敬の念といったものを通して体現している(つまりは、本人は無自覚でありながら、こうした生き方をさりげなくしているということ)に違いない。
そこには、いかなる「わざとらしさ」も「おしつけがましさ」も、自分を見せようとする気持ちもなく、自然で、ひょうひょうとして、ユーモアさえ感じられる雰囲気をもっているように思う。もちろん、ひょうきんさやユーモアだけでなく、優美なところもあり、また、勇ましいところもあるだろう。
こういう人こそ、真に「悟った人」なのではないだろうか。この3つの要素のうち、どれひとつ欠けても、悟っているとはいえないと思うのだ。ひょうきんなだけも、優美なだけでも、勇ましいだけでもダメなのだ。この3つのすべてが統合されていなければ、人間として完成されたとはいえないのだと思う。いかにも悟りすましたような人というのは、たぶん、悟ってはいない。
こうした3つの要素がすべて見事に表現されているのが「ユーモレスク」なのだ。
つまり、この曲は、「悟りの境地」を表現した音楽なのだと、私は勝手に思っている。「ユーモレスク」のような可愛らしい小品を「悟りの曲だ」なんていうと、たぶん、笑われてしまうかもしれないけれど、私の感性からいうならば、この曲はまさに「悟った人」を描いたともいうべき、真にすばらしい名曲なのである。
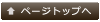
7月29日 決して裏切らない人
まだ若い二人の女性がカウンセリングにやってきた。
ひとりは、小さい頃から親のひどい虐待を受けて育った女性であった。若くして結婚したものの、結婚相手の男性も暴力的であった。親からも配偶者からも、まるで自分は、相手のストレスのはけ口の道具として扱われてきたという。
もうひとりは、子供の頃に父親が癌でなくなり、しばらくして、母親が自殺してしまった女性だった。その後、祖父母に育てられたが、一人っ子であり独身である彼女は、この祖父母が死んでしまったら、ほとんど身よりのいない天涯孤独の身になってしまうだろう。
二人の女性は、ともに人生のパートナーを、すなわち、結婚相手となる男性を求めていた。そして二人とも、同じ男性像を求めていた。
異口同音に彼女たちは言った。
「“決して裏切らない人”が欲しい・・・」。
「裏切らない」という意味は、単なる「浮気をしない」といったことではなく、もっと深く、人間性にかかわるレベルでの「裏切らない人」であった。
すなわち、前者の女性の場合、口ではやさしいことをいいながら、気分によって暴力を振るうことのない男性であった。「もう二度と暴力はしない」と謝っておきながら、何回もそれを破って暴力を振るうようなことをしない男性であった。
後者の女性の場合、自分を後に残して死んでしまったり、離れていったりしない男性であった。つまり、自分を孤独にしない男性、自分を決して見捨てることのない男性であった。彼女にとって、父親が癌で死んだこと、母親が自らの命を断った行為は、彼女にとっては「裏切り行為」なのであった。
こうした切望を心の底に抱く彼女たちは、配偶者となる男性だけでなく、どのような人に対しても、「本当にこの人は信用できるのか?」というまなざしで相手を見てきたようだった。
本当に信用できれば、心を開いて相手と接することができた。自分のありのままの感情をさらけだすことができ、相手の前で涙を流すことができた。しかし、信用できない相手には、決して自分の本心をさらけださない。表面だけをそつなく取り繕って、仮面をかぶり、うわべだけのつき合いをする。こうした二面的な態度をはっきりと使い分けていた。
心が純粋な人は(子供の頃は誰でも純粋だったはずだ)、人から裏切られると、とても傷ついてしまう。それは、人道的に許されないくらい大きな裏切りの場合もあれば、「今度メール送るからね」といっておきながら、結局はそのメールが来ないといったような、小さなことまであるかもしれないが、それでも心が繊細で純粋な人は傷ついてしまう。
そうして、しだいに他者に対して懐疑的になってしまうのだ。
「いま、この人は調子のいいことをいっているけれど、最後には自分を裏切るに違いない、自分から離れていってしまうに違いない……」
こんな疑惑や不安が頭から離れなくなってしまう。
それでも、人を信じたい気持ちはあるし、むしろ、こういう繊細で純粋な人ほど、本当に真実で誠実で、深く親しく、人との交流と触れあいを求めているから、「今度こそは」と期待して心を許し、誰かと交わろうとする。
ところが、やがてそうして付き合った人も、彼らのいう「裏切り」の行為をすることになり、またしても深く傷ついてしまうのだ。
そうして、こんなことを繰り返していくうちに、もう本当に人間なんか信じるのはやめてしまう。決して誰にも心を開くことなく、表面的な交際だけ適当にやって、あとは孤独に生きるようになってしまう。ある人は、裏切ることのない動物をパートナーにしながら。またある人は芸術を、ある人は自然を、唯一の心を許せる友として。
2004年7月の独想録
7月22日 ドボルザークの「ユーモレスク」
私の好きな曲のひとつに、ドボルザークの「ユーモレスク」がある。
5分足らずの小品であるが、ピアノやバイオリンなどでよく演奏される有名な曲なので、ご存じの方も多いと思う。
この曲は、雰囲気の異なる三つのメロディから構成されている。最初は、題名通りのひょうひょうとしたユーモア溢れるメロディ、次に、何ともいえない優美で上品なメロディ、そして三つ目は、困難に対して真剣に立ち向かっていくかのような勇壮なメロディである。ひとつの曲の中にタイプの異なるこうした三つの旋律が組み込まれていること自体、とてもチャーミングなのだが、私にはこの曲が、人生そのもの、人間としてあるべき生き方を示しているような気がしてならない。
すなわち、人間というものは、ユーモアをもってひょうひょうとしながらも、優美な上品さをもち、ときに勇気をもって挑戦的に生きていくひたむきさをもって生きるべきではないのかと。
作曲家のドボルザークは、交響曲第9番「新世界から」で有名だが、SLの趣味があって、長いこと駅にたたずんで汽車を見るのが好きだといった天真爛漫な面があった。その一方で、幼い子供と死別するなど、辛酸をなめ悲しみを乗り越えてきた経験をもっていた。「新世界から」を聴くと、まさにそんな彼の生き様とでもいうべき内容が感じられ、郷愁を誘う優美なメロディ(有名な第二楽章「家路」)もあれば、勇壮でたくましく情熱的なメロディもあるのだ(最終楽章)。
ところで、この交響曲の中では、シンバルが使われるのだが、実はそれが、たったの一回、それも終楽章の終わりの方の、「こんなところにシンバルの音がなぜ鳴るの?」と思ってしまうようなヘンな部分で、そのうえ小さい音で「シャン!」と控えめに鳴らされるだけなのである。
オーケストラでシンバルを担当する打楽器奏者は、この、ほとんど意味がないとさえ思いたくなるような、たった一回のシンバル演奏のためだけに、わざわざホールに来てステージの上に登り、出番がくるまでひたすら待ち続けるのである(たった一回のシンバルを鳴らすためだけに、オーケストラは高い人件費を払わなければならない!)。
ドボルザークが、なぜこのような、オーケストラ泣かせともいうべき「嫌がらせ」のようなことをしたのか、私にはわからない(知っている人がいたら教えて下さい)。
ただ、ドボルザークがどう考えていたかはともかく、私はこのことを肯定的に解釈したい。全体でたった一回だけ、誰が聴いても、「こんなところにシンバルを鳴らす必然性」を感じないところで、そのうえ、注意していないと聞き逃してしまうくらい小さな音で鳴らされるというところに、人生の妙味というようなものが表現されているような気がしてならない。
真にプロフェッショナルなオーケストラ奏者なら、このたった一回のシンバルの演奏に、全身全霊を傾けるだろう。「一期一会」ともいうべきこの一発を、真剣に心を込めて鳴らすだろう。「たいした意味のない音だから、いい加減にやってやろう」なんて思わないだろう(余談だが、むかしむかし、フランキー堺だったと思うが、オーケストラの打楽器奏者の役で、居眠りしていてこの部分のシンバルを忘れてしまってクビになるという映画があった)。
世の中には、一見すると、何の意味もないように思えるものが、実は(神の目から見れば)非常に意味があるということもある。人間の限られた小賢しい頭で「これは意味がない」なんて決めつけることはできないのだろう。どんなささいに思えることにも意味があるのだという謙虚さというか、人生のあらゆることを、おおらかに広く深く見つめる感性といったものが大切なのだと思う。
そんな感性をもった人たちは、たとえ日常のさりげない掃除だとか、地味すぎて誰も振り向かないような単調な仕事でさえ、心を込めて真剣に、誠実に、淡々とやるに違いない。
社会的な基準からいえば、あまり価値がないとされる人たちに対しても、また、地位が高いとか低いとか、生産的であるとか、そうでないとか、そういったものに一切こだわらず、存在する限りはどんなにちっぽけであっても、かけがえのない存在であるということ、どんなに小さな存在でも、それはこの地上の空間を占めているのだということ、こうしたことを、陳腐な社会道徳や倫理といった範疇からではなく、もっと深い、生命の奥から自然とわき上がる畏敬の念といったものを通して体現している(つまりは、本人は無自覚でありながら、こうした生き方をさりげなくしているということ)に違いない。
そこには、いかなる「わざとらしさ」も「おしつけがましさ」も、自分を見せようとする気持ちもなく、自然で、ひょうひょうとして、ユーモアさえ感じられる雰囲気をもっているように思う。もちろん、ひょうきんさやユーモアだけでなく、優美なところもあり、また、勇ましいところもあるだろう。
こういう人こそ、真に「悟った人」なのではないだろうか。この3つの要素のうち、どれひとつ欠けても、悟っているとはいえないと思うのだ。ひょうきんなだけも、優美なだけでも、勇ましいだけでもダメなのだ。この3つのすべてが統合されていなければ、人間として完成されたとはいえないのだと思う。いかにも悟りすましたような人というのは、たぶん、悟ってはいない。
こうした3つの要素がすべて見事に表現されているのが「ユーモレスク」なのだ。
つまり、この曲は、「悟りの境地」を表現した音楽なのだと、私は勝手に思っている。「ユーモレスク」のような可愛らしい小品を「悟りの曲だ」なんていうと、たぶん、笑われてしまうかもしれないけれど、私の感性からいうならば、この曲はまさに「悟った人」を描いたともいうべき、真にすばらしい名曲なのである。
7月29日 決して裏切らない人
まだ若い二人の女性がカウンセリングにやってきた。
ひとりは、小さい頃から親のひどい虐待を受けて育った女性であった。若くして結婚したものの、結婚相手の男性も暴力的であった。親からも配偶者からも、まるで自分は、相手のストレスのはけ口の道具として扱われてきたという。
もうひとりは、子供の頃に父親が癌でなくなり、しばらくして、母親が自殺してしまった女性だった。その後、祖父母に育てられたが、一人っ子であり独身である彼女は、この祖父母が死んでしまったら、ほとんど身よりのいない天涯孤独の身になってしまうだろう。
二人の女性は、ともに人生のパートナーを、すなわち、結婚相手となる男性を求めていた。そして二人とも、同じ男性像を求めていた。
異口同音に彼女たちは言った。
「“決して裏切らない人”が欲しい・・・」。
「裏切らない」という意味は、単なる「浮気をしない」といったことではなく、もっと深く、人間性にかかわるレベルでの「裏切らない人」であった。
すなわち、前者の女性の場合、口ではやさしいことをいいながら、気分によって暴力を振るうことのない男性であった。「もう二度と暴力はしない」と謝っておきながら、何回もそれを破って暴力を振るうようなことをしない男性であった。
後者の女性の場合、自分を後に残して死んでしまったり、離れていったりしない男性であった。つまり、自分を孤独にしない男性、自分を決して見捨てることのない男性であった。彼女にとって、父親が癌で死んだこと、母親が自らの命を断った行為は、彼女にとっては「裏切り行為」なのであった。
こうした切望を心の底に抱く彼女たちは、配偶者となる男性だけでなく、どのような人に対しても、「本当にこの人は信用できるのか?」というまなざしで相手を見てきたようだった。
本当に信用できれば、心を開いて相手と接することができた。自分のありのままの感情をさらけだすことができ、相手の前で涙を流すことができた。しかし、信用できない相手には、決して自分の本心をさらけださない。表面だけをそつなく取り繕って、仮面をかぶり、うわべだけのつき合いをする。こうした二面的な態度をはっきりと使い分けていた。
心が純粋な人は(子供の頃は誰でも純粋だったはずだ)、人から裏切られると、とても傷ついてしまう。それは、人道的に許されないくらい大きな裏切りの場合もあれば、「今度メール送るからね」といっておきながら、結局はそのメールが来ないといったような、小さなことまであるかもしれないが、それでも心が繊細で純粋な人は傷ついてしまう。
そうして、しだいに他者に対して懐疑的になってしまうのだ。
「いま、この人は調子のいいことをいっているけれど、最後には自分を裏切るに違いない、自分から離れていってしまうに違いない……」
こんな疑惑や不安が頭から離れなくなってしまう。
それでも、人を信じたい気持ちはあるし、むしろ、こういう繊細で純粋な人ほど、本当に真実で誠実で、深く親しく、人との交流と触れあいを求めているから、「今度こそは」と期待して心を許し、誰かと交わろうとする。
ところが、やがてそうして付き合った人も、彼らのいう「裏切り」の行為をすることになり、またしても深く傷ついてしまうのだ。
そうして、こんなことを繰り返していくうちに、もう本当に人間なんか信じるのはやめてしまう。決して誰にも心を開くことなく、表面的な交際だけ適当にやって、あとは孤独に生きるようになってしまう。ある人は、裏切ることのない動物をパートナーにしながら。またある人は芸術を、ある人は自然を、唯一の心を許せる友として。