HOME>独想録>
2004年5月の独想録
5月5日 3年間努力し続ければ
私の知り合いから、「部屋を整理していたら、こんなのが出てきたから送ります」といって、あるものが郵送されてきた。それは、雑誌から破られたひとつの記事であった。
その記事には見覚えがあった。それは、私が確か20歳か、21歳くらいのとき、学研から出している『中学二年コース』という雑誌に書いた超能力に関する記事だった。まるでタイムカプセルを開けたような思いがした。初めて原稿を書いて私の名前が活字となり、報酬をもらった最初の仕事だったのだ。私が大学生のときのことだ。
当時、私は超常現象を研究するある団体に所属していたのだが、そこの事務所に、この雑誌編集者から「超能力に関する記事を書いて欲しい」と依頼が来たのだった。受付の人が応対し、所属していた大学の先生などに頼んでみたのだが、どの先生も忙しくて、記事を書いている時間がないという。そこで受付の人が、「まだ若いけど、斉藤君というのがいるから、彼なら記事を書けるから頼んでみたら」と紹介してくれたのである。編集者は「え〜、学生ですかあ〜」と不満そうな声を上げていたという。それで、しぶしぶといった感じで私の自宅に電話がかかってきた。その応対ぶりも、「どうせ素人の学生なんかにロクな記事が書けるわけない」といった調子で、横柄な口調で、どんな内容の記事が書きたいのかを説明したのである。私はちょっと相手を見返してやろうと思い、電話があったのは夜だったのだが、そのまま徹夜をして原稿を書き上げ、明くる日に編集者に会ってその原稿を渡した。それまで3年ほど、このような世界を集中的に研究していたので、書く内容については何も困らなかった。
一夜にして仕上がったその原稿を見て、編集者は目を丸くしたのを覚えている。「完璧だ! まさにこんな記事を求めていたんです」と驚きの声をあげ、それ以後、その人はガラリと態度が変わり、私のことを「斉藤先生」とまで呼ぶようになった。紹介してくれた受付の人も鼻高々で「ほらみろ!」といった調子だった。
振り返れば、愉快で懐かしい想い出である。
私は思うのだが、どんなことでも3年もやっていると、何となくやり遂げることができて、それなりに報われたりするものだ。そのかわり、その3年間だけは、ひたすらエネルギーを集中するのだ。たとえば楽器演奏でもいいし、英会話でも、その他、何であれ、3年もがんばり続けるなら、才能のあるなしに関係なく、誰でもある程度のレベルにはなれるのではないかと思う。
ところが、世の中の大多数の人は、3年という年月を続けたりしない。どんなに才能をもっていたって、三日で達人になれるはずがない。しかし特別に才能はなくても、3年くらい努力すれば、そこそこ専門家になることはできると思う。案外、才能がある人ほど、長い間の努力などバカバカしくてやらず、結局、何も成果があがらないということになるのかもしれない。「3年間努力できること自体が才能だ」といわれればそれまでだが、一般に「努力」なんていうものは、才能とは思われていない。才能というには、あまりにも地味で味気ないものだ。
しかし、最後にものをいうのは、結局、忍耐強い努力ではないのだろうか。「ウサギとカメ」の話のように、カメこそが、最後に勝利を収めるのではないだろうか。
若い頃、「カメ」なんて大嫌いだった。そんなカッコ悪く退屈な生き方なんて、まっぴらごめんだった。「ウサギ」のように、スマートにさりげなく仕事をして、たちまちすばらしい業績を残せるような人間になりたいと思っていたものだ。
けれど、歳を取った今、私はむしろ「カメ」こそが、カッコいい生き方であると感じられる。退屈だとも思わない。重いこおらを背中にしょっているカメにとって、一歩一歩が大変な苦労であるに違いない。力を振り絞って、必死な思いをしながら前進しているのだ。退屈なんて感じているゆとりはないはずだ。若い頃は、こんなのろまな生き方はダサいと思っていたけれど、今では崇高なものを感じる。そういう生き方をしている人がいたら、私は深い尊敬の念を覚えるだろう。
ところで、余談だが、カメはなぜ、ウサギとの競争に応じたのだろうか?
ウサギの方が早いことは一目瞭然である。そんなことにも気づかないほど、カメはバカだったのだろうか?
私はそうは思わない。実はカメは非常に頭がよかったのだ。そのため、ウサギが途中で油断して居眠りでもするだろうと、最初から読んでいたに違いない。だから、まともに考えれば勝算などまったくない、無謀ともいえるような競争に挑んだのではないだろうか。そうして見事、計算通り、勝利を収めたのである。
そういう点から見ても、やはりカメはカッコいいと思う。
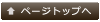
5月12日 真剣に生きる
ストレスというと、現代では「悪玉」の最たるものと見なされている。そんなストレスで神経症や鬱病になった人に「がんばれ!」ということはタブーだとされる。彼らは十分にがんばっている。これ以上がんばれということは、その責任を重くして、ますます落ち込ませるだけであると。
しかし、「がんばれといってはいけない」ということを、固定化された「真実」としてとらえるのは誤りであると私は思う。
たとえば、戦争や大規模な天災といったものが起きると、神経症患者が激減するという統計がある。それはなぜだろうか? 非常事態が来て「がんばったから」ではないのだろうか? がんばったために神経症が治ってしまったのではないだろうか? がんばらなければ確実に死ぬという状況に追い込まれても、がんばれないでそのまま死んでしまったとしたら、その人は本当に重い病気だったのだと思う。しかし、なかにはまだまだがんばれる人も相当いるのではないだろうか?
ストレスというのは、要するに「それが嫌だ」という気持ちがあるときに生じる。仕事のために徹夜するとストレスがたまるが、麻雀ならストレスにならない。だが、麻雀が嫌いな人に徹夜でやらせたら、ストレスでいっぱいになるだろう。
つまり、「嫌だと思うからストレスとなり、嫌だと思わなければストレスにはならない」ということなのだ。
もちろん、人間として、誰もが感じるストレスというものはある。たとえば強制収容所のような、極端に劣悪な生活環境に置かれたような場合だ。しかし、こうしたことは滅多にあるものではない。
したがって、現代社会はストレスだらけだというが、視点を変えて言えば、「現代人は“嫌だ”と思うものが多くなった」ということではないだろうか?
多くの人は、「自分が嫌なことをさせられた」ということで、ストレスに苦しんでいるだけではないのだろうか?
むかし、こうした問題のある子供を受け入れてスパルタ式に指導する「戸塚ヨットスクール」というのがあった。死亡者が出て問題となり廃止されたが、そこには一理の真実があったような気もする。実際、そのスクールで多くの子供が立ち直り、感謝する親も少なくなかった。
嫌なことから逃げようとしたら、際限がない、というのが人生ではないだろうか。
職場に嫌な人間がいるからストレスになるというが、嫌な人間はどこにでもいる。嫌な人間のいない職場を追求していったらきりがない。嫌な人間がいても、それにストレスを感じない自分になる以外には道はないように思う。
ところが、いわゆる癒し系の本などを読むと「ねばならない」というのはよくない、といったことが書いてある。「がんばってはいけない」とか、「ありのままの自分でいい」などといっている。こんな本を、戦争や混乱や貧困で悲惨な状況に生きている人たちに見せてやりたい。そのあまりの幼稚な内容に笑われるか、あきれられるのがオチだろう。「がんばらなくても生きられるあなた方がうらやましい」といわれるだろう。彼らには、がんばるか、がんばらないかといった選択の余地はない。がんばるか、さもなくば死ぬしかないのだ。しかし、そういう状況に生きている人たちの目を見て欲しい。ふやけた日本人なんかより、ずっと生き生きした目をしているはずだ。
「がんばらなくてもいい」などという、人間の怠惰心につけこんで本を売ろうとしている商業主義にだまされているから、ちょっと自分が気にいらないことがあると、たちまち「ストレス」になってしまう人間が増えてしまったのではないのか。
世の中には、冒険や危険を冒さなければ、手に入らないものもある。いつまでも病人として一生を生きるというのは、すでに死んでいるも同然だ。そのようになった人を蘇生させるには、生やさしい方法がどれほど通用するか、疑問である。
世の中で、どれほどの人が真剣に生きているだろう。真剣とは文字通り「真剣」なのであり、竹刀や木刀ではない。当たったら肉体が切り裂かれ死んでしまうのだ。つまり、命がけだ。真剣に生きるとは、命がけで生きるということだ。一歩間違ったら死んでしまうような状況を生きることだ。
これは少し極端であるとしても、このくらいの気持ちで毎日を生きていれば、きっと人生において何かをつかむことができるのではないかと思う。
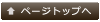
5月20日 真実はひとつであり多でもある
真実というものは、固定された一点に存在するというものではなく、不可知なる全体を不動のものにさせるダイナミックな運動の中にある、いや、その運動そのものが真実ではないのかと、私は思っている。このことは、私の生きざまの基調ともなっている。
たとえば、「起きあがりこぼし」を右に倒すと、それは左に移動して起きあがる。この場合の真実とは「左に向かう運動」なのだ。また、左に倒すと右に向かう。この場合は「右に向かう運動」が真実なのだ。あるときは「右運動」が真実となり、あるときは「左運動」が真実となる。
このことは、「真実はその時代の社会状況に応じて変わるものだ」といった皮相的な意味ではない。究極的な「真実」は、まさにダイナミズムの中に多様に存在するという意味である。
真実というものは、おそらく「生きている」。生きているとは、活動しているということだ。そして、活動しているということは、恒久的なシンメトリーのバランスを維持し続けているのではなく、バランスを崩すということである。人間は歩いているときは、上半身を左右のどちらかに傾けて一本足で地面を蹴っている。きわめてアンバランスな状態だ。「歩く」という「真実」は、「右足を出す」ことであり、また「左足を出す」ということなのだ。だが、このアンバランスな運動の中に、「二本足でまっすぐ歩く」という、きわめてバランスのよい安定した状態が築かれているのである。
だから、「これが真実だ」といって、固定的で恒久的な一点を指し示すような言説を、私は信じることはできない。それは政治的な右翼だとか左翼といったものもそうであるし、互いを否定し合うな宗教上のドグマから、「こうすれば健康になる」といったハウツーに至るまでそうだ。
むかしは、栄養満点の食事を取ることがいいとされたが、今では粗食が健康にいいという。むかしは熱が出れば冷まさなければならないといわれていたが、今では、熱は身体に侵入したウイルスを死滅させるための身体の防御反応だから、あたたかくしているのがいいとされる。ところが中には、身体を冷たくした方が、その冷たさに反発して身体がもっと熱を出すから、やはり冷たくした方がいいんだ、といった説もある。こうなると、いったいどの説が本当なのだか、わからなくなってくる。
「真実は一つだ」というのは、おそらく正しいだろう。ところが、ひとつである真実は、多様に現れるのだと思う。神様だってそうだ。神は根本的な第一原理であるから、当然のことながら、神はひとつであろう。だが、そのひとつである神は、多様に現れる。また、多様に現れるからこそ「ひとつである」ことの証明ともなっている。神はどこかの空間の一点にのみ存在するという考え方は、「一本足で歩行できる」といっているのと同じだ。二本足でこそ、人間はひとりで歩けるのだ。
だから、ユダヤ・キリスト・イスラムのような一神教も真実であるし、神道のような多神教もまた真実なのだと思う。真実ではないのは、そうしたことが真実であると見抜けないわれわれ人間の認識そのものにある。ユダヤ教の神、キリスト教の神、イスラム教の神、ヒンヅー教や神道の神など、さまざまな神が存在しているということ自体が、神は「ひとつ」であることを証明しているのではないだろうか。そのことを見抜けず、「一神教だけが真実で多神教を説く宗教は間違っている」などと言ったりする。何と皮相的で物質的なものの見方なのだろう。
神はひとつにして多であるという主張は「矛盾」している。論理的知性では。けれども、神は知性や論理で認識される存在ではない。ただ愛だけが、この言葉を何の矛盾も感じることなく認識することができるに違いない。神は愛をもってのみ認識されるのであり、そのとき神は、一にして多、多にして一になる。
宗教の名のもとに殺し合いをしている人たちは、神のことなど何もわかっていないのだと思う。真のユダヤ教徒、真のキリスト教徒、真のイスラム教徒であれば、他の宗教を否定するなんてことはあり得ない。愛し合う二人の間に、まさに「生きている」神の存在そのものを感じるからだ。
2004年5月の独想録
5月5日 3年間努力し続ければ
私の知り合いから、「部屋を整理していたら、こんなのが出てきたから送ります」といって、あるものが郵送されてきた。それは、雑誌から破られたひとつの記事であった。
その記事には見覚えがあった。それは、私が確か20歳か、21歳くらいのとき、学研から出している『中学二年コース』という雑誌に書いた超能力に関する記事だった。まるでタイムカプセルを開けたような思いがした。初めて原稿を書いて私の名前が活字となり、報酬をもらった最初の仕事だったのだ。私が大学生のときのことだ。
当時、私は超常現象を研究するある団体に所属していたのだが、そこの事務所に、この雑誌編集者から「超能力に関する記事を書いて欲しい」と依頼が来たのだった。受付の人が応対し、所属していた大学の先生などに頼んでみたのだが、どの先生も忙しくて、記事を書いている時間がないという。そこで受付の人が、「まだ若いけど、斉藤君というのがいるから、彼なら記事を書けるから頼んでみたら」と紹介してくれたのである。編集者は「え〜、学生ですかあ〜」と不満そうな声を上げていたという。それで、しぶしぶといった感じで私の自宅に電話がかかってきた。その応対ぶりも、「どうせ素人の学生なんかにロクな記事が書けるわけない」といった調子で、横柄な口調で、どんな内容の記事が書きたいのかを説明したのである。私はちょっと相手を見返してやろうと思い、電話があったのは夜だったのだが、そのまま徹夜をして原稿を書き上げ、明くる日に編集者に会ってその原稿を渡した。それまで3年ほど、このような世界を集中的に研究していたので、書く内容については何も困らなかった。
一夜にして仕上がったその原稿を見て、編集者は目を丸くしたのを覚えている。「完璧だ! まさにこんな記事を求めていたんです」と驚きの声をあげ、それ以後、その人はガラリと態度が変わり、私のことを「斉藤先生」とまで呼ぶようになった。紹介してくれた受付の人も鼻高々で「ほらみろ!」といった調子だった。
振り返れば、愉快で懐かしい想い出である。
私は思うのだが、どんなことでも3年もやっていると、何となくやり遂げることができて、それなりに報われたりするものだ。そのかわり、その3年間だけは、ひたすらエネルギーを集中するのだ。たとえば楽器演奏でもいいし、英会話でも、その他、何であれ、3年もがんばり続けるなら、才能のあるなしに関係なく、誰でもある程度のレベルにはなれるのではないかと思う。
ところが、世の中の大多数の人は、3年という年月を続けたりしない。どんなに才能をもっていたって、三日で達人になれるはずがない。しかし特別に才能はなくても、3年くらい努力すれば、そこそこ専門家になることはできると思う。案外、才能がある人ほど、長い間の努力などバカバカしくてやらず、結局、何も成果があがらないということになるのかもしれない。「3年間努力できること自体が才能だ」といわれればそれまでだが、一般に「努力」なんていうものは、才能とは思われていない。才能というには、あまりにも地味で味気ないものだ。
しかし、最後にものをいうのは、結局、忍耐強い努力ではないのだろうか。「ウサギとカメ」の話のように、カメこそが、最後に勝利を収めるのではないだろうか。
若い頃、「カメ」なんて大嫌いだった。そんなカッコ悪く退屈な生き方なんて、まっぴらごめんだった。「ウサギ」のように、スマートにさりげなく仕事をして、たちまちすばらしい業績を残せるような人間になりたいと思っていたものだ。
けれど、歳を取った今、私はむしろ「カメ」こそが、カッコいい生き方であると感じられる。退屈だとも思わない。重いこおらを背中にしょっているカメにとって、一歩一歩が大変な苦労であるに違いない。力を振り絞って、必死な思いをしながら前進しているのだ。退屈なんて感じているゆとりはないはずだ。若い頃は、こんなのろまな生き方はダサいと思っていたけれど、今では崇高なものを感じる。そういう生き方をしている人がいたら、私は深い尊敬の念を覚えるだろう。
ところで、余談だが、カメはなぜ、ウサギとの競争に応じたのだろうか?
ウサギの方が早いことは一目瞭然である。そんなことにも気づかないほど、カメはバカだったのだろうか?
私はそうは思わない。実はカメは非常に頭がよかったのだ。そのため、ウサギが途中で油断して居眠りでもするだろうと、最初から読んでいたに違いない。だから、まともに考えれば勝算などまったくない、無謀ともいえるような競争に挑んだのではないだろうか。そうして見事、計算通り、勝利を収めたのである。
そういう点から見ても、やはりカメはカッコいいと思う。
5月12日 真剣に生きる
ストレスというと、現代では「悪玉」の最たるものと見なされている。そんなストレスで神経症や鬱病になった人に「がんばれ!」ということはタブーだとされる。彼らは十分にがんばっている。これ以上がんばれということは、その責任を重くして、ますます落ち込ませるだけであると。
しかし、「がんばれといってはいけない」ということを、固定化された「真実」としてとらえるのは誤りであると私は思う。
たとえば、戦争や大規模な天災といったものが起きると、神経症患者が激減するという統計がある。それはなぜだろうか? 非常事態が来て「がんばったから」ではないのだろうか? がんばったために神経症が治ってしまったのではないだろうか? がんばらなければ確実に死ぬという状況に追い込まれても、がんばれないでそのまま死んでしまったとしたら、その人は本当に重い病気だったのだと思う。しかし、なかにはまだまだがんばれる人も相当いるのではないだろうか?
ストレスというのは、要するに「それが嫌だ」という気持ちがあるときに生じる。仕事のために徹夜するとストレスがたまるが、麻雀ならストレスにならない。だが、麻雀が嫌いな人に徹夜でやらせたら、ストレスでいっぱいになるだろう。
つまり、「嫌だと思うからストレスとなり、嫌だと思わなければストレスにはならない」ということなのだ。
もちろん、人間として、誰もが感じるストレスというものはある。たとえば強制収容所のような、極端に劣悪な生活環境に置かれたような場合だ。しかし、こうしたことは滅多にあるものではない。
したがって、現代社会はストレスだらけだというが、視点を変えて言えば、「現代人は“嫌だ”と思うものが多くなった」ということではないだろうか?
多くの人は、「自分が嫌なことをさせられた」ということで、ストレスに苦しんでいるだけではないのだろうか?
むかし、こうした問題のある子供を受け入れてスパルタ式に指導する「戸塚ヨットスクール」というのがあった。死亡者が出て問題となり廃止されたが、そこには一理の真実があったような気もする。実際、そのスクールで多くの子供が立ち直り、感謝する親も少なくなかった。
嫌なことから逃げようとしたら、際限がない、というのが人生ではないだろうか。
職場に嫌な人間がいるからストレスになるというが、嫌な人間はどこにでもいる。嫌な人間のいない職場を追求していったらきりがない。嫌な人間がいても、それにストレスを感じない自分になる以外には道はないように思う。
ところが、いわゆる癒し系の本などを読むと「ねばならない」というのはよくない、といったことが書いてある。「がんばってはいけない」とか、「ありのままの自分でいい」などといっている。こんな本を、戦争や混乱や貧困で悲惨な状況に生きている人たちに見せてやりたい。そのあまりの幼稚な内容に笑われるか、あきれられるのがオチだろう。「がんばらなくても生きられるあなた方がうらやましい」といわれるだろう。彼らには、がんばるか、がんばらないかといった選択の余地はない。がんばるか、さもなくば死ぬしかないのだ。しかし、そういう状況に生きている人たちの目を見て欲しい。ふやけた日本人なんかより、ずっと生き生きした目をしているはずだ。
「がんばらなくてもいい」などという、人間の怠惰心につけこんで本を売ろうとしている商業主義にだまされているから、ちょっと自分が気にいらないことがあると、たちまち「ストレス」になってしまう人間が増えてしまったのではないのか。
世の中には、冒険や危険を冒さなければ、手に入らないものもある。いつまでも病人として一生を生きるというのは、すでに死んでいるも同然だ。そのようになった人を蘇生させるには、生やさしい方法がどれほど通用するか、疑問である。
世の中で、どれほどの人が真剣に生きているだろう。真剣とは文字通り「真剣」なのであり、竹刀や木刀ではない。当たったら肉体が切り裂かれ死んでしまうのだ。つまり、命がけだ。真剣に生きるとは、命がけで生きるということだ。一歩間違ったら死んでしまうような状況を生きることだ。
これは少し極端であるとしても、このくらいの気持ちで毎日を生きていれば、きっと人生において何かをつかむことができるのではないかと思う。
5月20日 真実はひとつであり多でもある
真実というものは、固定された一点に存在するというものではなく、不可知なる全体を不動のものにさせるダイナミックな運動の中にある、いや、その運動そのものが真実ではないのかと、私は思っている。このことは、私の生きざまの基調ともなっている。
たとえば、「起きあがりこぼし」を右に倒すと、それは左に移動して起きあがる。この場合の真実とは「左に向かう運動」なのだ。また、左に倒すと右に向かう。この場合は「右に向かう運動」が真実なのだ。あるときは「右運動」が真実となり、あるときは「左運動」が真実となる。
このことは、「真実はその時代の社会状況に応じて変わるものだ」といった皮相的な意味ではない。究極的な「真実」は、まさにダイナミズムの中に多様に存在するという意味である。
真実というものは、おそらく「生きている」。生きているとは、活動しているということだ。そして、活動しているということは、恒久的なシンメトリーのバランスを維持し続けているのではなく、バランスを崩すということである。人間は歩いているときは、上半身を左右のどちらかに傾けて一本足で地面を蹴っている。きわめてアンバランスな状態だ。「歩く」という「真実」は、「右足を出す」ことであり、また「左足を出す」ということなのだ。だが、このアンバランスな運動の中に、「二本足でまっすぐ歩く」という、きわめてバランスのよい安定した状態が築かれているのである。
だから、「これが真実だ」といって、固定的で恒久的な一点を指し示すような言説を、私は信じることはできない。それは政治的な右翼だとか左翼といったものもそうであるし、互いを否定し合うな宗教上のドグマから、「こうすれば健康になる」といったハウツーに至るまでそうだ。
むかしは、栄養満点の食事を取ることがいいとされたが、今では粗食が健康にいいという。むかしは熱が出れば冷まさなければならないといわれていたが、今では、熱は身体に侵入したウイルスを死滅させるための身体の防御反応だから、あたたかくしているのがいいとされる。ところが中には、身体を冷たくした方が、その冷たさに反発して身体がもっと熱を出すから、やはり冷たくした方がいいんだ、といった説もある。こうなると、いったいどの説が本当なのだか、わからなくなってくる。
「真実は一つだ」というのは、おそらく正しいだろう。ところが、ひとつである真実は、多様に現れるのだと思う。神様だってそうだ。神は根本的な第一原理であるから、当然のことながら、神はひとつであろう。だが、そのひとつである神は、多様に現れる。また、多様に現れるからこそ「ひとつである」ことの証明ともなっている。神はどこかの空間の一点にのみ存在するという考え方は、「一本足で歩行できる」といっているのと同じだ。二本足でこそ、人間はひとりで歩けるのだ。
だから、ユダヤ・キリスト・イスラムのような一神教も真実であるし、神道のような多神教もまた真実なのだと思う。真実ではないのは、そうしたことが真実であると見抜けないわれわれ人間の認識そのものにある。ユダヤ教の神、キリスト教の神、イスラム教の神、ヒンヅー教や神道の神など、さまざまな神が存在しているということ自体が、神は「ひとつ」であることを証明しているのではないだろうか。そのことを見抜けず、「一神教だけが真実で多神教を説く宗教は間違っている」などと言ったりする。何と皮相的で物質的なものの見方なのだろう。
神はひとつにして多であるという主張は「矛盾」している。論理的知性では。けれども、神は知性や論理で認識される存在ではない。ただ愛だけが、この言葉を何の矛盾も感じることなく認識することができるに違いない。神は愛をもってのみ認識されるのであり、そのとき神は、一にして多、多にして一になる。
宗教の名のもとに殺し合いをしている人たちは、神のことなど何もわかっていないのだと思う。真のユダヤ教徒、真のキリスト教徒、真のイスラム教徒であれば、他の宗教を否定するなんてことはあり得ない。愛し合う二人の間に、まさに「生きている」神の存在そのものを感じるからだ。