HOME>独想録>
2007年6月の独想録
6月11日 半世紀を越えてやってきた本
今日、注文していた一冊の古本が届いた。
『道徳療法』(アンリ・バリュック著)という本で、奥付をみると昭和32年出版とある(私はまだ生まれていない!)。いま執筆中の本の参考資料としてどうしても必要となり、インターネットで調べて購入したのである。
この本の要旨を述べると、善悪の判断などつかないような精神病の患者であっても、心の深い層では道徳意識というものが失われずにしっかりと残っている。患者に対して人間らしく接することにより、この道徳意識が目覚めて、精神病が治癒されるというものである。著者は重い精神病を病んで何も感じていないように見えた患者に対して、人間的に接した。そしてこの患者が正気を取り戻したとき、患者はそのときの著者の対応について、こういったという。
「この人間的な温かさこそ、私が絶えず求めていたものでした」
正気を失ったように見えていても、患者はちゃんと状況を認識していたのである。そして、著者の人間的な温かさが彼を正気に戻したのだ。
いま、私が執筆している本も、趣旨としてはこれと同じである。心理カウンセリングに関する本であるが、私の場合は、患者の「霊性」を目覚めさせることによって癒されると考えている。そのためには、哲学者ブーバーのいう「我と汝」の関係性(ひらたくいえば、“愛の関係性”)を築くことであると。この主張を裏付けるような研究や資料を探していたところ、今回のこの本が見つかったのだ。
患者に対して、人間的に接するということは、現在の医療ではもっとも欠如していることではないだろうか。3時間も待たされたあげく、診察に入っても、ろくに話も聞いてもらえず顔も見てもらえず、10分ほどで薬をもらっておしまいである。これは医師に責任があるというより、医療制度の問題なのであるが、医師に問題があるときも少なくない。患者をモノ扱いにしているような医師もいる。機械を修理するためには、相手にどう接しようと同じである。どう接するかなど、治療の効果とは関係がないと思っている医療関係者もまだまだ多いようだ。たとえ、知識としてはわかっていても、そうした関係性というものは、スキルの問題よりも人間性の問題だから、実践するということは非常に難しい。
しかし、患者と人間的な関係を築くことによって、患者の生命力は強化され、患者は癒される方向に進んでいくのである。これは疑いようもない事実なのだ。
このことは、すでにこの古本が出版された時代から啓蒙されてきていることなのに、いまだにそれが社会的な通説となっていないことには、非常に残念なものがある。しかし、このことはなんとしても訴えていかなければならない。いま書いている本で、そのことを全面的に主張したいと思っている。
それにしても、 私は運がいいというのか、「こういう資料が欲しい」と思っていると、いつのまにか導かれるようにその資料を見つけるということがよくある。今回もそんな感じだった。私が本を探すというより、本が私を捜してやってきてくれたような印象さえもつこともある。
この著者のまえがきの最後に書かれた日付を見て驚いた。
1957年6月11日とある。
すなわち、著者はちょうど50年前の今日、この本を仕上げたことになる。
私には、この本が半世紀後に私のもとに来る運命をもっていたように感じられた。そしていま、ついにその出会いが果たせたのであると。
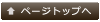
6月21日 最初が肝心……しかし
人間というものは、最初の体験がどんなものであったかによって、これから先、その分野でうまくやっていけるかどうかが、大きく変わってしまうように思われる。
たとえば、初めて英語の授業を受けたとき、ちょっとした失敗をして恥をかき、クラスで笑い者にされたとしよう。するともう、英語というものが嫌いになって、英語の能力において大きな進歩が期待できなくなってしまったりする。逆に、最初にちょっとうまくいって先生からほめられたりすると、英語が好きになり、英語の能力がどんどんと伸びていくに違いない。
人生というものは、ちょっとした成功や、ちょっとした失敗の連続であり、そのどちらになるかはちょっとした運によることが大きい。どんなに得意な分野であっても、失敗したりうまくいかないといったことは常にあることだ。けれども、最初にうまくいったか、うまくいかなかったかで、その後の流れが大きく変わってしまう。その意味では、最初というものは大切である。
また、どんなに自分自身がすぐれたものをもっていても、それを理解してくれる環境にいるかどうか、といったことも、その後の人生を大きく変えてしまう原因にもなる。
たとえば、個人主義的な生き方を好む性格の人は、地方の田舎では住みにくいということがよくある。地方の田舎は、隣近所のつきあいが濃密で、町や村の行事などがいつも行われ、それに参加しなければ、悪口をいわれ、村八分にされたりして、実質的に住んでいられなくなるといったことがある。
その場所に住んでいれば、その場所が世界となるから、そこで人から嫌われれば、まるで全世界から嫌われているような感覚をもってしまうかもしれない。世の中のすべての人が自分を嫌っているのだ、自分は嫌われるような人間なのだ……といった、極端な思いこみをして自信を失ってしまうかもしれない。
しかしながら、たとえば芸術家や作家といった人たちは、自分の内面を大切にして人づきあいがよくない人が多いように思われる。そのため、芸術家や作家の資質を理解しない環境に住んでいると、せっかくの才能や可能性の芽がつぶされてしまうこともあるだろう。それは何というもったいないことだろう。
その意味では、自分の内面世界を大切にする人は、都会に住んだ方がいいかもしれない。都会はいい意味でも悪い意味でも個人主義的で、隣人がどんなライフスタイルを営もうと無関心である。もしも可能なら、パリのような都会に住んだ方がもっといいかもしれない。聞くところによれば、パリという街は芸術家を尊重し、芸術家の考えやライフスタイルをよく理解して励ましてくれるところのようだ。
お金よりも精神性を重んじる人は、お金や物質的豊かさを至上価値と考える社会や世界に身をおいたら、無能扱いされ軽蔑されるだろう。しかし、マザーテレサの施設のように、むしろ物質的なものを所有している人が軽蔑されるような世界に身をおけば、この人は尊敬され評価されることだろう。
いずれにしろ、一番最初にうまくいくか、いかないかなどは、たまたま運がよかったとか悪かったとか、その程度のつまらない理由が大部分なのだ。そんなことで、ある種の「洗脳」をされてしまう。だから、もし何かに対して自分はうまくやれないといったコンプレックスをもっているとしたら、たいていは最初にたまたまうまくいったか、たまたまうまくいかなかったかといった、深い根拠など何もない、つまらないことなのだと思って、洗脳を解き、心を新たに再チャレンジするべきである。
さらに、いくらまわりにいる人が、自分のことを認めてくれなかったとしても、それで世界のすべての人から認められないなどという妄想を抱くのも馬鹿馬鹿しいことだ。ベートーベンの音楽が理解できない人にベートーベンの音楽を聴かせても「なんて退屈なつまらない音楽だろう」というだろう。わからない人はわからないのだ。
もちろん、だからといって、ひとりよがりになってしまってはいけないが、少なくても身近に自分の価値を認めてくれる人がいないという理由だけで、自分の可能性を自ら否定してしまうような愚かなマネはしてはいけない。
何かに自信をもつにしても、劣等感をもつにしても、どのみちつまらないことがきっかけなのだから、おおげさに考えず、ちょっとでもうまくいったり、ちょっとでも自分のいいところを見つけたら、おおいに自信をもつようにしよう。
2007年6月の独想録
6月11日 半世紀を越えてやってきた本
今日、注文していた一冊の古本が届いた。
『道徳療法』(アンリ・バリュック著)という本で、奥付をみると昭和32年出版とある(私はまだ生まれていない!)。いま執筆中の本の参考資料としてどうしても必要となり、インターネットで調べて購入したのである。
この本の要旨を述べると、善悪の判断などつかないような精神病の患者であっても、心の深い層では道徳意識というものが失われずにしっかりと残っている。患者に対して人間らしく接することにより、この道徳意識が目覚めて、精神病が治癒されるというものである。著者は重い精神病を病んで何も感じていないように見えた患者に対して、人間的に接した。そしてこの患者が正気を取り戻したとき、患者はそのときの著者の対応について、こういったという。
「この人間的な温かさこそ、私が絶えず求めていたものでした」
正気を失ったように見えていても、患者はちゃんと状況を認識していたのである。そして、著者の人間的な温かさが彼を正気に戻したのだ。
いま、私が執筆している本も、趣旨としてはこれと同じである。心理カウンセリングに関する本であるが、私の場合は、患者の「霊性」を目覚めさせることによって癒されると考えている。そのためには、哲学者ブーバーのいう「我と汝」の関係性(ひらたくいえば、“愛の関係性”)を築くことであると。この主張を裏付けるような研究や資料を探していたところ、今回のこの本が見つかったのだ。
患者に対して、人間的に接するということは、現在の医療ではもっとも欠如していることではないだろうか。3時間も待たされたあげく、診察に入っても、ろくに話も聞いてもらえず顔も見てもらえず、10分ほどで薬をもらっておしまいである。これは医師に責任があるというより、医療制度の問題なのであるが、医師に問題があるときも少なくない。患者をモノ扱いにしているような医師もいる。機械を修理するためには、相手にどう接しようと同じである。どう接するかなど、治療の効果とは関係がないと思っている医療関係者もまだまだ多いようだ。たとえ、知識としてはわかっていても、そうした関係性というものは、スキルの問題よりも人間性の問題だから、実践するということは非常に難しい。
しかし、患者と人間的な関係を築くことによって、患者の生命力は強化され、患者は癒される方向に進んでいくのである。これは疑いようもない事実なのだ。
このことは、すでにこの古本が出版された時代から啓蒙されてきていることなのに、いまだにそれが社会的な通説となっていないことには、非常に残念なものがある。しかし、このことはなんとしても訴えていかなければならない。いま書いている本で、そのことを全面的に主張したいと思っている。
それにしても、 私は運がいいというのか、「こういう資料が欲しい」と思っていると、いつのまにか導かれるようにその資料を見つけるということがよくある。今回もそんな感じだった。私が本を探すというより、本が私を捜してやってきてくれたような印象さえもつこともある。
この著者のまえがきの最後に書かれた日付を見て驚いた。
1957年6月11日とある。
すなわち、著者はちょうど50年前の今日、この本を仕上げたことになる。
私には、この本が半世紀後に私のもとに来る運命をもっていたように感じられた。そしていま、ついにその出会いが果たせたのであると。
6月21日 最初が肝心……しかし
人間というものは、最初の体験がどんなものであったかによって、これから先、その分野でうまくやっていけるかどうかが、大きく変わってしまうように思われる。
たとえば、初めて英語の授業を受けたとき、ちょっとした失敗をして恥をかき、クラスで笑い者にされたとしよう。するともう、英語というものが嫌いになって、英語の能力において大きな進歩が期待できなくなってしまったりする。逆に、最初にちょっとうまくいって先生からほめられたりすると、英語が好きになり、英語の能力がどんどんと伸びていくに違いない。
人生というものは、ちょっとした成功や、ちょっとした失敗の連続であり、そのどちらになるかはちょっとした運によることが大きい。どんなに得意な分野であっても、失敗したりうまくいかないといったことは常にあることだ。けれども、最初にうまくいったか、うまくいかなかったかで、その後の流れが大きく変わってしまう。その意味では、最初というものは大切である。
また、どんなに自分自身がすぐれたものをもっていても、それを理解してくれる環境にいるかどうか、といったことも、その後の人生を大きく変えてしまう原因にもなる。
たとえば、個人主義的な生き方を好む性格の人は、地方の田舎では住みにくいということがよくある。地方の田舎は、隣近所のつきあいが濃密で、町や村の行事などがいつも行われ、それに参加しなければ、悪口をいわれ、村八分にされたりして、実質的に住んでいられなくなるといったことがある。
その場所に住んでいれば、その場所が世界となるから、そこで人から嫌われれば、まるで全世界から嫌われているような感覚をもってしまうかもしれない。世の中のすべての人が自分を嫌っているのだ、自分は嫌われるような人間なのだ……といった、極端な思いこみをして自信を失ってしまうかもしれない。
しかしながら、たとえば芸術家や作家といった人たちは、自分の内面を大切にして人づきあいがよくない人が多いように思われる。そのため、芸術家や作家の資質を理解しない環境に住んでいると、せっかくの才能や可能性の芽がつぶされてしまうこともあるだろう。それは何というもったいないことだろう。
その意味では、自分の内面世界を大切にする人は、都会に住んだ方がいいかもしれない。都会はいい意味でも悪い意味でも個人主義的で、隣人がどんなライフスタイルを営もうと無関心である。もしも可能なら、パリのような都会に住んだ方がもっといいかもしれない。聞くところによれば、パリという街は芸術家を尊重し、芸術家の考えやライフスタイルをよく理解して励ましてくれるところのようだ。
お金よりも精神性を重んじる人は、お金や物質的豊かさを至上価値と考える社会や世界に身をおいたら、無能扱いされ軽蔑されるだろう。しかし、マザーテレサの施設のように、むしろ物質的なものを所有している人が軽蔑されるような世界に身をおけば、この人は尊敬され評価されることだろう。
いずれにしろ、一番最初にうまくいくか、いかないかなどは、たまたま運がよかったとか悪かったとか、その程度のつまらない理由が大部分なのだ。そんなことで、ある種の「洗脳」をされてしまう。だから、もし何かに対して自分はうまくやれないといったコンプレックスをもっているとしたら、たいていは最初にたまたまうまくいったか、たまたまうまくいかなかったかといった、深い根拠など何もない、つまらないことなのだと思って、洗脳を解き、心を新たに再チャレンジするべきである。
さらに、いくらまわりにいる人が、自分のことを認めてくれなかったとしても、それで世界のすべての人から認められないなどという妄想を抱くのも馬鹿馬鹿しいことだ。ベートーベンの音楽が理解できない人にベートーベンの音楽を聴かせても「なんて退屈なつまらない音楽だろう」というだろう。わからない人はわからないのだ。
もちろん、だからといって、ひとりよがりになってしまってはいけないが、少なくても身近に自分の価値を認めてくれる人がいないという理由だけで、自分の可能性を自ら否定してしまうような愚かなマネはしてはいけない。
何かに自信をもつにしても、劣等感をもつにしても、どのみちつまらないことがきっかけなのだから、おおげさに考えず、ちょっとでもうまくいったり、ちょっとでも自分のいいところを見つけたら、おおいに自信をもつようにしよう。