HOME>独想録>
2008年3月の独想録
3月11日 品格とは何か?
書店をのぞくと、最近、『○○の品格』というタイトルの本が目立つ。国家の品格、日本人の品格、女性の品格、男の品格、親の品格、父親の品格、母の品格、人間の品格、大人の品格、子供の品格、高校生の品格、政治家の品格、総理の品格、社長の品格、上司の品格、魔女子の品格(?)、ヤマダ電機の品格、池田大作の品格、朝めしの品格・・・・、他にもまだまだある。ちなみに、私が読んだのは『国家の品格』だけだ。
これくらい品格ということがいわれ、本になっているということは、品格に欠ける人や物事が多いということ、それに対して「それではいけない」と多くの人々が思っていることを示しているのだろう。
この、いわば品格ブームともいうべきものが、かつてバブルの全盛期に、日本人が海外から「エコノミック・アニマル」と呼ばれていた時代に、流行して欲しかったと思う。もっとも、あのときに品格を説くような本を出したとしても、おそらく売れなかったに違いない。それまでは「忍耐や勤勉」を子供や若者に教え、「汗水たらして働くのが美徳だ」などといっていた当時の中高年層さえもが、競って株を買いあさり、率先してマネー・ゲームに狂っていたのだから。
きっと、そんな中高年層も、バブルが来るまでは「品格」があったのだろう。少なくても、自分たちには品格があったと信じていたに違いない。しかし、その品格がただのメッキに過ぎなかったことが、バブルによって明らかになってしまったのだ。結局、バブルの崩壊によって、人々の多くは金も品格も失ってしまった。しかも今さら「品格」を説くわけにもいかず、結局は醜態をさらしたまま、社会から退いていったのである。
そうして、骨のあるりんとした年長者がいなくなったから(もともといなかったことがバレたから)、若者たちはクラゲのように、忍耐して何かを貫くという気概を失い、嫌なことはしたくない、その日さえ楽しければいい、自分さえよければいいといった考えをもつようになり、そうした価値観をもった若者が親になった現在、ニートのような子供をたくさん生み出すことになったのではないだろうか(もちろん、それだけが原因のすべてではないだろうけれども)。
ところで、そもそも品格とは何なのだろうか?
辞書で引いてみると、「なんとなくただよう上品さ」といったように説明されている。「格」という文字は、「人格」という言葉にも使われているように、ある種の雰囲気のような意味があるようだ。
したがって、ただ上品なだけでは「品格」にはならないのだ。もし上品というだけであれば、テクニックを学べば誰でも上品にはなれる。たとえば、テーブル・マナーの講習会を受ければ、誰でも食事が上品にできるようになる。言葉使いや振る舞いを注意すれば、誰でも上品になれる。
しかし、それだけでは「品格」というものは出てこない。
品格がある人は、とくに自分が上品であることをアピールしなくても、どことなく上品さを感じるといった人のことである。たとえ、テーブル・マナーなどまったく知らなかったとしても、上品さを感じさせる人のことであろう。
いったい、どこからそんな上品さがにじみ出ているのかといえば、結局は、人間性から来ていることは間違いない。いわば人格ということになる。品格ある人のことを人格者というのだろう。いくら口先で立派なことを言っても、それだけで品格は生まれないし、人格者にはならない。人格はテクニックの問題ではなく、結局はトータルなその人の精神と生き方によって決まるものである。
そうなると、品格を得るためにテクニックなどを学んでも無駄ということになってしまうのだろうか? 私は必ずしもそうは思わない。形から入っていくことで精神も変わるということはある。第一、「品格ある人になろう」という気持ちをもって努力をしていること自体、すでにある程度の品格が備わっている証拠だと思う。本当にどうしようもなく品格の欠けた人は、そもそも品格をもとうなどとは思わないだろうし、品格という言葉そのものに何の関心ももたないだろう。
しかしそれでもやはり、テクニックそのものが品格をもたらしてくれるのではない。
この場合、自らに問うてみなければならないことがある。
それは、「品格を身につけて、何かいいことでもあるのか?」という問いである。まるで何かの資格でも取得するかのように、品格を身につけておけばトクをすることがあるのだろうか?
品格を身につけておけば、トクをすることはたくさんある。品格が高ければ、自然と品格が高い人と縁ができるし(類は友を呼ぶ)、品格が高い人は裏切ることがなく誠実で、助け合いの精神に満ちているだろうから、交際していれば、トクをすることはたくさんあるだろう。
しかし、トクをするからという動機で品格を身につけようとしても、おそらく真の品格は養えない。品格というものは、そうした打算を超えたところにある。品格それ自体のために品格を養うこと、その他にはいかなる損得勘定も入れないこと、まさにそんな精神にのみ品格は宿る。
あえていえば、それは芸術家が純真な気持ちで芸術作品を創作する気持ちに近いのかもしれない。真の芸術家はお金や名声のために作品を創作しているのではない。美しいもの、感動するものを生み出すこと、そのものが喜びなのだ。同じように、自分を品格ある人間にさせようとする努力とは、自分自身が芸術家であると同時に作品になることだ。彫刻家になると同時に、彫刻される石になることだ。芸術作品を創造していくような感覚で自分を彫り続け、磨き続けていくのである。
しかし、自分を彫り磨くことは、必ずしも楽しいとは限らない。単なる固まりの石に刀を入れて削ぎ落とすようなものだ。それには当然、痛みを伴う。「私はありのままでいたい、ありのままの自分を認めてくれなければ嫌だ」などといって形が変わるのを拒む無骨な石の固まりを、いったい誰が感動をもって賛美したりするだろう。何度も何度も体を刃物で切り取られる苦痛に耐えてこそ優美な形となり、ヤスリで磨かれる苦痛に耐えてこそ光沢が出る。そうして見事な彫像が生まれるのだ。彫像は何もいわないが、そこに在るというだけで、周囲の人に感動を与える。まさに品格がそこにある。そんな「作品」に、人々は感動して賛美する。
品格が形成されるときというのは、苦痛を感じるときである。
その苦痛には二つの種類がある。ひとつは、辛いことに耐える苦痛であり、もうひとつは快楽に耐える苦痛だ。辛い体験はいうまでもなく苦痛であるが、目の前に快楽があるのに、その快楽が自分を下品にしてしまうならば断固としてその誘惑をはねつけることも、非常な苦痛を伴うものである。
しかし、品格を養うには、この二つの苦痛を何度も何度も乗り越えていかなければならないのだろう。もちろん、だからといって、やたらに苦しめばいいということではないだろう。必要ではない苦痛は避けるべきだし、自分を下品にさせない快楽なら受け入れて楽しめばいい。
幸運なときは誰だって品格をもつことができる(もっているように見せることができる)。しかし、それが本物かどうかは、辛い経験をしたとき、悪しき快楽を前にしたときにわかる。苦しみにおかれようと快楽におかれようと、変わらずに責任を果たし、義務を履行し、姑息な手段に訴えることなく、誠実さを貫き、ごまかしたりせず、逃げたりせず、みっともないことをせずに、ひたすら天(神)が望んでいるであろうと信じることをする、断固としてそれをやり抜く、そんな生き方をしてきた人だけが、おそらく本当の品格というものをつかむことになるのだろう。
その意味でいえば、苦難は品格を養うための絶好のチャンスだ。快楽もまた、品格を養うための絶好のチャンスである。だがそれは、これまで培ってきた品格をいっぺんにだいなしにしてしまう危険なワナでもある。
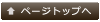
3月25日 平気で人を殺す人の心理
先日、駅の構内で、ナイフで八人が殺傷された事件が起きた。犯人は二十代の若者で、以前に老人を殺害して指名手配されていた。「誰でもいいから人を殺したかった」というのが動機だという。今年の1月くらいから人が殺したくなってきたのだそうだ。
今日、ニュースで犯人の少年時代の様子を報道していたが、それを見た限りでは、特に異常なところがあったようには思えない、ごく普通の少年だった。
もしアメリカのように誰もが銃をもてるような社会だったら、おそらくナイフではなくて銃で人を殺していたのではないかと思われた。だとしたら、犠牲者はもっと増えていたに違いない。日本の銃規制の厳しさに感謝したい。
今回の場合、あきらかに精神がおかしくて殺人を犯したわけではなさそうだ。もちろん、このような異常なことをしたのだから、まともな精神ではないのだろうが、いわゆる「精神病」の範疇にはおそらく入っていないように思われる。つまり、病理学的には正常な人が、「人を殺したくなった」という理由で平気で人を殺しているのだ。いったい、このような心理を、どのように理解したらいいのだろうかと、考えざるをえなかった。今後、このような人が増えていってしまうのだろうか?
今回のような重大な事件ではないが、カミソリのようなもので女の子を切りつけるとか、そういう事件が最近、多くなったように思う。誰かが憎くて傷つけるのではないのだ。ある種の遊び感覚、快楽を目的に、そのようなことをしているわけである。仮に、そのような行為をしてみたくなったとしても、「それはいけないことだ」という気持ちが働いて、自制できないのだろうか?
ひとつ、興味深いことは、こうした無差別殺人のようなことをした犯人は、逮捕されて死刑を宣告される可能性があるとしても、それをあまり怖れていない、ということがしばしば見られることだ。なかには「自分を死刑にしてくれ」と希望する者もあるようだし、アメリカでは銃乱射などをした後に、たいてい犯人は自殺をしている。
つまり、他人が死ぬのも自分が死ぬのも、そう深刻なことだと思っていないような印象を受けるのである。いったいどうして、このような感覚になってしまったのだろうか?
生命というものが軽く感じられてしまう状況というのは、たとえば戦争などがそうだ。戦場で敵も味方も虫けらのように殺され死んでいくのを見ていると、生命というものがそう大したことがないように感じられてくるといわれる。それは確かにそうだろう。しかし、自分が死ぬということに関しては、たとえ戦場でも、恐怖が消えることはないはずだ。ある種の覚悟や悟りのようなものを開いて死ぬことが怖くなくなるということはあり得るかもしれないが、それと、今回のような事件とは別であろう。犯人はまるで、自分が死ぬことに対してもあっけらかんとしている。
映画や漫画などでは、いつも人が殺されたり死んだりしている。人が死なない映画を見つける方が難しいくらいだ。しかも、その死に方や殺し方が、しだいに残酷で異常になってきているように思う。私たちは、そういう映画なり漫画を見ても、あまりショックを感じることはない。それはフィクションだとわかっているからなのだろうか? そうかもしれない。だが、ニュースなどで、たとえばイラクで自爆テロがあったと報道されたとき、実際に人が何人も死んでいるわけだが、それを見ても、それほどショックを受けないのではないか? つまり、フィクションか現実かということは、私たちが思うほど、実はあまり大きな要因ではないのかもしれない。
一方、戦争を体験した人たちは、ほとんど口をそろえて「戦争はしてはいけない!」と叫ぶ。実際に戦争というものを、生で体験しているから、それがいかに悲惨であるか、よくわかるのだ。だから、戦争を体験している人が、テロ事件のニュースを見たときには、そのショックはずっと大きいのではないかと思う。
しかし、実際に、私たちのほとんどは、戦争やテロ事件を体験することはない。私たちが知る戦争やテロ事件というのは、テレビ画面や新聞や本といった「平面」に映し出された画像や文字や音声だけである。実際の戦争やテロというのは、立体的な出来事なのだ。しかも、残酷なシーンなどはカットされている。死体がバラバラになり内臓があちこちに散らばっている光景が映し出されることはない。つまり、ニュースで報道される戦争だとかテロ事件といった殺人の映像なり情報は、嘘ではないが本当ではない、ということなのだ。
暴力や殺人シーンを描いた映画などは、それこそまったくリアリティに欠けている。ボクシングのようにいつまでも殴り合っていたりする。しかし、拳で誰かの頬を殴った経験がある人ならわかるかもしれないが、そんなことをしたら、よほど空手か何かで鍛えているのでない限り、指の骨を痛めたり、骨折してしまったりするのだ。殴られた方も、映画ではひるむことなく殴り返したりしているが、実際には一度でも殴られたらその痛みやショックで意識がもうろうとなり、しばらくは顔を手で押さえて何もできなくなってしまう。これが現実である。さらに荒唐無稽な映画になると、主人公が二発も三発も銃で撃たれているのに、平気で応戦したりしている(悪者は一発で死んでしまうのに主人公は三発も弾丸を受けても平気なのだ!)。弾丸が当たれば、まずその痛みで動きが取れなくなり力が抜けて倒れてしまうし、内臓に当たった場合は、かなり出血するので血圧が急激に低下して脳に血がいかなくなり、すぐに倒れてしまう。これが現実である。
ところが、戦争や暴力といったことを、ほとんど映画とか不完全なニュースでしか知り得ない私たちは、映画で見たことを、いつのまにか現実であると思ってしまう。少なくても、それほど現実とはかけ離れてはいないだろうと思ってしまう。真実の情報を知らないのだから、そう思うしかないわけだ。
そうして、人を殺すということも、映画のワンシーン、漫画の一こま程度の出来事くらいにしか思わなくなってくるのかもしれない。壮絶な痛みと恐怖に満ちて死んでいく人の苦しみ、愛する者がそうして殺されてしまった人たちの苦しみ、こんなことなど、何もわからなくなってしまっているのではないのか?
もちろん、映画やニュース報道が、無差別殺人の原因だというつもりはない。他にもさまざまな原因はあるだろう。しかし、映画やニュースといった現実とはかけ離れた情報を現実であるかのように錯覚してしまうことが、ああした事件を引き起こす、ひとつの要因になっているであろうことは間違いないと思う。私たちは、もっと生の体験が必要なのだ。
2008年3月の独想録
3月11日 品格とは何か?
書店をのぞくと、最近、『○○の品格』というタイトルの本が目立つ。国家の品格、日本人の品格、女性の品格、男の品格、親の品格、父親の品格、母の品格、人間の品格、大人の品格、子供の品格、高校生の品格、政治家の品格、総理の品格、社長の品格、上司の品格、魔女子の品格(?)、ヤマダ電機の品格、池田大作の品格、朝めしの品格・・・・、他にもまだまだある。ちなみに、私が読んだのは『国家の品格』だけだ。
これくらい品格ということがいわれ、本になっているということは、品格に欠ける人や物事が多いということ、それに対して「それではいけない」と多くの人々が思っていることを示しているのだろう。
この、いわば品格ブームともいうべきものが、かつてバブルの全盛期に、日本人が海外から「エコノミック・アニマル」と呼ばれていた時代に、流行して欲しかったと思う。もっとも、あのときに品格を説くような本を出したとしても、おそらく売れなかったに違いない。それまでは「忍耐や勤勉」を子供や若者に教え、「汗水たらして働くのが美徳だ」などといっていた当時の中高年層さえもが、競って株を買いあさり、率先してマネー・ゲームに狂っていたのだから。
きっと、そんな中高年層も、バブルが来るまでは「品格」があったのだろう。少なくても、自分たちには品格があったと信じていたに違いない。しかし、その品格がただのメッキに過ぎなかったことが、バブルによって明らかになってしまったのだ。結局、バブルの崩壊によって、人々の多くは金も品格も失ってしまった。しかも今さら「品格」を説くわけにもいかず、結局は醜態をさらしたまま、社会から退いていったのである。
そうして、骨のあるりんとした年長者がいなくなったから(もともといなかったことがバレたから)、若者たちはクラゲのように、忍耐して何かを貫くという気概を失い、嫌なことはしたくない、その日さえ楽しければいい、自分さえよければいいといった考えをもつようになり、そうした価値観をもった若者が親になった現在、ニートのような子供をたくさん生み出すことになったのではないだろうか(もちろん、それだけが原因のすべてではないだろうけれども)。
ところで、そもそも品格とは何なのだろうか?
辞書で引いてみると、「なんとなくただよう上品さ」といったように説明されている。「格」という文字は、「人格」という言葉にも使われているように、ある種の雰囲気のような意味があるようだ。
したがって、ただ上品なだけでは「品格」にはならないのだ。もし上品というだけであれば、テクニックを学べば誰でも上品にはなれる。たとえば、テーブル・マナーの講習会を受ければ、誰でも食事が上品にできるようになる。言葉使いや振る舞いを注意すれば、誰でも上品になれる。
しかし、それだけでは「品格」というものは出てこない。
品格がある人は、とくに自分が上品であることをアピールしなくても、どことなく上品さを感じるといった人のことである。たとえ、テーブル・マナーなどまったく知らなかったとしても、上品さを感じさせる人のことであろう。
いったい、どこからそんな上品さがにじみ出ているのかといえば、結局は、人間性から来ていることは間違いない。いわば人格ということになる。品格ある人のことを人格者というのだろう。いくら口先で立派なことを言っても、それだけで品格は生まれないし、人格者にはならない。人格はテクニックの問題ではなく、結局はトータルなその人の精神と生き方によって決まるものである。
そうなると、品格を得るためにテクニックなどを学んでも無駄ということになってしまうのだろうか? 私は必ずしもそうは思わない。形から入っていくことで精神も変わるということはある。第一、「品格ある人になろう」という気持ちをもって努力をしていること自体、すでにある程度の品格が備わっている証拠だと思う。本当にどうしようもなく品格の欠けた人は、そもそも品格をもとうなどとは思わないだろうし、品格という言葉そのものに何の関心ももたないだろう。
しかしそれでもやはり、テクニックそのものが品格をもたらしてくれるのではない。
この場合、自らに問うてみなければならないことがある。
それは、「品格を身につけて、何かいいことでもあるのか?」という問いである。まるで何かの資格でも取得するかのように、品格を身につけておけばトクをすることがあるのだろうか?
品格を身につけておけば、トクをすることはたくさんある。品格が高ければ、自然と品格が高い人と縁ができるし(類は友を呼ぶ)、品格が高い人は裏切ることがなく誠実で、助け合いの精神に満ちているだろうから、交際していれば、トクをすることはたくさんあるだろう。
しかし、トクをするからという動機で品格を身につけようとしても、おそらく真の品格は養えない。品格というものは、そうした打算を超えたところにある。品格それ自体のために品格を養うこと、その他にはいかなる損得勘定も入れないこと、まさにそんな精神にのみ品格は宿る。
あえていえば、それは芸術家が純真な気持ちで芸術作品を創作する気持ちに近いのかもしれない。真の芸術家はお金や名声のために作品を創作しているのではない。美しいもの、感動するものを生み出すこと、そのものが喜びなのだ。同じように、自分を品格ある人間にさせようとする努力とは、自分自身が芸術家であると同時に作品になることだ。彫刻家になると同時に、彫刻される石になることだ。芸術作品を創造していくような感覚で自分を彫り続け、磨き続けていくのである。
しかし、自分を彫り磨くことは、必ずしも楽しいとは限らない。単なる固まりの石に刀を入れて削ぎ落とすようなものだ。それには当然、痛みを伴う。「私はありのままでいたい、ありのままの自分を認めてくれなければ嫌だ」などといって形が変わるのを拒む無骨な石の固まりを、いったい誰が感動をもって賛美したりするだろう。何度も何度も体を刃物で切り取られる苦痛に耐えてこそ優美な形となり、ヤスリで磨かれる苦痛に耐えてこそ光沢が出る。そうして見事な彫像が生まれるのだ。彫像は何もいわないが、そこに在るというだけで、周囲の人に感動を与える。まさに品格がそこにある。そんな「作品」に、人々は感動して賛美する。
品格が形成されるときというのは、苦痛を感じるときである。
その苦痛には二つの種類がある。ひとつは、辛いことに耐える苦痛であり、もうひとつは快楽に耐える苦痛だ。辛い体験はいうまでもなく苦痛であるが、目の前に快楽があるのに、その快楽が自分を下品にしてしまうならば断固としてその誘惑をはねつけることも、非常な苦痛を伴うものである。
しかし、品格を養うには、この二つの苦痛を何度も何度も乗り越えていかなければならないのだろう。もちろん、だからといって、やたらに苦しめばいいということではないだろう。必要ではない苦痛は避けるべきだし、自分を下品にさせない快楽なら受け入れて楽しめばいい。
幸運なときは誰だって品格をもつことができる(もっているように見せることができる)。しかし、それが本物かどうかは、辛い経験をしたとき、悪しき快楽を前にしたときにわかる。苦しみにおかれようと快楽におかれようと、変わらずに責任を果たし、義務を履行し、姑息な手段に訴えることなく、誠実さを貫き、ごまかしたりせず、逃げたりせず、みっともないことをせずに、ひたすら天(神)が望んでいるであろうと信じることをする、断固としてそれをやり抜く、そんな生き方をしてきた人だけが、おそらく本当の品格というものをつかむことになるのだろう。
その意味でいえば、苦難は品格を養うための絶好のチャンスだ。快楽もまた、品格を養うための絶好のチャンスである。だがそれは、これまで培ってきた品格をいっぺんにだいなしにしてしまう危険なワナでもある。
3月25日 平気で人を殺す人の心理
先日、駅の構内で、ナイフで八人が殺傷された事件が起きた。犯人は二十代の若者で、以前に老人を殺害して指名手配されていた。「誰でもいいから人を殺したかった」というのが動機だという。今年の1月くらいから人が殺したくなってきたのだそうだ。
今日、ニュースで犯人の少年時代の様子を報道していたが、それを見た限りでは、特に異常なところがあったようには思えない、ごく普通の少年だった。
もしアメリカのように誰もが銃をもてるような社会だったら、おそらくナイフではなくて銃で人を殺していたのではないかと思われた。だとしたら、犠牲者はもっと増えていたに違いない。日本の銃規制の厳しさに感謝したい。
今回の場合、あきらかに精神がおかしくて殺人を犯したわけではなさそうだ。もちろん、このような異常なことをしたのだから、まともな精神ではないのだろうが、いわゆる「精神病」の範疇にはおそらく入っていないように思われる。つまり、病理学的には正常な人が、「人を殺したくなった」という理由で平気で人を殺しているのだ。いったい、このような心理を、どのように理解したらいいのだろうかと、考えざるをえなかった。今後、このような人が増えていってしまうのだろうか?
今回のような重大な事件ではないが、カミソリのようなもので女の子を切りつけるとか、そういう事件が最近、多くなったように思う。誰かが憎くて傷つけるのではないのだ。ある種の遊び感覚、快楽を目的に、そのようなことをしているわけである。仮に、そのような行為をしてみたくなったとしても、「それはいけないことだ」という気持ちが働いて、自制できないのだろうか?
ひとつ、興味深いことは、こうした無差別殺人のようなことをした犯人は、逮捕されて死刑を宣告される可能性があるとしても、それをあまり怖れていない、ということがしばしば見られることだ。なかには「自分を死刑にしてくれ」と希望する者もあるようだし、アメリカでは銃乱射などをした後に、たいてい犯人は自殺をしている。
つまり、他人が死ぬのも自分が死ぬのも、そう深刻なことだと思っていないような印象を受けるのである。いったいどうして、このような感覚になってしまったのだろうか?
生命というものが軽く感じられてしまう状況というのは、たとえば戦争などがそうだ。戦場で敵も味方も虫けらのように殺され死んでいくのを見ていると、生命というものがそう大したことがないように感じられてくるといわれる。それは確かにそうだろう。しかし、自分が死ぬということに関しては、たとえ戦場でも、恐怖が消えることはないはずだ。ある種の覚悟や悟りのようなものを開いて死ぬことが怖くなくなるということはあり得るかもしれないが、それと、今回のような事件とは別であろう。犯人はまるで、自分が死ぬことに対してもあっけらかんとしている。
映画や漫画などでは、いつも人が殺されたり死んだりしている。人が死なない映画を見つける方が難しいくらいだ。しかも、その死に方や殺し方が、しだいに残酷で異常になってきているように思う。私たちは、そういう映画なり漫画を見ても、あまりショックを感じることはない。それはフィクションだとわかっているからなのだろうか? そうかもしれない。だが、ニュースなどで、たとえばイラクで自爆テロがあったと報道されたとき、実際に人が何人も死んでいるわけだが、それを見ても、それほどショックを受けないのではないか? つまり、フィクションか現実かということは、私たちが思うほど、実はあまり大きな要因ではないのかもしれない。
一方、戦争を体験した人たちは、ほとんど口をそろえて「戦争はしてはいけない!」と叫ぶ。実際に戦争というものを、生で体験しているから、それがいかに悲惨であるか、よくわかるのだ。だから、戦争を体験している人が、テロ事件のニュースを見たときには、そのショックはずっと大きいのではないかと思う。
しかし、実際に、私たちのほとんどは、戦争やテロ事件を体験することはない。私たちが知る戦争やテロ事件というのは、テレビ画面や新聞や本といった「平面」に映し出された画像や文字や音声だけである。実際の戦争やテロというのは、立体的な出来事なのだ。しかも、残酷なシーンなどはカットされている。死体がバラバラになり内臓があちこちに散らばっている光景が映し出されることはない。つまり、ニュースで報道される戦争だとかテロ事件といった殺人の映像なり情報は、嘘ではないが本当ではない、ということなのだ。
暴力や殺人シーンを描いた映画などは、それこそまったくリアリティに欠けている。ボクシングのようにいつまでも殴り合っていたりする。しかし、拳で誰かの頬を殴った経験がある人ならわかるかもしれないが、そんなことをしたら、よほど空手か何かで鍛えているのでない限り、指の骨を痛めたり、骨折してしまったりするのだ。殴られた方も、映画ではひるむことなく殴り返したりしているが、実際には一度でも殴られたらその痛みやショックで意識がもうろうとなり、しばらくは顔を手で押さえて何もできなくなってしまう。これが現実である。さらに荒唐無稽な映画になると、主人公が二発も三発も銃で撃たれているのに、平気で応戦したりしている(悪者は一発で死んでしまうのに主人公は三発も弾丸を受けても平気なのだ!)。弾丸が当たれば、まずその痛みで動きが取れなくなり力が抜けて倒れてしまうし、内臓に当たった場合は、かなり出血するので血圧が急激に低下して脳に血がいかなくなり、すぐに倒れてしまう。これが現実である。
ところが、戦争や暴力といったことを、ほとんど映画とか不完全なニュースでしか知り得ない私たちは、映画で見たことを、いつのまにか現実であると思ってしまう。少なくても、それほど現実とはかけ離れてはいないだろうと思ってしまう。真実の情報を知らないのだから、そう思うしかないわけだ。
そうして、人を殺すということも、映画のワンシーン、漫画の一こま程度の出来事くらいにしか思わなくなってくるのかもしれない。壮絶な痛みと恐怖に満ちて死んでいく人の苦しみ、愛する者がそうして殺されてしまった人たちの苦しみ、こんなことなど、何もわからなくなってしまっているのではないのか?
もちろん、映画やニュース報道が、無差別殺人の原因だというつもりはない。他にもさまざまな原因はあるだろう。しかし、映画やニュースといった現実とはかけ離れた情報を現実であるかのように錯覚してしまうことが、ああした事件を引き起こす、ひとつの要因になっているであろうことは間違いないと思う。私たちは、もっと生の体験が必要なのだ。