HOME>独想録>
2008年7月の独想録
7月4日 歳を取るということ
歳をとれば、いろいろと不都合なことが生じてくる。なかでも、心身の機能が衰えてくるほど、イヤなものはない。まず感じるのは、体力が落ち、疲れがなかなか回復しなくなることで、次に近くが見えにくくなることだ。その他、容姿の衰えもイヤなものである。もはや、若さの美貌ゆえにチヤホヤされることはなくなってしまう。
身体の自由がきかなくなると、やりたいことも制限されてくるのが辛い。海外旅行などもあまり大変な場所へは行けなくなるし、スポーツだって激しいものはできなくなる。美味しいものを食べたり酒を飲むということも制限される。ちょっとしたことで病気になりやすくなり、怪我もしやすくなる。そのため常に病院に通ったり薬を飲まなければならなくなる。
しかも、こうした身体的な不都合だけでなく、歳をとると、他にもイヤなことがたくさん増えてくる。
まず、就職先がなくなってくる。十分な蓄えがある人はいいが、そうでなければ、常に職を失うことの不安につきまとわれる。
また、親は先に死んでしまうので、もはや経済的にも精神的にも頼れる人がいなくなってくる。アパートを借りようにも、保証人がいなくなるので、借りることも難しくなってくる。
友達もいなくなってくる。すでに死んでしまった友人も多くなるし、交際範囲も狭くなるから出会う機会もない。ひどい場合は、配偶者や子供などの家族も、いなくなってしまうことがある。
さらに、たいていの場合、年寄りは嫌われる。子供や若い人たちは、どこへ行っても歓迎してくれるが、年寄りはあまり歓迎されない。ときにはかなり露骨に、やっかいもの扱いされることがある。
きわめつけは、寝たきりになってしまうことだ。下の世話をされることは、する方もイヤだろうが、される方だって、尊厳が傷つけられてイヤなものなのだ。そのうえ、部屋が臭いとかいわれて嫌われる。ついには壁の向こうから「いい加減に早く死んでくれないかしら」などという声が聞こえてきたりする。
それでもまだ、お金がたくさんあればいい。お金がない老人ほど惨めなものはないだろう。ヘルパーも満足に来てもらえず、家族からも単なる「穀潰し」「やっかいもの」とされてしまう。ひとり貧しく狭い部屋で、病気になっても誰からも気づいてもらえず、孤独にひとり死んでいくことになるかもしれない。
このように、歳をとるということは、まさに踏んだり蹴ったりの状態になることだ。
こんな現実を、いったいどのように受け入れていけばいいというのだろう。若いときのような、豊かな感受性をそのまま維持していたら、それこそ気も狂わんばかりの拷問ではないだろうか。
そこで、ぼけてしまう、という「癒し手」が忍び寄ってくるのかもしれない。ぼけてしまうことを多くの人は恐れているが、しかし、ぼけて、自分がおかれた悲惨な状況を理解できなくなれば、心の平安を得られるかもしれない。ぼけてしまうことは、まさに恩恵なのかもしれない。
けれども、それでもなお、ぼけてしまうこと自体が、人間の尊厳が失われていくような気がして、ぼけることだけは避けたいと思う。たとえ老いの厳しさに苛まれるとしても。
ならば、いったいどうすれば、老いても幸せでいられるのだろうか?
そのためには、まず健康であること、現役時代に仕事が順調に運んで退職金と年金がもらえ蓄えも十分にあり、自分の家を所有してローンがないこと、結婚して子供が生まれ、その子供がまともに育って孫をもうけること、配偶者も健康で元気なこと、しかも夫婦円満であること、家の中には子供夫婦と孫が同居し、親孝行な子供と孫から、敬愛されること、自分のことを慕って訪ねてくる友人や仲間がいること、そして死ぬときは、寝たきりになることなく、ぽっくりと逝くこと・・・だ。
だが、こんな条件をすべて満たした人が、世の中にどれくらいいるというのか?
それでも、こうした辛い老いの状況において、少なくてもひとつだけ、「よいこと」がある。それは、死を怖れなくなることだ。それどころか、早く死が訪れてこの辛い状況から解放してくれないかなと望むようになるかもしれない。若いときや、未来に希望をもって充実して生きているときは、死は恐ろしく、何としても避けたい恐怖であろう。死の恐怖を克服することは容易なことではない。
だが、悲惨で孤独な老後を生きていれば、その死が、何よりも甘美な「癒し手」のようにさえ思えてくる。そうして死の恐怖を克服できることが、辛い老いを生きることの、かけがえのない報酬なのかもしれない。
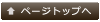
7月10日 功徳のバーゲン・セール
テレビのニュースを見ていたら、浅草の浅草寺が映っており、たくさんの人がお参りにやってくる光景が見えた。なんでも、7月の10日は、この日にお参りすれば、四万八千日お参りしたのと同じ功徳が得られるという。
このような民間信仰の言い伝えに、いちいち目くじらを立てることも大人げないのかもしれないが、このニュースを見て、バーゲン・セールや、悪徳商法の手口を連想してしまった。
「本日限り、だいこんが半額!」
「えびの養殖事業にいま投資すればもうかります。チャンスは今だけです!」
一日だけお参りすれば、本当に四万八千日お参りしたのと同じ功徳がもらえるのだったら、誰も苦労はしない。もし、本当にここに二人の人がいて、ひとりは四万八千日、熱心にお参りして、もう一方は7月10日に一日だけお参りしただけであるとして、この二人が同じ功徳だとしたら、人生に修行もなにもあったものではない。仏教が説く法(ダルマ=宇宙の法則)では、本当にそんなことを認めているのか? だとしたら、正直にコツコツ努力する者は馬鹿者ということになる。
あるいは、そんなことはないというのなら、仏教では嘘が行われていることになる。嘘をつくことは、仏教の戒律では、虚妄罪科にあたるはずである。戒律を破っていることになる。
私からいわせると、このような「むしのいい」話は、日本に限ったことではない。チベット仏教の寺院などへ行くと、くるくると回転する鐘のようなものがあり、それを一回まわすだけで、マントラを数多く唱えたのと同じ功徳があるといっている。それで、僧や在家信者などが一生懸命にその鐘みたいなものをくるくると回している。
宗教とは、日常生活から遊離してはならないが、それでも日常的な世俗の塵から離れたものをもっていなければならないと、私は思う。仏教の象徴である蓮の花が、汚泥の上に咲くが花そのものは汚泥にまったく汚れないように。
このように、世俗から超然とした、清らかで聖なる領域があるからこそ、宗教に慰めや魂の救いが求められるのではないだろうか。世俗では正直者がバカをみるし、不条理なことが起こるし、権力や金持ちだけがいいめをみるようなことがまかり通り、ちゃっかりと人をだしぬいてうまいことしてトクをしたりとか、汗水たらしてお金を稼ぐよりギャンブルや投資でもうけて醜い傲慢さを発揮するとか、打算ばかりで真心がないとか、陰で人を苦しめているような人間が成功や幸運に恵まれるとか、そういう不公平で汚いことだらけなのだから、せめて宗教だけでも、そうしたこととは無縁の、清らかな純粋性を保っていて欲しいものだ。
だからこそ、宗教に魂の救いを求めようという気にもなる。だからこそ、宗教を信じることで、世俗ではずるい生き方をした方がトクであるとしても、自分だけはそんなことはせずに正直にまっとうに生きようという気持ちにもなるのではないか?
そのような純粋性を人に教えるはずの宗教が、「功徳のバーゲン・セール」のような俗っぽいことを説いて、いったいどうするのだろうと思う。
もちろん、世の中には、非常に辛い状況にある人がいる。そんな人はわらをもすがろうという気持ちであろう。たとえば、家族に病人がいて、その病気を治してあげたいという思いで、功徳のある7月10日の今日、お参りに来るという人もいるかもしれない。
もし、本気で功徳があると信じるならば、それが暗示になって、本当によいことが起こるかもしれない。結果的には、確かに功徳があったということになる。
しかし、病気を治したいためにお参りにくる、つまり、神仏に救いを求めるというのであれば、要するに、病気を治してくれるなら、神仏でなくてもいいわけだ。貧乏を救ってくれるなら、神仏でなくてもいいわけだ。他に悩みを解決してくれるものがないから、仕方なく、神仏にお参りに来るということであろう。
賽銭箱にお金を入れて「願いを叶えてください」と祈るのは、要するに、自動販売機にお金を入れて商品を手に入れようとする発想と、まるで変わらない。
人間は弱いから、病気や貧乏を助けてくださいと神仏にお願いするのは、無理もないことであるし、決して悪いことではないとは思う。神仏は慈悲に満ちているだろうから、人間のそういうことも理解してくれるはずだ。
しかし、もし、それだけしかしないのであれば、それは信仰でもなんでもない。単なる「商取引」をしているに過ぎない。
宗教の本当の目的は、そういう世俗的なことから超然とする高い心境を開発することではないだろうか。「7月10日は功徳のバーゲンセールをしますよ!」などといわれても、そんなことをよしとしない、潔い境地を得ることではないのだろうか?
それなのに、宗教が率先して、いかにも世の中には、「うまい話」があるかのようなことを説き、むしのいい欲望を煽って、悪徳商法にだまされるようなカモを養成するようなことをして、いったいどうするのだろう。
2008年7月の独想録
7月4日 歳を取るということ
歳をとれば、いろいろと不都合なことが生じてくる。なかでも、心身の機能が衰えてくるほど、イヤなものはない。まず感じるのは、体力が落ち、疲れがなかなか回復しなくなることで、次に近くが見えにくくなることだ。その他、容姿の衰えもイヤなものである。もはや、若さの美貌ゆえにチヤホヤされることはなくなってしまう。
身体の自由がきかなくなると、やりたいことも制限されてくるのが辛い。海外旅行などもあまり大変な場所へは行けなくなるし、スポーツだって激しいものはできなくなる。美味しいものを食べたり酒を飲むということも制限される。ちょっとしたことで病気になりやすくなり、怪我もしやすくなる。そのため常に病院に通ったり薬を飲まなければならなくなる。
しかも、こうした身体的な不都合だけでなく、歳をとると、他にもイヤなことがたくさん増えてくる。
まず、就職先がなくなってくる。十分な蓄えがある人はいいが、そうでなければ、常に職を失うことの不安につきまとわれる。
また、親は先に死んでしまうので、もはや経済的にも精神的にも頼れる人がいなくなってくる。アパートを借りようにも、保証人がいなくなるので、借りることも難しくなってくる。
友達もいなくなってくる。すでに死んでしまった友人も多くなるし、交際範囲も狭くなるから出会う機会もない。ひどい場合は、配偶者や子供などの家族も、いなくなってしまうことがある。
さらに、たいていの場合、年寄りは嫌われる。子供や若い人たちは、どこへ行っても歓迎してくれるが、年寄りはあまり歓迎されない。ときにはかなり露骨に、やっかいもの扱いされることがある。
きわめつけは、寝たきりになってしまうことだ。下の世話をされることは、する方もイヤだろうが、される方だって、尊厳が傷つけられてイヤなものなのだ。そのうえ、部屋が臭いとかいわれて嫌われる。ついには壁の向こうから「いい加減に早く死んでくれないかしら」などという声が聞こえてきたりする。
それでもまだ、お金がたくさんあればいい。お金がない老人ほど惨めなものはないだろう。ヘルパーも満足に来てもらえず、家族からも単なる「穀潰し」「やっかいもの」とされてしまう。ひとり貧しく狭い部屋で、病気になっても誰からも気づいてもらえず、孤独にひとり死んでいくことになるかもしれない。
このように、歳をとるということは、まさに踏んだり蹴ったりの状態になることだ。
こんな現実を、いったいどのように受け入れていけばいいというのだろう。若いときのような、豊かな感受性をそのまま維持していたら、それこそ気も狂わんばかりの拷問ではないだろうか。
そこで、ぼけてしまう、という「癒し手」が忍び寄ってくるのかもしれない。ぼけてしまうことを多くの人は恐れているが、しかし、ぼけて、自分がおかれた悲惨な状況を理解できなくなれば、心の平安を得られるかもしれない。ぼけてしまうことは、まさに恩恵なのかもしれない。
けれども、それでもなお、ぼけてしまうこと自体が、人間の尊厳が失われていくような気がして、ぼけることだけは避けたいと思う。たとえ老いの厳しさに苛まれるとしても。
ならば、いったいどうすれば、老いても幸せでいられるのだろうか?
そのためには、まず健康であること、現役時代に仕事が順調に運んで退職金と年金がもらえ蓄えも十分にあり、自分の家を所有してローンがないこと、結婚して子供が生まれ、その子供がまともに育って孫をもうけること、配偶者も健康で元気なこと、しかも夫婦円満であること、家の中には子供夫婦と孫が同居し、親孝行な子供と孫から、敬愛されること、自分のことを慕って訪ねてくる友人や仲間がいること、そして死ぬときは、寝たきりになることなく、ぽっくりと逝くこと・・・だ。
だが、こんな条件をすべて満たした人が、世の中にどれくらいいるというのか?
それでも、こうした辛い老いの状況において、少なくてもひとつだけ、「よいこと」がある。それは、死を怖れなくなることだ。それどころか、早く死が訪れてこの辛い状況から解放してくれないかなと望むようになるかもしれない。若いときや、未来に希望をもって充実して生きているときは、死は恐ろしく、何としても避けたい恐怖であろう。死の恐怖を克服することは容易なことではない。
だが、悲惨で孤独な老後を生きていれば、その死が、何よりも甘美な「癒し手」のようにさえ思えてくる。そうして死の恐怖を克服できることが、辛い老いを生きることの、かけがえのない報酬なのかもしれない。
7月10日 功徳のバーゲン・セール
テレビのニュースを見ていたら、浅草の浅草寺が映っており、たくさんの人がお参りにやってくる光景が見えた。なんでも、7月の10日は、この日にお参りすれば、四万八千日お参りしたのと同じ功徳が得られるという。
このような民間信仰の言い伝えに、いちいち目くじらを立てることも大人げないのかもしれないが、このニュースを見て、バーゲン・セールや、悪徳商法の手口を連想してしまった。
「本日限り、だいこんが半額!」
「えびの養殖事業にいま投資すればもうかります。チャンスは今だけです!」
一日だけお参りすれば、本当に四万八千日お参りしたのと同じ功徳がもらえるのだったら、誰も苦労はしない。もし、本当にここに二人の人がいて、ひとりは四万八千日、熱心にお参りして、もう一方は7月10日に一日だけお参りしただけであるとして、この二人が同じ功徳だとしたら、人生に修行もなにもあったものではない。仏教が説く法(ダルマ=宇宙の法則)では、本当にそんなことを認めているのか? だとしたら、正直にコツコツ努力する者は馬鹿者ということになる。
あるいは、そんなことはないというのなら、仏教では嘘が行われていることになる。嘘をつくことは、仏教の戒律では、虚妄罪科にあたるはずである。戒律を破っていることになる。
私からいわせると、このような「むしのいい」話は、日本に限ったことではない。チベット仏教の寺院などへ行くと、くるくると回転する鐘のようなものがあり、それを一回まわすだけで、マントラを数多く唱えたのと同じ功徳があるといっている。それで、僧や在家信者などが一生懸命にその鐘みたいなものをくるくると回している。
宗教とは、日常生活から遊離してはならないが、それでも日常的な世俗の塵から離れたものをもっていなければならないと、私は思う。仏教の象徴である蓮の花が、汚泥の上に咲くが花そのものは汚泥にまったく汚れないように。
このように、世俗から超然とした、清らかで聖なる領域があるからこそ、宗教に慰めや魂の救いが求められるのではないだろうか。世俗では正直者がバカをみるし、不条理なことが起こるし、権力や金持ちだけがいいめをみるようなことがまかり通り、ちゃっかりと人をだしぬいてうまいことしてトクをしたりとか、汗水たらしてお金を稼ぐよりギャンブルや投資でもうけて醜い傲慢さを発揮するとか、打算ばかりで真心がないとか、陰で人を苦しめているような人間が成功や幸運に恵まれるとか、そういう不公平で汚いことだらけなのだから、せめて宗教だけでも、そうしたこととは無縁の、清らかな純粋性を保っていて欲しいものだ。
だからこそ、宗教に魂の救いを求めようという気にもなる。だからこそ、宗教を信じることで、世俗ではずるい生き方をした方がトクであるとしても、自分だけはそんなことはせずに正直にまっとうに生きようという気持ちにもなるのではないか?
そのような純粋性を人に教えるはずの宗教が、「功徳のバーゲン・セール」のような俗っぽいことを説いて、いったいどうするのだろうと思う。
もちろん、世の中には、非常に辛い状況にある人がいる。そんな人はわらをもすがろうという気持ちであろう。たとえば、家族に病人がいて、その病気を治してあげたいという思いで、功徳のある7月10日の今日、お参りに来るという人もいるかもしれない。
もし、本気で功徳があると信じるならば、それが暗示になって、本当によいことが起こるかもしれない。結果的には、確かに功徳があったということになる。
しかし、病気を治したいためにお参りにくる、つまり、神仏に救いを求めるというのであれば、要するに、病気を治してくれるなら、神仏でなくてもいいわけだ。貧乏を救ってくれるなら、神仏でなくてもいいわけだ。他に悩みを解決してくれるものがないから、仕方なく、神仏にお参りに来るということであろう。
賽銭箱にお金を入れて「願いを叶えてください」と祈るのは、要するに、自動販売機にお金を入れて商品を手に入れようとする発想と、まるで変わらない。
人間は弱いから、病気や貧乏を助けてくださいと神仏にお願いするのは、無理もないことであるし、決して悪いことではないとは思う。神仏は慈悲に満ちているだろうから、人間のそういうことも理解してくれるはずだ。
しかし、もし、それだけしかしないのであれば、それは信仰でもなんでもない。単なる「商取引」をしているに過ぎない。
宗教の本当の目的は、そういう世俗的なことから超然とする高い心境を開発することではないだろうか。「7月10日は功徳のバーゲンセールをしますよ!」などといわれても、そんなことをよしとしない、潔い境地を得ることではないのだろうか?
それなのに、宗教が率先して、いかにも世の中には、「うまい話」があるかのようなことを説き、むしのいい欲望を煽って、悪徳商法にだまされるようなカモを養成するようなことをして、いったいどうするのだろう。