
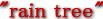 vol.22
vol.22
田村奈津子詩集 虹を飲む日
1996年 あざみ書房刊 \1500 注文できます。 あざみ書房刊 \1500 注文できます。
<往復詩集>わがまま詩篇 田村奈津子詩集『虹を飲む日』(1996年あざみ書房刊)より
|
 文化鍋に月を入れて
文化鍋に月を入れて 彩られた夜(エッセイ「イルカの微笑み」)
彩られた夜(エッセイ「イルカの微笑み」) 冬の旅
冬の旅 見えない風景
見えない風景 愛しの六十二分
愛しの六十二分 青い水(エッセイ「死者の言葉」)
青い水(エッセイ「死者の言葉」) 赤い月、赤い耳
赤い月、赤い耳 新しい月、新しい鉄
新しい月、新しい鉄 満ちる月、欠けた太陽(エッセイ「思い出したニホン人」)
満ちる月、欠けた太陽(エッセイ「思い出したニホン人」) 眼差しの森
眼差しの森 砂漠のバラ(エッセイ「羊の香り」)
砂漠のバラ(エッセイ「羊の香り」) 優しいマグマ
優しいマグマ 黄色い声
黄色い声 みどりの指
みどりの指 リトアニアの青い空(エッセイ「光に溶けるからだ」)
リトアニアの青い空(エッセイ「光に溶けるからだ」) 虹を飲む日(エッセイ「オレンジ色の場所」)
虹を飲む日(エッセイ「オレンジ色の場所」)
文化鍋に月を入れて………November23 1994
|
| |
| | やがて月が満ちる
| | K画伯に呼び出されて
| | 夜の階段を スキップでかけおりると
| | 底には 本当にミロがいて
| | 文化鍋で「兜蟹」を煮込んでいる
| | 月にうろうろ カニ族の勘が横ばいする
| | 浮世の泡をつなぐ 偶然の一冊
| | センセイ 西江先生 西荻の街で
| | またお目にかかれるなんて 思ってもみませんでした
| | いろいろな動物になることを 試みてこられたセンセイが
| | ミロの友達だったなんて
| | 犬猫が皮を 無意味に切り取られる時代には
| | 何を食べればいいのかよくわかりません
| | 文学部181教室から いま
| | センセイの渇いた大きな笑い声が甦ってきました
| | ニホンの言葉が異境に別れていく
| | そんな時代は 先生の耳が端麗です
| |
| | ミロの瞳に月が満ちて
| | 今宵眠れない人に 朗報が浸透する
| | あなたの感情は 正しい波動だった
| | 実は センセイ
| | わたくしの この十年は 蜃気楼のようでしたよ
| | あぶくなんて ちっとも たたなかったのです そう はじめっから
| | 太いくせにすかすかの骨を
| | 栄養失調でめまいしたカラダで煮込んでも
| | おいしい鍋などできるはずもなく
| | 未開でよかった
| | わたくしの あたま
| | ラクダでよかった
| | わたくしの せなか
| | あの頃聞いた センセイの文化人類学の授業だけが
| | 瘤のなかの 脂肪で
| | ほら いま 焼酎が溶かしはじめているのです
| | らんぷの光に 灯油の匂い漂い
| | ミナカタクマグス全集に 『東京のラクダ』*走り
| | あなたの鍋は そろそろ あぶくたった 煮え立った?
|
*『東京のラクダ』(1994)―西江雅之著 |
 <詩>彩られた夜(田村奈津子)
<詩>彩られた夜(田村奈津子)
 <詩>「植物地誌」ダイズ(関富士子)
<詩>「植物地誌」ダイズ(関富士子)
 <詩>音の梯子(関富士子)
<詩>音の梯子(関富士子)
彩られた夜………November 29 1994
新宿ピットイン『CLUB LEO』に陶酔するJに
|
| |
| | レナードが 和太鼓を一打ちする
| | からだは出し抜けに目を覚まし
| | 背骨を思い出す 足が動き始める
| |
| | 麻衣さんが 母音を発声する
| | 細胞は門を解き放ち
| | 歌に乗った魂が からだから抜けていく
| |
| | 板橋さんは 音と戯れているから
| | 澄ました旋律は 今日は不在だ
| | それでも感情を撫でられたくて
| | 誰もが 子音を待ち焦がれている
| |
| | その夜 何が起こるのか
| | 誰も予測がつかなかった
| | その夜 何が起こったか
| | やがてわかる日が来るはずだ
| |
| | 右の頭皮が 痺れている
| | 木枯らしの顔が 火照っている
| | 言葉は どこかへ消えてしまった
| | ただ ビールがおいしい
| | そんな かんたんな夜に
| | 太鼓は天地を揺るがす
| | 声は深海からあふれだす
| | ピアノは星界を受信する
| |
| | わたしたちは 今夜
| | 解体されて 光の中ではじけている
| | わたしたちは 今夜
| | 細胞を からだのなかで泡立たせている
|
*太鼓ーレナード衛藤、ボーカル−山根麻衣、ピアノ−板橋文夫
イルカの微笑み December 18 1994
11月29日のピットインでのライブのあとすぐに、山根麻衣さんと、妹さんの栄子さんのお宅で、ゆっくりお話する機会に恵まれた。ライブの話はもちろんのこと、その夜は、鍋を囲んで、それぞれの身の回りで起こっている変化の兆しを報告し合うというおもしろい展開になった。中でも一番興味深かったのは、麻衣さんが今年の9月に下田の海でイルカと泳いだときの話だった。具体的な出来事一つ一つに、心ひかれたわけではなく、映画『グランブルー』のイルカの微笑みを想い浮かべながら聞いていると、体験者の語りを通して、自分もだんだんうれしくなっていくのがわかって感動した。そのうちに妙なことに気がついた。元々彼女がエネルギッシュな歌手であることは事実なのだが、向き合って話していると、頭の右側がピリピリと心地よく振動することに気づいたのである。
不思議に思い翌日、『ドルフィン・コネクション』という本を読んでみると、イルカに会ってきた人には、イルカの生体電気が流れていて、それが放射されているのだと書かれていた。そんなこととは知らずに、イルカの話に耳を傾けているだけで、何か気持ちの良いものが受け取れるとしたら、素敵なことだ。
イルカに会った人には、会ってみるべきだ!
|
|
 <詩>冬の旅(田村奈津子)
<詩>冬の旅(田村奈津子)
 <詩>文化鍋に月を入れて(田村奈津子)
<詩>文化鍋に月を入れて(田村奈津子)
冬の旅………December 18 1994
|
| |
| | 黄色が去ったばかりの
| | スカスカと
| | 何かが澄んでいく
| | 空に根をはる
| | はだかの梢を見上げていたら
| | 今朝の夢をつたって
| | くるみを抱えた
| | シマリスがのぼってきた
| |
| | 『霧の中の風景』*から
| | 動物の知恵を持つ
| | 子どもが二人現れ
| | 老木とあいさつを交わしている
| | (アレハ アメノウズメノミコト?
| |
| | からだを響かせ
| | 声をなびかせ
| | 八雲立つ原野で
| | 待ち合わせしたのは
| | いつのこと?
| | いくつもの詩を放ち
| | いく人ものワタシを脱いだら
| | 神話は甦る
| | どんな闇にも
| | どんな混沌にも
| |
| | 時間が消えた古書店の
| | 棚から落ちてきたのは
| | 『世界は音』**
| | 千年も探し続けていた本だった
| | 柚子色にふくらんだ月の
| | 冴えた光を浴びて
| | 地球のつぼみは
| | 今宵 やっと
| | ほころび始めたばかりだ |
*『霧の中の風景』(1988−テオ・アンゲロプロス監督
**『世界は音』(1986)−J・E・ベーレント著
|
 <詩>見えない風景(田村奈津子)
<詩>見えない風景(田村奈津子)
 彩られた夜(田村奈津子)
彩られた夜(田村奈津子)
見えない風景………January 17 1995
|
| | わたしの部屋は狭い
| | 白いロフトベッドの下にテレビがあり
| | 今朝からガレキと火災の映像が流れ続けている
| | さっき遊びにやってきた
| | ポーランド人の絵描きと
| | ニホン人の写真家が
| | 無言で新聞に溜め息をおとしたあとで
| | わたしの書架の本を頼りに
| | たがいの世界を探り合っている
| | 部屋に浮かんだ雲のようなベッドでは
| | 眠りから異界に入った
| | 霊媒の友人が
| | 突然の死者たちを悼んで寝汗をかいている
| | 宇宙のエネルギーに直に触れた
| | 彼女のからだには断層ができ
| | 内臓がバラバラになって浮遊しているらしい
| | わたしの国は狭い
| | 一瞬で東と西に分断されてしまった
| | 神戸市東灘区に住んでいる
| | 叔父にはまだ電話がつながらない
| | 曇った頭でキッチンに立ち
| | 満月の晩餐のために
| | 鶏モモ肉を白ゴマと七味で炒めた
| |
| | わたしの惑星は狭くなった はずだが
| | 壁の崩れたベルリンを抜けて
| | 東欧に向かっても
| | ポーランドの友人の
| | こわばった記憶にはなかなか辿り着けないだろう
| | 『地下水道』を潜り抜け
| | 灰をかぶったつもりになっても
| | ズブロッカを流し込んだ凍える瞳に
| | 映った風景は
| | 決して見えはしない
| | あなたの宇宙に
| | 静かに耳を傾けていたい
| | 何もできない冬に ただそれだけ
|
|
 <詩>愛しの六十二分(田村奈津子)
<詩>愛しの六十二分(田村奈津子)
 <詩>冬の旅(田村奈津子)
<詩>冬の旅(田村奈津子)
愛しの六十二分………February 20 1995
|
| | 山羊座の人と
| | 六本木に
| | 映画を観に行った
| | 冬の旅は
| | 東欧から
| | バルト海を渡り
| | 北欧へ向かう
| | 仏頂面で クール
| | 唐突で マヌケな
| | 二組の男女と一緒に
| | グループ交際の
| | 六十年代へたどりつく
| | ここでは はぐれかけた空気が
| | 足踏みミシンで振動している
| | ロケンロールと
| | 扁平のリーゼントがあって
| | 笑い顔と
| | 色がない
| | この世界では
| | 消されかけた記憶が
| | ネッカチーフをかぶる
| | 『愛しのタチアナ』*の
| | 古びたカメラでスクラップされている
| | 拳銃もなく
| | 殺し合いもない
| | 六十二分間は
| | 鎮圧される魂が
| | 追われることもない
| | アキ・カウリスマキ監督の
| | 左眉の笑いに
| | からだがほころんでいく
| | カウリス(山羊)と
| | フィン語で名付けられた
| | 遅すぎた怪物は
| | 世紀末から断絶しようと
| | 坂道をゆっくり上っていった
|
*『愛しのタチアナ』(1994)-アキ・カウリスマキ監督
|
 <詩>青い水(田村奈津子)
<詩>青い水(田村奈津子)
 <詩>見えない風景(田村奈津子)
<詩>見えない風景(田村奈津子)
青い水………March 14 1995
|
| | たくさんのひとが
| | 通り抜けていく
| | からだのエナジーが
| | 凧のように引っぱられる
| | 風の中で
| | 光の中で
| | わたしの時間がめくられ
| | 明かされる
| | 星々の道筋
| | 手のひらから
| | あふれる光で
| | 綾取りして
| | 何を思い出したか
| | 突然の日常がはじまる
| | 風よ吹け
| | 風よ舞え
| | 笛のように わたし
| | あなたに叫びたい
| | 雲に乗った女が
| | 砂漠に降りてくる
| | よかったね
| | 今晩は
| | 痛かったね
| | トランジット
| | 移行する空間に
| | 溺れかけても
| | 飛び込みたいのは
| | 青い水の
| | 誘惑
| | 老人に抱かれた
| | 黒いむく犬が
| | 夢の中で
| | 目を覚ました
|
死者の言葉 March 14 1995
ロバート・アルトマンが、レイモンド・カーヴァーの短編小説と詩をもとに映画化した『ショート・カッツ』は、パノラマの真ん中にいるみたいで、とても刺激的だった。恵比寿のビール工場跡地にできた映画館は、ゆったりと快適な座り心地で、人間模様の曼陀羅の中をぐるぐる巡っているような気になった。アルトマンの底力に、年の功という言葉を再確認させられた。
カーヴァーの作品の中で私が一番好きなのは、詩集『水の出会うところ』に入っている「父のさいふ」という作品だ。父親が死んだあとに残ったさいふにまつわる詩だ。命を失ったそのさいふから葬儀代を支払い、父親は故郷の墓地への最後の最高の旅に出かけるというような詩だった。それを読んだせいかどうかは忘れてしまったが、うちにも父の死後しばらく「父のさいふ」が存在していた。不思議なもので家族の誰かの誕生日近くになると、父親が係わったテキストのわずかな印税が入るという知らせが届いた。空っぽになっていたさいふには、食事に行けるくらいのお金が巡ってきた。「これでなんかうまいもんでも食べてこいや」という父の声が聞こえてくるようで、私はなんだか嬉しかった。勝手な思い込みなのだろうが、死者の意志を感じてしまうことがある。 |
|
 <詩>赤い月、赤い耳(田村奈津子)
<詩>赤い月、赤い耳(田村奈津子)
 <詩>青い水(田村奈津子)
<詩>青い水(田村奈津子)
赤い月、赤い耳………………May 9 1995
よみうりホールにて
ティク・ナット・ハンのダルマトークに耳を傾けるJに
|
| | ヴェトナム生まれの詩人で
| | 仏教者の
| | ティク・ナット・ハンを迎えて
| | のパンフレットは
| | 赤い薔薇のこだま
| | 彼の瞳は澄んで
| | 耳は空に開かれているので
| | 嗚呼! キレイ ナンテキレイ
| | と溜め息をつきながら
| | 一枚 また 一枚
| | もらってきては眺めてしまう
| |
| | 半月に
| | 共鳴する鐘の音
| | 静かな言葉を
| | 一枚 また 一枚
| | からだに染み込ませた
| |
| | 耳を傾けなさい
| | 目覚めた人はそう言った
| | ハングリーゴースト(餓鬼)の
| | あふれるワタクシタチの国には
| | 聴く人
| | が少ないので
| | 聴くふりをする人
| | を見分けられない
| | 目覚めた人は いつも
| | 微笑んでいて
| | ワタクシタチの国は 今にも
| | 泣き出しそうだ
| |
| | 赤い月が 静かな水に映り
| | 赤い耳が 熱く深く広がった |
|
 <詩>新しい月、新しい鉄(田村奈津子)
<詩>新しい月、新しい鉄(田村奈津子)
 <詩>青い水(田村奈津子)
<詩>青い水(田村奈津子)
新しい月、新しい鉄………july 28 1995
|
| | 七月二十一日
| | 月と冥王星が引きあって
| | 天空に暗号が刻まれた
| | からだの双六を逆戻り
| | 自分を捜そうとするから
| | 耳から鬼が入ってきた
| | 私は鉄の生まれだ
| | うたれてうたれて
| | 魂の形を作る
| | タタラの土地で
| | 蟹座に生まれ
| | 夏の子供と名付けられた
| | 私のなかの炎も
| | サナギに似ているだろうか
| |
| | 新しい月が巡るたびに
| | 記憶がはがれて耳が裸になっていく
| | たたかれてたたかれて
| | 頑固な夏が育っていく
| | 私は鉄の生まれだ
| | 哲学の男と名付けられた父親は
| | 乙女座に生まれ
| | タタラの土地へ
| | 移り住んだ
| | 彼の魂が
| | サナギから蝶になり
| | 彼岸に飛び立ってから
| | 七回目の神在り月が巡ってくる
| | スサノオの風を呼び込み
| | 遮光器土偶のおんなのように
| | 目を閉じて
| | 耳を開いて
| | 闇と交わりたい
| | 私は鉄の生まれだ
| | からだの炉で炭を焼き続けるのだ |
|
 <詩>満ちる月、欠けた太陽(田村奈津子)
<詩>満ちる月、欠けた太陽(田村奈津子)
 <詩>赤い月、赤い耳(田村奈津子)
<詩>赤い月、赤い耳(田村奈津子)
満ちる月、欠けた太陽………August 18 1995
|
| |
| | もう 帰ろうよ
| | あんな森は出ようよ 父さん
| | 里に向かって歩く
| | 子供の私が
| | つないだ右手を揺すっている
| | 待ってやれ
| | もう少しだけ 一緒にいてやれ
| | あいつが自我(太陽)で迷っている
| | そう言って亡父は
| | ヘマタイト(赤鉄鉱)の咲く
| | 山に戻っていった
| | そう言われて私は
| | パイライト(黄鉄鉱)の光る
| | 朝に目を覚ました
| |
| | あいつには
| | 太陽が謎めいている
| | あいつは
| | 太陽(父)に出会いそこなった
| | あいつの
| | 太陽が欠けている
| | 満ちていく月が
| | 気を引っぱり 熱を上げ
| | 彼の耳を狂わせた
| | 聴覚がかすんで地図が見えない
| | 真夏に迷う古都で
| | こうなったら あんた
| | 犬になりなさい
| | こうなったら 弟よ
| | 維新の道で父を探しなさい
| | 澄んだ空には盆の月
| | 吠えているのかいないのか
| | 眠りこけてた犬(自己)が瞑想する
| | 汗ばむ鼻が嗅ぎ当てたのは
| | 東山、坂本竜馬の墓だった
|
思い出したニホン人 August 18 1995
八月十六日の朝日新聞に、オウム真理教の都沢和子被告、初公判の記事が載っていた。七年前の「独房」での修行を終え、悟りを得たときの感想だという彼女の言葉もあった。「一番に思ったのは『この世はなんて汚いんだろう』ということです。外に出て、車の中から眺める景色は、鉄やビルがとても冷たい感じでした。食べ物屋が浅ましく見え、スーツを着た人間が異様に見えました。何かひもでその人の体がグルグルと縛られて、解放感がないように感じました。」と。本当に悟りを得ると、もっと風景は優しく見えるようになるんじゃないのかなぁと、私は不思議に思った。読んでいるうちに小学五年生の春の記憶が甦ってきた。西ドイツの小学校から、京都の小学校に戻ったときのことだ。
世の中が汚いとは思わなかったが、日本の街は無神経な顔をしているように感じられた。教室に足を踏み入れると思春期の入口で自意識過剰な子供たちが、男子と女子に分かれて不自然な様子で座っていた。全員の黒髪に圧倒されてめまいがしそうになった。
ある日いきなり背中に、金魚鉢の水を入れられた。誰もとがめてはくれなかった。プライドがあったのでいじめられたとは思わなかったが、時折思い出すときのニホン人は、怖くて異様だ。
|
|
 <詩>眼差しの森(田村奈津子)
<詩>眼差しの森(田村奈津子)
 <詩>新しい月、新しい鉄(田村奈津子)
<詩>新しい月、新しい鉄(田村奈津子)
眼差しの森………October 31 1995
坂田栄一郎写真展『アマランス』−新宿パークタワーにて
|
| |
| | 歌子さんから電話があって
| | その写真家のドラマチックな
| | 星の巡りが
| | 私の水星につながると
| | カラダを抜けた想いが もう
| | 新宿の森に舞い込んでいた
| | 北風にまかれて
| | くじいた足をひきずって
| | あとから自分を運んでいった
| |
| | 二進法の窓とすれ違って
| | 新しいビルの
| | 通路を曲がると
| | アマランスが香っていた
| | ねじれた足首は
| | 右と左に分かれる脳に
| | ストップをかける
| | あらわれているものは何?
| | 眼差しの触手が
| | 撫でて溶かす関節
| |
| | ユーディ・メニューインの手
| | ミハイル・ゴルバチョフの額
| | ネルソン・マンデラの歯
| | いくつもの肖像から
| | 光の粒子がにじんでいる
| | 空に近い眼差しから
| | 神様がこぼれてくる
| |
| | 立ち止まりたい ここで
| | 人間にみつめられる この森で
| | もつれた神経を大地にほどき
| | 詩の身体を植物に変えて
| | 始まりの種に戻りたい
|
|
 <詩>砂漠のバラ(田村奈津子)
<詩>砂漠のバラ(田村奈津子)
 <詩>満ちる月、欠けた太陽(田村奈津子)
<詩>満ちる月、欠けた太陽(田村奈津子)
砂漠のバラ………December 12 1995
|
| |
| | 泳げないひとはしかし
| | せめて自分のからだの海で
| | 溺れることだけは
| | 避けたいと願い
| | 時折 異常な勢いで発熱する
| |
| | 水の太陽
| | 火の月 を
| | 九十度の角度で
| | かかえた女の
| | ミクロコスモスでは
| | 火と水が(ひみつ)の戦いを
| | いや 秘密の和解を取り結ぼうと
| | 砂嵐が 脳を吹き抜けては視床下部を狂わせる
| |
| | 熱風の夢砂漠に
| | ローズ色の稲妻が走った
| | 氷の屋根裏に住む
| | オシリスが
| | 天球儀をかかえて落ちてきた
| |
| | 泳げないひとはしかし
| | からだの水が四十度の熱で
| | 蒸発するのがうれしい
| | まぬけな話ではあるが
| | 埋もれていた土地が
| | 記憶の海から浮上し
| | とんでもない感情が運ばれてくるからだ
| | なじみの風景が変わる
| | オリオンが光る
| | やがて土地から水がにじむ
| | 砂嵐が去ったあと
| | 蟹座の人体には
| | 石でできたバラが咲いているだろう
|
羊の香り December 12 1995
一九九五年は、自分の意志と無関係に移動せざるを得ないことの多い一年だった。弟が突然ニュージーランドで結婚式を挙げたいと言い出したときもそうだった。「そんな芸能人みたいなことやめてくれよ」とブツブツ文句を言いながらついて行き、結局一番ニュージーランドを好きになって帰ってきたのは、私だった。
しかし、何がよかったかと問われて熱っぽく語れるような体験は、ほとんどない。天候が悪く、鯨にもイルカにもペンギンにも会えなかった。気の毒に思ってくれたガイドさんが、牧場に羊の赤ちゃんを見に連れていってくれた。だだっぴろい土地に立って、深呼吸をすると、スカッと自分が抜けていくように感じられた。
ニュージーランドはイギリスに似せて作られた国だから、街並みは小英国という印象だが、空気中の人工密度は、やけに低いように感じられた。イギリスの空間には、目に見えない生き物がたくさん住んでいて、細胞が直に反応してしまうような迫力を感じたことがあったが、歴史が浅い分、ニュージーランドの空間は何だかスカスカしているのである。
それが頼りなく思われる場合もあるだろうが、私には妙に爽快だった。そのかわりに、隙間を埋めるように、街やホテルは羊の香りで満ちていた。
|
|
 <詩>優しいマグマ(田村奈津子)
<詩>優しいマグマ(田村奈津子)
 <詩>眼差しの森(田村奈津子)
<詩>眼差しの森(田村奈津子)
優しいマグマ………January 1 1996
|
| |
| | 長い間あなたを待っていました
| | 「熱い熱い」と震えながら
| | この店の片隅で
| | あなたが気づいてくれるのを
| | 涼しげな水晶にしか
| | 目もくれなかったあなたが
| | 暗黒のわたしを覗き込み
| | 混沌のマグマに
| | 飛び込んでしまう日が
| | やがて来るだろうと
| | 待ちきれず 火山から
| | あなたに会いにやってきたのです
| |
| | 今日のあなたは
| | 眼差しが強い
| | 目覚めた細胞があなたに
| | 交信している
| | 優しい影が噴出している
| |
| | あなたは 気づいている
| | アンテナの髪を伝わって
| | 頭皮がピリピリすることに
| | あなたは 感じている
| | 指先から二の腕にむかって
| | 電気が走っていることを
| |
| | 球になったわたしを手に取って
| | 耳を傾けてください
| | 浮き上がった緑の同心円は
| | 笑われたあなたの記憶です
| | もう何も 恐れないで
| | 黒曜石(わたし)は
| | 冥界の痛さを溶かす瞳だから
|
|
 <詩>黄色い声(田村奈津子)
<詩>黄色い声(田村奈津子)
 <詩>砂漠のバラ(田村奈津子)
<詩>砂漠のバラ(田村奈津子)
黄色い声………January 31 1996
|
| |
| | 石毛拓郎の名前には
| | 石が二つも鎮座している
| | 石を割って聞こうとしている
| |
| | センセイ イシゲ先生
| | 今日 突然
| | 学校と縁が切りたくなった
| | 石の言葉で割れそうになった
| | そんな僕は
| | どこへ行けばいい?
| | とりあえず
| | 二日 学校を拒否する
| | そのあと
| | 石のように暗い僕は
| | どこへ転がればいい?
| |
| | 闇い脳も 光り
| | デクノボーもひとつの青い照明
| | あの人が言った言葉が 光り
| |
| | 黄色い声が欲しい 僕
| | の名を呼ぶ 声
| | に めま
| | いがす る 僕
| | は 頭のな
| | かで 走り続け る
| |
| | 桜が散る頃
| | 僕は僕を助ける
| | 教室には戻らない
| | でも センセイ 憶えていて
| | 学校と別れても
| | カラダとは別れない
| | 僕は光り 闇い石の僕は
| | 声に包まれた光り |
|
 <詩>みどりの指(田村奈津子)
<詩>みどりの指(田村奈津子)
 <詩>優しいマグマ(田村奈津子)
<詩>優しいマグマ(田村奈津子)
みどりの指………February 22 1996
|
| |
| | 純情なきみを
| | のぼせあがらせた
| | あいまいな言葉
| | 影のない楽観主義を
| | もう信じてはいけない
| | きみが教室を出るというのなら
| | わたしの地下壕
| | ホロスコープ*第十二室
| | 無意識の部屋から
| | 大逆転のウラヌス(天王星)
| | 「伝統破りの星」をなんとか
| | 引きずり出す覚悟をするだけだ
| |
| | 一九九六年一月十二日
| | 水瓶座に天王星が移動した
| | わたしがわたしの
| | 泣き虫の子供をくぐり抜け
| | 魚座の記憶を破壊する
| | 新しい風を呼吸して
| | 戸惑うきみを夢に溶かし込んだ
| |
| | みえない言葉が
| | 飛び交う街を
| | アトピーの膚をさらして
| | きみは漂い続ける
| | もっと気紛れに
| | わがままな身体になればいい
| | 嘔吐に変容する言葉を
| | 洗い流す光りを
| | 集めるアンテナは
| | きみの切り忘れた爪が無防備な
| | みどりのゆび
| | その光る指先だけが道標だ |
*ホロスコープ‐占星術で使われる星の配置図
|
 <詩>リトアニアの青い空(田村奈津子)
<詩>リトアニアの青い空(田村奈津子)
 <詩>黄色い声(田村奈津子)
<詩>黄色い声(田村奈津子)
リトアニアの青い空………March 14 1996
停電の夜に
|
| |
| | オレンジの香りを溶かす
| | ロウソクの炎にあぶられて
| | この浅い闇から
| | やってくるのは 誰?
| | 二時間四十五分の穴に
| | 耳を澄ます
| | 電気工事の向こうに
| | 耳を澄ます
| |
| | (静かな場所)をおとずれて
| | それはおもいがけず
| | モノクロの写真
| | 樹間に吊られたデトロイトの
| | 等身大のぬいぐるみの人形から
| | リトアニアの青い空へ飛んだ
| |
| | あの瞳 あのうつろな瞳
| | きみの声変わりスレスレのからだで
| | うごめいている妖怪はいつか見た
| | リトアニアの画家
| | スタシスの作る仮面
| | 木の膚に金魚色の唇
| | 太い鼻と灰色の瞳
| | 見つめられて人間が壊れそうになる
| | 「石」と名付けられたその仮面が
| | つつましやかに生きる森へ
| | きみの指ときみの夢を
| | 停電の夜に地下工事でつなぐ
| |
| | トウキョウの闇に棲む妖精に
| | 耳を澄ます
| | 灰色の瞳に満ちるリトアニアに
| | 耳を澄ます
| | 仮面の裏側で連続するドラマに
| | 耳を澄ます
|
*詩集(静かな場所)(1981)-吉増剛造著
**スタシス(1949)-リトアニア生まれの画家。1976年にポーランドへ移住。
光に溶けるからだ March 14 1996
『境界を超える対話』というテーマで、五月二十四日から五月二十七日まで、南伊豆国民休暇村で行われる「トランスパーソナル学会議」の手伝いをしている。スタッフの編集者に薦められて『ホリスティック・コミュニケーション』(春秋社)という本を読んだ。私は原題の『トランスパーソナル・コミュニケーション』のままのほうがよかったのではと思ったが、興味深い本であることは間違いない。このコミュニケーションの技法を実際に取り入れている学校が、日本にも存在するという事実にも感動した。
「自分の内部でのコミュニケーション」「対人的なコミュニケーション」「自我を越えたコミュニケーション」の方法を、呼吸、座り方、立ち方、歩き方、リラクセーション、注意の集中、イマジネーションを通して、身につけて言うプログラムが具体的に提示されている。自分でもやってみたいと思うような実習がたくさんある。
例えばエネルギーだけになること――エネルギー覚醒のふつうの次元を超えて、からだの限界を越えた純粋なエネルギーとして自分自身を体験する。仰向けになり目を閉じて、光の中に溶ける身体をイメージするのだ。地球のすべての生命あるものとつながりを感じ、自分自身を信頼し、直観に従うことが基本の授業は、きっと刺激的だと思う。
|
|
 <詩>虹を飲む日(田村奈津子)
<詩>虹を飲む日(田村奈津子)
 <詩>みどりの指(田村奈津子)
<詩>みどりの指(田村奈津子)
虹を飲む日………June 12 1996
|
| |
| | 手のひらが抜けている
| | 小さな風が生きている
| | クチナシの庭を
| | 一緒に歩く人には内緒で
| | わたしはワタシを
| | 宇宙にハメコンダ
| | 左手は空に右手はぬくもりに
| |
| | (ツナガッタ
| |
| | 午睡に落ちた彼は
| | フラスコに色水を作る
| | 手をかざすと 虹が
| | いくつもの 虹が
| | 手のひらをくぐって上昇する
| | 呪文に乗って
| |
| | (カケアガル
| |
| | 虹をぼくは初めて見たんだ
| | ゴーグルをはずすといきなり
| | カクテルになって降ってきた
| | ブルーハワイの味で
| | 渦巻きながらぼくに入ってきた
| | 丸くなっておなかに
| |
| | (タマッテル
| |
| | からだを巡って大地へ還っていく
| | 眠る母は少女を起こし
| | クロマティックの河で
| | 「虹の蛇」を釣り上げた
| | 彼女のチャンネルが開いていく
| | 光に合流した魂が
| | 色彩の鳥を羽ばたかせた
|
オレンジ色の場所 July 22 1996
『午後のオレンジ』というタイトルの宮迫千鶴さんのコラージュ作品をながめながら、この文章を書いている。「トランスパーソナル学会議」の講演者の一人でいらした宮迫さんのエッセイ集『草と風の癒し』(青土社)は、私が近頃一番気に入っている本だ。
彼女と私が、お互いの父親をガンで失ったのは七〜八年前のことだ。やっと喪が明けた状態が訪れたと言えるようになった頃に、学会で直接お目にかかり、お話を聞かせていただく機会に恵まれた。タイミングよく、バリ島での体験がモチーフになっているという今年の個展にも間に合った。画廊では、色彩が形になって、リズミカルに浮遊していた。
宮迫さんのエッセイは、魂の癒しの旅の道中で起こってくるシンクロニシティのエネルギーに、軽やかに乗って書かれているところが、私にはとても魅力的に思われた。そしてそのように書かれた作品は、読者にもその波動を伝え、共時性を起こしてしまう。
彼女はアイヌのシャーマンに出会い、死から生へ向かう転換点にたどり着かれたのだが、私もまた友人の写真家宇井眞紀子さんを通じてアイヌ民族に触れ、新しい風を感じていたところだった。アイヌの魂に癒された宮迫さんのオレンジ色は、私が生へ向かう転換点だ。
|
|
 著者紹介・作品一覧(たむらなつこ)
著者紹介・作品一覧(たむらなつこ)
 <詩>田村奈津子詩集『地図からこぼれた庭』
<詩>田村奈津子詩集『地図からこぼれた庭』
 <詩>リトアニアの青い空(田村奈津子)
<詩>リトアニアの青い空(田村奈津子)
 <詩>音の梯子(関富士子)
<詩>音の梯子(関富士子)
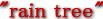 vol.22
vol.22